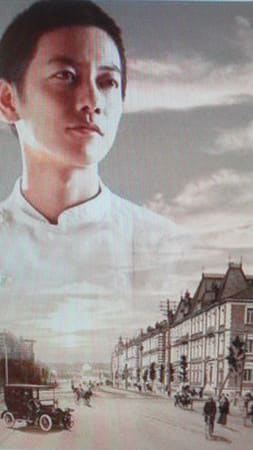『あん』
~「どら焼いかがですか!」~
1 出会い
ハンセン病を描いた作品は二度目。『砂の器』が初めだ。『あん』もつらい映画なのだろうと思って、映画館への足は少しばかり重かった。しかし違っていた。
カンヌ映画祭の作品(河瀬直美監督)である。ホントに映画っていいなと思った。美しかった。心を洗われ、そして力をもらった。

「あたし、50年間あんこを作ってるのよ」
映画が始まってすぐの、この徳江(樹木希林)の言葉で考えた。徳江の手は病(やまい)で侵されて、大きく形を変えている。十代で故郷を追われた徳江は、施設入所の時、母が徹夜して作ってくれたブラウスもみんな、洗いざらい処分される。患者は人と接触してはいけない。外部の人間は、施設/患者に近づいてはいけない。ハンセン病は、骨をも溶かす「忌(いま)わしい」病気だった。
「伝染性の強い不治の病」という世の中で、徳江が小豆のあんこを作ろうと思ったきっかけはなんだったろう。これは食べ物だ。豆にも水にも自分の手を浸(つ)けるのだ。毎日豆と話をして腕をあげたのだろうか。
「こんなに美味しい」
そう思い、施設の仲間とそう言い合い食べたのだろうか。身体に対する不安も、自分自身あったに違いない。それが日々の生活の中で少しずつ払拭(ふっしょく)されたのだろうか。
時を追うに従い、菌や伝染性の極めて弱いことが発見/解明される。治療法が確立される。それらの出来事に伴い、外に出たい/出られる思いが作られたのだろうか。長い年月と苦しみの向こうから、徳江が千太郎の店にやってくる。
「あたしが作ったあんこ、食べてみて」
と、徳江が差し出すあんこを、プレハブ小屋で店長をする千太郎(永瀬正敏)は、いったんは捨てる。しかし、
「つぶあんか」
と言わせることを忘れなかった。つぶあんだったから捨てた。徳江に対して「不浄(ふじょう)のもの」という見方を、一度も千太郎はしなかった。そんな人間の深い部分を徳江が見逃さなかったから、千太郎に声をかけた。あとでそれが分かる。
2 「世間」というあり方
徳江が小豆と会話しながら手塩にかけたあんこは、やがて小さな店の前に行列を作る。


しかし、客は波を引くように途絶える。徳江にはみんな分かる。でも、大量に売れ残ったどら焼を前に、そして素通りする人々を前に、招き猫を磨く。
このあと物語は、静かに進む。私たちははある期待をして観続けた。それはある部分で受けいれられ、ある部分では裏切られる。
中学生のワカナ(内田伽羅:樹木希林の孫)に誘われ、千太郎は施設を訪れる。徳江は静かに二人を迎える。はしゃぐでもない、かといって嫌な顔をするのでもない徳江の静かな顔から、様々なメッセージが流れて来る。千太郎は、そのメッセージをどう受け取ったらいいのか、身の置き場所に困るような躊躇(ちゅうちょ)をする。

幸せでした、という最後の徳江の手紙には、
「私たちはこの世を見るために、聞くために、生まれてきた」
としたためられていた。これは世間の非情を責める言葉ではない。千太郎と出会って、世の中を見ることが出来た感謝の言葉だ。映画は、誰が心ない噂をばらまいて客を奪ったのかという展開をしない。徳江は誰も責めない。千太郎は自分を責めた。
私は強烈に教えられた気がする。
○私たちが向かうのは「世間」や「世界」とは別な処(ところ)でいい
○私たちが向かっているのは「世間」や「世界」ではない
と教えられた気がしている。
私は「風評被害」なる言葉を、いきなり思い出した。自分に降りかかった災難を、他の誰かから「克服しなさい」「そうしないと復興しない」と言われる時の言葉だ。そして、せっかく丹精込めて作った米や野菜を、邪険にされる時に訴える言葉だ。徳江はそういう場所にはいなかった。

徳江の好きな桜が満開の公園で、千太郎がどら焼を売るラスト。客の来ない屋台で、やがて意を決したように、
「どら焼いかがですか!」
と声を上げる千太郎の頭は、もうボサボサの長い髪ではなかった。
土曜日の盛況だったのだろう。思いの外(ほか)、若い人が多かった。その満席の観客から、これも静かな拍手が起きたのだった。
3 補足
「癩病(らいびょう)」の意味を、ハンセン病と限定して、揉(も)め事を避けている辞書も多い。しかし、聖書や日本書紀の昔から登場する「癩病」が、固有の疫病(えきびょう)として分類されていたはずがない。「正体不明の恐ろしい病」程度の意味づけで始まっているというのが正確なところだ。ちなみに白川静の『字訓』によると、癩病の作りの「頼」の部分は、神から天与されたものを意味するので、癩病は神聖病だったという。中国は孔子の時代の話である。

映画『ベンハー』(1959年)にも、癩病に罹(かか)った人々が追い込まれる谷/洞窟が出て来る。キリストが処刑され、キリストの血と、その時に降った雨が病を流すという奇跡で映画は終わる。多分にこの時、谷には他の「正体不明の恐ろしい病」、性病患者や精神疾患の患者がいたことは間違いない(フーコー『狂気の誕生』など)。
そして、あと補足したいことは、ふたつの『砂の器』(松本清張原作)である。ケチつけから入るが、2004年フジテレビのドラマを、私は相当入れ込んで見た。しかし、最終回は見なかった。事件は、ダム建設反対で村八分にあった人間が、その過去を知られたくないということを動機としている。待ってくれ、東京まで逃げれば村は追いかけて来ないじゃないのか。自分の過去を知る人間を殺す動機としては、はなはだ貧弱だ。
さて、ハンセン病が「伝染病」として予防法が施行されるのは1953年。これによって患者の徹底管理/隔離をはかる。この予防法が廃止されるのは、1996年。たかだか20年前だ。映画制作の時期、癩病に関する世間の認識は「正体不明の恐ろしい病」だったはずだ。映画の上映は1962年なのである。制作にあたって、松竹と制作側(監督・野村芳太郎)は、激しく対立する。制作費は監督と松竹が折半(せっぱん)という結末まである。そしてさらに、この映画上映を全国の癩病患者(全癩協)が反対する。「差別を助長する」からだ。そして、全癩協との長い話し合いで、ようやくこぎつけた上映だ。
家を、村を追い出された親子。全国どこを放浪しても、石を投げつけられる。そんなハンセン病の過去を持つピアニストを、ある日子どもの頃世話になったお巡りさんが訪ねる。彼はその夜、お巡りさんを殺すのだ。
☆☆
いろんな人に『あん』を勧めてます。皆さんもぜひどうぞ。上映は、全国で77館とはずいぶんな数字(少ないという意味ですよ)とも思いますが、また一度、
「私たちが向かうのは『世間』や『世界』ではない」
と、思うことにします。
☆☆
『天皇の料理番』好調ですねえ。見てますか。先週ひとつ残念だったのが、篤蔵の頭。髪を伸ばすのもいいけど、明治のコックがあれでいいのかなあ。一気に今風になってましたが、パリなら許されたのでしょうか。かなり残念。
☆☆
珍しく体調崩しました。年取ってからの風邪はこたえますねえ。皆さんも梅雨時の体調、お気をつけて。
~「どら焼いかがですか!」~
1 出会い
ハンセン病を描いた作品は二度目。『砂の器』が初めだ。『あん』もつらい映画なのだろうと思って、映画館への足は少しばかり重かった。しかし違っていた。
カンヌ映画祭の作品(河瀬直美監督)である。ホントに映画っていいなと思った。美しかった。心を洗われ、そして力をもらった。

「あたし、50年間あんこを作ってるのよ」
映画が始まってすぐの、この徳江(樹木希林)の言葉で考えた。徳江の手は病(やまい)で侵されて、大きく形を変えている。十代で故郷を追われた徳江は、施設入所の時、母が徹夜して作ってくれたブラウスもみんな、洗いざらい処分される。患者は人と接触してはいけない。外部の人間は、施設/患者に近づいてはいけない。ハンセン病は、骨をも溶かす「忌(いま)わしい」病気だった。
「伝染性の強い不治の病」という世の中で、徳江が小豆のあんこを作ろうと思ったきっかけはなんだったろう。これは食べ物だ。豆にも水にも自分の手を浸(つ)けるのだ。毎日豆と話をして腕をあげたのだろうか。
「こんなに美味しい」
そう思い、施設の仲間とそう言い合い食べたのだろうか。身体に対する不安も、自分自身あったに違いない。それが日々の生活の中で少しずつ払拭(ふっしょく)されたのだろうか。
時を追うに従い、菌や伝染性の極めて弱いことが発見/解明される。治療法が確立される。それらの出来事に伴い、外に出たい/出られる思いが作られたのだろうか。長い年月と苦しみの向こうから、徳江が千太郎の店にやってくる。
「あたしが作ったあんこ、食べてみて」
と、徳江が差し出すあんこを、プレハブ小屋で店長をする千太郎(永瀬正敏)は、いったんは捨てる。しかし、
「つぶあんか」
と言わせることを忘れなかった。つぶあんだったから捨てた。徳江に対して「不浄(ふじょう)のもの」という見方を、一度も千太郎はしなかった。そんな人間の深い部分を徳江が見逃さなかったから、千太郎に声をかけた。あとでそれが分かる。
2 「世間」というあり方
徳江が小豆と会話しながら手塩にかけたあんこは、やがて小さな店の前に行列を作る。


しかし、客は波を引くように途絶える。徳江にはみんな分かる。でも、大量に売れ残ったどら焼を前に、そして素通りする人々を前に、招き猫を磨く。
このあと物語は、静かに進む。私たちははある期待をして観続けた。それはある部分で受けいれられ、ある部分では裏切られる。
中学生のワカナ(内田伽羅:樹木希林の孫)に誘われ、千太郎は施設を訪れる。徳江は静かに二人を迎える。はしゃぐでもない、かといって嫌な顔をするのでもない徳江の静かな顔から、様々なメッセージが流れて来る。千太郎は、そのメッセージをどう受け取ったらいいのか、身の置き場所に困るような躊躇(ちゅうちょ)をする。

幸せでした、という最後の徳江の手紙には、
「私たちはこの世を見るために、聞くために、生まれてきた」
としたためられていた。これは世間の非情を責める言葉ではない。千太郎と出会って、世の中を見ることが出来た感謝の言葉だ。映画は、誰が心ない噂をばらまいて客を奪ったのかという展開をしない。徳江は誰も責めない。千太郎は自分を責めた。
私は強烈に教えられた気がする。
○私たちが向かうのは「世間」や「世界」とは別な処(ところ)でいい
○私たちが向かっているのは「世間」や「世界」ではない
と教えられた気がしている。
私は「風評被害」なる言葉を、いきなり思い出した。自分に降りかかった災難を、他の誰かから「克服しなさい」「そうしないと復興しない」と言われる時の言葉だ。そして、せっかく丹精込めて作った米や野菜を、邪険にされる時に訴える言葉だ。徳江はそういう場所にはいなかった。

徳江の好きな桜が満開の公園で、千太郎がどら焼を売るラスト。客の来ない屋台で、やがて意を決したように、
「どら焼いかがですか!」
と声を上げる千太郎の頭は、もうボサボサの長い髪ではなかった。
土曜日の盛況だったのだろう。思いの外(ほか)、若い人が多かった。その満席の観客から、これも静かな拍手が起きたのだった。
3 補足
「癩病(らいびょう)」の意味を、ハンセン病と限定して、揉(も)め事を避けている辞書も多い。しかし、聖書や日本書紀の昔から登場する「癩病」が、固有の疫病(えきびょう)として分類されていたはずがない。「正体不明の恐ろしい病」程度の意味づけで始まっているというのが正確なところだ。ちなみに白川静の『字訓』によると、癩病の作りの「頼」の部分は、神から天与されたものを意味するので、癩病は神聖病だったという。中国は孔子の時代の話である。

映画『ベンハー』(1959年)にも、癩病に罹(かか)った人々が追い込まれる谷/洞窟が出て来る。キリストが処刑され、キリストの血と、その時に降った雨が病を流すという奇跡で映画は終わる。多分にこの時、谷には他の「正体不明の恐ろしい病」、性病患者や精神疾患の患者がいたことは間違いない(フーコー『狂気の誕生』など)。
そして、あと補足したいことは、ふたつの『砂の器』(松本清張原作)である。ケチつけから入るが、2004年フジテレビのドラマを、私は相当入れ込んで見た。しかし、最終回は見なかった。事件は、ダム建設反対で村八分にあった人間が、その過去を知られたくないということを動機としている。待ってくれ、東京まで逃げれば村は追いかけて来ないじゃないのか。自分の過去を知る人間を殺す動機としては、はなはだ貧弱だ。
さて、ハンセン病が「伝染病」として予防法が施行されるのは1953年。これによって患者の徹底管理/隔離をはかる。この予防法が廃止されるのは、1996年。たかだか20年前だ。映画制作の時期、癩病に関する世間の認識は「正体不明の恐ろしい病」だったはずだ。映画の上映は1962年なのである。制作にあたって、松竹と制作側(監督・野村芳太郎)は、激しく対立する。制作費は監督と松竹が折半(せっぱん)という結末まである。そしてさらに、この映画上映を全国の癩病患者(全癩協)が反対する。「差別を助長する」からだ。そして、全癩協との長い話し合いで、ようやくこぎつけた上映だ。
家を、村を追い出された親子。全国どこを放浪しても、石を投げつけられる。そんなハンセン病の過去を持つピアニストを、ある日子どもの頃世話になったお巡りさんが訪ねる。彼はその夜、お巡りさんを殺すのだ。
☆☆
いろんな人に『あん』を勧めてます。皆さんもぜひどうぞ。上映は、全国で77館とはずいぶんな数字(少ないという意味ですよ)とも思いますが、また一度、
「私たちが向かうのは『世間』や『世界』ではない」
と、思うことにします。
☆☆
『天皇の料理番』好調ですねえ。見てますか。先週ひとつ残念だったのが、篤蔵の頭。髪を伸ばすのもいいけど、明治のコックがあれでいいのかなあ。一気に今風になってましたが、パリなら許されたのでしょうか。かなり残念。
☆☆
珍しく体調崩しました。年取ってからの風邪はこたえますねえ。皆さんも梅雨時の体調、お気をつけて。