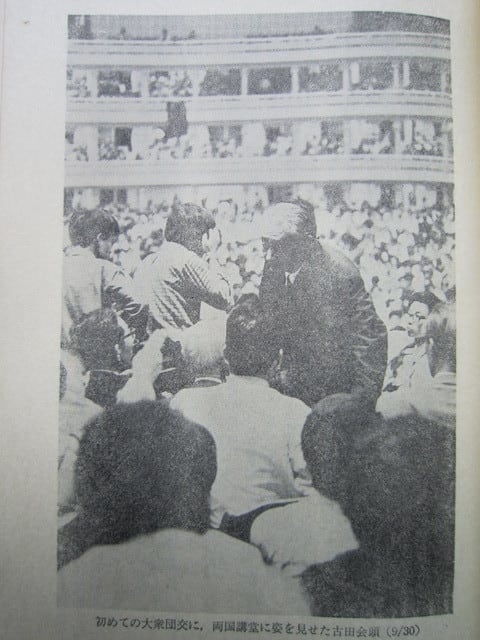内原義勇軍訓練所
~満洲/戦後を考えるために~
☆初めに☆
今年の読書特集で、満蒙開拓義勇軍の本(『満蒙開拓青少年義勇軍の旅路』)を紹介しました。
国内で唯一の義勇軍訓練所は、茨城県東茨城郡・内原(現・水戸市内原町)にありました。全国から志願した少年たちが、ここで二カ月の訓練を受けて、その後満洲に渡ったのです。
☆☆
相も変わらず良く調べもせずに出むく私です。訓練所跡の「義勇軍資料館」は館内工事中、12月上旬まで休館でした。
館内には入れませんでしたが、今回は外観と概要をお知らせします。次の時は、館内まで見学してレポートします。
1 日輪兵舎
復元された日輪兵舎は、内原図書館・郷土資料館の庭一角に立っている。単純で工期が短く、訓練生10人が5日で建てたという。多くの人員を収容することが可能な、モンゴルのパオを模した「日輪」構造。

直径11m、30坪の兵舎には60人が収容可能だったという。ここも閉められているので、外からの写真です。

大鍋や農機具も見えます。

こちらが記念館。

2 訓練所での生活
今回は義勇軍募集のポイントと、少年たちの生活がどのようだったのか、ふたつに絞り込もうと思う。
しかし、年間3万人の募集に対し、1938年の初年度は2万5千人を下回り、翌年の1939年は1万人さえ及ばなかった。この数字の低さは、1937年の日中戦争本格的開始が原因らしい。国内の軍需産業が活況(かっきょう)を呈し、「満洲に渡ることもない」状況が生まれたのだ。仕方なく募集は県ごとの割り当てがされる。教育会(現教育委員会)や教師はノルマ達成に奔走(ほんそう)する。
そして割り当ての数が、なぜか山形・宮城・長野や新潟に多かった。みんな雪の多い寒冷地だった。計画書には、
応募した子どもたち(訓練生)には、厳しい軍隊式の生活と粗末な食事が待っていた。離れた家族が現金や食べ物を送ることは禁じられ、手紙は検閲された。しかし訓練生はおとなしく従わなかった。訓練所外での機会を利用して検閲なしの手紙を出し、訓練先で現金を受け取り、あるものは訓練先で脱走した。
義勇軍の記録として残される多くの手記が、内原訓練所の日々を懐かしくつづるものが多い。教官にめぐまれた訓練生もあったというので、全部が嘘ではないだろう。そういうケースもあったということだ。しかし、それらが当時の「検閲」ずみの文章であることを、私たちは踏まえた方がよさそうである。夜、8時30分の消灯ラッパに、涙をこらえて床に就(つ)く子どもたちだった。
☆笠間稲荷☆
内原の目と鼻の先に、笠間があります。菊祭り真っ盛りの笠間稲荷に寄りました。境内です。

反対側からのショット。

これは近くの小学生たちの作品なんです。見事ですね。

開店前の饅頭屋さんで、おじさんがひとり、慌(あわ)ただしくあんこを仕込んでました。まかないさんも誰もまだ来てない店でした。いいおじさんで、店内のお猪口(ちょこ)に、
「これ、値段がついてないんですが………」
私が尋ねると、忙しいさなか出てきてくれるんです。これはねと、下に敷いてあった袋を取り出し、
「酒好きのダンナがお気に入りの猪口をこの袋に入れておくのさ」
「これを持って店に行くってことらしいよ」
袋には2500円のシール。ちっとたけえな、おじさんはそう言って笑い、おいしいよ、と出来立て饅頭を差し出すのです。
こういうお店ではつい買い物をしてしまいますねえ。

通り沿いは地元の造り酒屋『松緑』です。
~満洲/戦後を考えるために~
☆初めに☆
今年の読書特集で、満蒙開拓義勇軍の本(『満蒙開拓青少年義勇軍の旅路』)を紹介しました。
国内で唯一の義勇軍訓練所は、茨城県東茨城郡・内原(現・水戸市内原町)にありました。全国から志願した少年たちが、ここで二カ月の訓練を受けて、その後満洲に渡ったのです。
☆☆
相も変わらず良く調べもせずに出むく私です。訓練所跡の「義勇軍資料館」は館内工事中、12月上旬まで休館でした。
館内には入れませんでしたが、今回は外観と概要をお知らせします。次の時は、館内まで見学してレポートします。
1 日輪兵舎
復元された日輪兵舎は、内原図書館・郷土資料館の庭一角に立っている。単純で工期が短く、訓練生10人が5日で建てたという。多くの人員を収容することが可能な、モンゴルのパオを模した「日輪」構造。

直径11m、30坪の兵舎には60人が収容可能だったという。ここも閉められているので、外からの写真です。

大鍋や農機具も見えます。

こちらが記念館。

2 訓練所での生活
今回は義勇軍募集のポイントと、少年たちの生活がどのようだったのか、ふたつに絞り込もうと思う。
「かぞえ16歳より19歳までの身体剛健意思強固なるもの」
「内地訓練二カ月、現地訓練三カ年を終了したあかつきには………独立農業者たらしむべく国家はこれを助成する」
は、募集要項。そして、満洲開拓本部(略称)の年報によれば、実際に応募したのは、多くが農家の次男以下で、高等小学校を卒業したばかりの十五,六歳の少年たちだった。零細(れいさい)農家にとって夢のような話だった。「内地訓練二カ月、現地訓練三カ年を終了したあかつきには………独立農業者たらしむべく国家はこれを助成する」
しかし、年間3万人の募集に対し、1938年の初年度は2万5千人を下回り、翌年の1939年は1万人さえ及ばなかった。この数字の低さは、1937年の日中戦争本格的開始が原因らしい。国内の軍需産業が活況(かっきょう)を呈し、「満洲に渡ることもない」状況が生まれたのだ。仕方なく募集は県ごとの割り当てがされる。教育会(現教育委員会)や教師はノルマ達成に奔走(ほんそう)する。
そして割り当ての数が、なぜか山形・宮城・長野や新潟に多かった。みんな雪の多い寒冷地だった。計画書には、
「満洲……というのは寒いところでありますから、寒い経験のない人間が行っては冬が越されない」
とある。しかしこれを読めば、集団就職で上京する中卒の子どもたちを思った人たちは多いだろう。応募した子どもたち(訓練生)には、厳しい軍隊式の生活と粗末な食事が待っていた。離れた家族が現金や食べ物を送ることは禁じられ、手紙は検閲された。しかし訓練生はおとなしく従わなかった。訓練所外での機会を利用して検閲なしの手紙を出し、訓練先で現金を受け取り、あるものは訓練先で脱走した。
義勇軍の記録として残される多くの手記が、内原訓練所の日々を懐かしくつづるものが多い。教官にめぐまれた訓練生もあったというので、全部が嘘ではないだろう。そういうケースもあったということだ。しかし、それらが当時の「検閲」ずみの文章であることを、私たちは踏まえた方がよさそうである。夜、8時30分の消灯ラッパに、涙をこらえて床に就(つ)く子どもたちだった。
☆笠間稲荷☆
内原の目と鼻の先に、笠間があります。菊祭り真っ盛りの笠間稲荷に寄りました。境内です。

反対側からのショット。

これは近くの小学生たちの作品なんです。見事ですね。

開店前の饅頭屋さんで、おじさんがひとり、慌(あわ)ただしくあんこを仕込んでました。まかないさんも誰もまだ来てない店でした。いいおじさんで、店内のお猪口(ちょこ)に、
「これ、値段がついてないんですが………」
私が尋ねると、忙しいさなか出てきてくれるんです。これはねと、下に敷いてあった袋を取り出し、
「酒好きのダンナがお気に入りの猪口をこの袋に入れておくのさ」
「これを持って店に行くってことらしいよ」
袋には2500円のシール。ちっとたけえな、おじさんはそう言って笑い、おいしいよ、と出来立て饅頭を差し出すのです。
こういうお店ではつい買い物をしてしまいますねえ。

通り沿いは地元の造り酒屋『松緑』です。