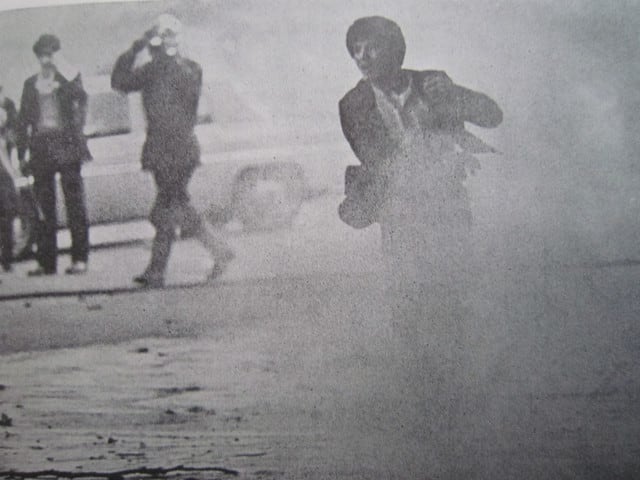上野/浅草
~「見てはいけません」~
☆初めに☆
新年号ですが、いつも通りに年を逆上り大晦日に関する記事となります。そしてこれも恒例ですが、上野/浅草界隈(かいわい)のレポートとなります。
☆アメ横☆
大晦日のアメ横は早めに閉まる。逆に言うとその頃は、いつもの安値にさらなる拍車がかかり、中トロのさくが1000円などという状態だ。その熱気と乗りは尋常ではない。

一緒に歩いていた若い仲間が、どうしてアメ横というのか、と尋ねて来る。進駐軍の品物を横流しする戦後の闇市として、とりわけ多くの中国からの引揚者(ひきあげしゃ)や朝鮮の人たちのてこ入れがあって賑(にぎ)わったアメ横(アメや砂糖の説もある)。こんなことも知らずにいるのかと驚くと同時に、今はトルコや中東の人たちが仕切る店も目立つようになったこのエリアの、相変わらずと言えるいかがわしい相貌(そうぼう)に、私は考えてしまった。
アメ横入口にあったレストランが改装されて再開した。名前は知らないが、昔からの「聚落台(じゅらくだい)」なのだろうか。

終戦から15年後に開店し、2008年に閉店した「聚落台」。
今のそれはきらびやかに変身したものの、私には影のようにあちこちにうごめく人たちの姿がはっきり見える。
☆傷痍(しょうい)軍人☆
東京は昔、遠い場所だった。茨城の片田舎から、今なら一時間もあれば着くことが出来る上野は、当時は着くまでに優に二時間を越えた。列車の蒸気機関車は颯爽(さっそう)と煙を吐き、ゆっくりと進んだ。そして発車の本数も頼りなく、私たちはホームで長い時間を過ごしたのだ。
上野に到着すると、そこには汽車に代わりチョコレート色の機関車が、モーターの音を響かせている。それは東京という「体験」だった。
幼年時、一年に一度も行かなかった東京だが、そこで必ず恐ろしいものを見た。電車の中に、白い布をまとった人たちがやって来るのだ。みんな身体のどこかが無かった。ある人はアコーディオンを弾き、片手のない人はハーモニカを吹き、両足の無い人は、床は手を頼りに「慰問(いもん)箱」を抱えていた。お揃いの軍帽を被り、全員サングラスをしていた。ある人は無くなった片手の代わりに、フック船長のようなカギ状の金属をつけているのも恐怖をあおった。しかし、目が離せなかった。気がつくと、私の顔は母の懐(ふところ)の中だった。「見てはいけません」。
上野駅を降りても同じだった。西郷さんの銅像に上がる階段で、同じ出で立ちの人たちが、やはりひざまずき軍歌を歌っていた。一体あの人たちは何をしたのだろう、そして何をしているのだろう、私はきっとそう思っていた。そしてそこに戦争の姿を見ていた。
「見てはいけません」と母が言ったわけではない。しかし、どうすることも出来ないことをどうにかしろと言われても困ります、そういう母の気持ちがはっきり聞こえた気がする。この始末はまだついていない。戦争とはそういう始末のつかないものだ。
☆上野駅☆
この戦争の影のあとにやって来たのが「集団就職」だ。高度成長が陰りを帯びる1975年まで、集団就職列車は東北や北陸から「金の卵」を運んだ。15歳の子どもたちが数々の手作り荷物を持って、ホームで泣く家族をあとにした。
時代は違うが、啄木が「ふるさとの訛(なま)り」を聞きたくて、本郷のアパートから向かったのも上野駅である。
上野駅広小路口に、流行歌『ああ上野駅』の歌碑が建っている。たまにだが、私より少し年かさのいった人たちが、碑のそばで談笑しているのを見る。
そんなこんなの上野界隈なのだ。うごめいている、あるいはじっとたたずむおびただしい影があるのは当たり前だ。若い人たちは池袋も上野もそんなに変わらないというのだが………私は上野の影とまた一度向き合う。
☆浅草☆
さて、浅草です。少し時間が遅めだったせいか、雷門前は若干(じゃっかん)人出が少なめだったかな。

これも変わらず、仲見世で揚げ饅頭と甘酒を買って味わいます。

もちろん、尾張屋の行列につきます。

注文にもたもたしていても、この店は「ゆっくりでいいんですよ」と、言ってくれます。こんなに混雑してるのに。

そして、そばみそを頼もうとすると、「いやそれは『八海山』についてますから大丈夫です」と。この店はやっぱり気分がいい。

いい気分、ほろ酔い気分で店を出ます。
来年がいい年でありますように。
☆後記☆
新しい年となりました。今年も頑張ります。どうぞ、このブログを今年もよろしくお願いします。
☆ ☆
正月のテレビってどっしようもないんですが、BS1の「ホンダはどうしてF1に勝利できたか」(だったかな)は、感動しました。新入り社員の時にセナと一緒に戦った人たちが、今トップで指揮してるんですねえ。ブラジルへの思いがひと通りではないのがまた良かった。
今年はやってほしい。F1中継!
~「見てはいけません」~
☆初めに☆
新年号ですが、いつも通りに年を逆上り大晦日に関する記事となります。そしてこれも恒例ですが、上野/浅草界隈(かいわい)のレポートとなります。
☆アメ横☆
大晦日のアメ横は早めに閉まる。逆に言うとその頃は、いつもの安値にさらなる拍車がかかり、中トロのさくが1000円などという状態だ。その熱気と乗りは尋常ではない。

一緒に歩いていた若い仲間が、どうしてアメ横というのか、と尋ねて来る。進駐軍の品物を横流しする戦後の闇市として、とりわけ多くの中国からの引揚者(ひきあげしゃ)や朝鮮の人たちのてこ入れがあって賑(にぎ)わったアメ横(アメや砂糖の説もある)。こんなことも知らずにいるのかと驚くと同時に、今はトルコや中東の人たちが仕切る店も目立つようになったこのエリアの、相変わらずと言えるいかがわしい相貌(そうぼう)に、私は考えてしまった。
アメ横入口にあったレストランが改装されて再開した。名前は知らないが、昔からの「聚落台(じゅらくだい)」なのだろうか。

終戦から15年後に開店し、2008年に閉店した「聚落台」。
今のそれはきらびやかに変身したものの、私には影のようにあちこちにうごめく人たちの姿がはっきり見える。
☆傷痍(しょうい)軍人☆
東京は昔、遠い場所だった。茨城の片田舎から、今なら一時間もあれば着くことが出来る上野は、当時は着くまでに優に二時間を越えた。列車の蒸気機関車は颯爽(さっそう)と煙を吐き、ゆっくりと進んだ。そして発車の本数も頼りなく、私たちはホームで長い時間を過ごしたのだ。
上野に到着すると、そこには汽車に代わりチョコレート色の機関車が、モーターの音を響かせている。それは東京という「体験」だった。
幼年時、一年に一度も行かなかった東京だが、そこで必ず恐ろしいものを見た。電車の中に、白い布をまとった人たちがやって来るのだ。みんな身体のどこかが無かった。ある人はアコーディオンを弾き、片手のない人はハーモニカを吹き、両足の無い人は、床は手を頼りに「慰問(いもん)箱」を抱えていた。お揃いの軍帽を被り、全員サングラスをしていた。ある人は無くなった片手の代わりに、フック船長のようなカギ状の金属をつけているのも恐怖をあおった。しかし、目が離せなかった。気がつくと、私の顔は母の懐(ふところ)の中だった。「見てはいけません」。
上野駅を降りても同じだった。西郷さんの銅像に上がる階段で、同じ出で立ちの人たちが、やはりひざまずき軍歌を歌っていた。一体あの人たちは何をしたのだろう、そして何をしているのだろう、私はきっとそう思っていた。そしてそこに戦争の姿を見ていた。
「見てはいけません」と母が言ったわけではない。しかし、どうすることも出来ないことをどうにかしろと言われても困ります、そういう母の気持ちがはっきり聞こえた気がする。この始末はまだついていない。戦争とはそういう始末のつかないものだ。
☆上野駅☆
この戦争の影のあとにやって来たのが「集団就職」だ。高度成長が陰りを帯びる1975年まで、集団就職列車は東北や北陸から「金の卵」を運んだ。15歳の子どもたちが数々の手作り荷物を持って、ホームで泣く家族をあとにした。
時代は違うが、啄木が「ふるさとの訛(なま)り」を聞きたくて、本郷のアパートから向かったのも上野駅である。
上野駅広小路口に、流行歌『ああ上野駅』の歌碑が建っている。たまにだが、私より少し年かさのいった人たちが、碑のそばで談笑しているのを見る。
そんなこんなの上野界隈なのだ。うごめいている、あるいはじっとたたずむおびただしい影があるのは当たり前だ。若い人たちは池袋も上野もそんなに変わらないというのだが………私は上野の影とまた一度向き合う。
☆浅草☆
さて、浅草です。少し時間が遅めだったせいか、雷門前は若干(じゃっかん)人出が少なめだったかな。

これも変わらず、仲見世で揚げ饅頭と甘酒を買って味わいます。

もちろん、尾張屋の行列につきます。

注文にもたもたしていても、この店は「ゆっくりでいいんですよ」と、言ってくれます。こんなに混雑してるのに。

そして、そばみそを頼もうとすると、「いやそれは『八海山』についてますから大丈夫です」と。この店はやっぱり気分がいい。

いい気分、ほろ酔い気分で店を出ます。
来年がいい年でありますように。
☆後記☆
新しい年となりました。今年も頑張ります。どうぞ、このブログを今年もよろしくお願いします。
☆ ☆
正月のテレビってどっしようもないんですが、BS1の「ホンダはどうしてF1に勝利できたか」(だったかな)は、感動しました。新入り社員の時にセナと一緒に戦った人たちが、今トップで指揮してるんですねえ。ブラジルへの思いがひと通りではないのがまた良かった。
今年はやってほしい。F1中継!