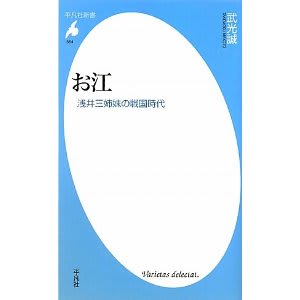
浅井長政に嫁いだ織田信長の異母妹、お市の方には3人の娘がいた。茶々(淀殿)、お初、お江。彼女たちはそれぞれ、数奇な人生をたどる。
茶々は秀吉の側室となり、秀頼を生んだ。お初は京極高次の妻に、お江は離婚を重ねて徳川秀忠の妻に。
本書は、この3人の女性を基軸に戦国時代の推移を天下取りに向けた信長の野望から大坂夏の陣で豊臣が滅びるまでを解説している。薄い新書スタイルだが中身は濃い。
切り口が斬新(と思える)。大坂夏の陣を、親キリシタン大名群と反キリシタン大名群との決戦とみたり、それを淀殿とお江との姉妹の争いとみたり。
お初はここで姉の淀殿につくような動きをみせるが、お江と内通し、徳川方を勝利に導くための工作を行っていた。
女性の能力を評価していることも特徴的である。男性と女性との役割をしっかり心得、対等の関係にあったととらえている。戦国時代は戦いに明け暮れた「男の時代」のようにみえるが、動乱の歴史のなかのかなりの部分が女性によってうごかされていた、とまで言い切っている。阿茶局、北政所しかり、お江、淀殿しかり。
著者の戦国時代を見る目は、わたしにはあたらしかった。織田信長の国造りの構想、兵法の斬新さ。秀吉はどちらかというと「いけいけ」タイプで、民衆の統治を構想する力が弱かった。家康は詭計にたけ、情報戦略の意義を把握し、民衆統治への配慮も行き届いていた、など。
さらに歴史に「もし、ならば」は禁句だが、人間のある主観的判断がその後の運命の岐路となったことも事実である。関ヶ原の合戦では真田昌幸が秀忠軍を粉砕し、その時点では西軍が優勢であった。石田三成のまずい指揮が西軍の大敗を結果させた。夏の陣で、淀殿があれほど決戦に執着しなければ、豊臣家が消滅することはなかった。歴史の無常を思い知らされる。
「序章:関ヶ原以降、戦さは合戦から謀略戦に変貌」「第一章:天下統一とお市の姫たち」「第二章:お市の姫たちの生き方」「第三章:関ヶ原合戦」「第四章:豊臣家復興の謀略に動く淀殿」「第五章:大阪冬の陣」「第六章:大阪夏の陣」「終章:戦国の終わりとお市の姫たち」
最新の画像[もっと見る]




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます