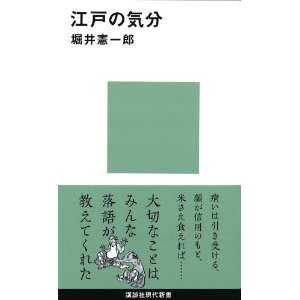
落語を通して、江戸の気分をリアルに想像しようというのが、本書の狙いのようである。著者によれば、「落語は、口承芸能なので、江戸のころの空気がところどころに残っている」ので、「その当時の生活の空気が感じられるのだ。そこをとっかかりに江戸を暮らしてみる気分になってみる、という試みである」というのだ(「まえがき」p.3)。
それで、どういう江戸の気分がかもし出されてくるのかと思って、本文に入っていくと、著者は、「まえがき」で宣言したとおり、いろいろな落語を引き合いに出して、病にかかった場合、神信心にすがる場合、武士が刀をぬく場合、火事の場合、花見をする場合、葬式の場合、カネを使う場合など、江戸の人たちの生活の臭いかぎとろうとしている。よく落語を聞いていないとこういう本はかけない。索引には何と116の落語が並んでいる。
著者は1959年生まれのコラムニスト。落語関係の著書が多い。本書の目次は以下のとおり。
「第1章:病と戦う馬鹿はいない」
「第2章:神様はすぐそこにいる」
「第3章:キツネタヌキにだまされる」
「第4章:武士は戒厳令下の軍人だ」
「第5章:火事も娯楽の江戸の街」
「第6章:火消は破壊する」
「第7章:得江戸の花見は馬鹿の祭典だ」
「第8章:蚊帳に守られる夏」
「第9章:棺桶は急ぎ家へ運び込まれる」
「第10章:死と隣り合わせの貧乏」
「第11章:無人というお楽しみ会」
「第12章:金がなくとも生きていける」
「第13章:米だけ食べて生きる」
「附章:京と大坂と江戸と」
最新の画像[もっと見る]




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます