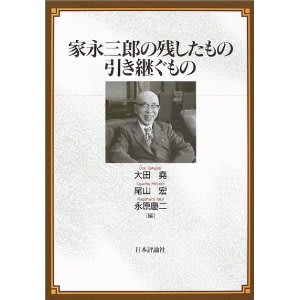
教科書裁判闘争で偉大な役割を果たした家永三郎先生の人と業績を回顧し、さらにその運動を継承した実践を展望した好著。 編集者は太田堯さん、尾山宏さん、永原慶二さんだが、編者を含め40人が原稿を寄せている。
通読して、家永三郎先生の精神的遺産の巨大さ、教科書裁判の歴史的意義の深さ、その後の運動の広がりの多様さと広範さに驚嘆する。
家永教科書裁判は1965年、家永三郎(1913-2002)が一学者、一国民として現行教科書検定制度が違憲違法であるとして、国(文部省)を相手取って起こした裁判である。以降、第二次訴訟提訴(1967年)、第三次訴訟提訴(1984年)を経て、1997年8月29日の最高裁第三小法廷判決をもって終結した。
三度の提訴を通じて、地裁から上下級10カ所の担当裁判所から10件の判決を出させた。中身としては検定制度の適用違憲をいうもの(杉本判決)、検定制度の恣意的な運用を批判するもの(畔上判決)、検定制度は合憲とするが、個々の検定処分の行き過ぎをとがめるもの4件などがある。
この裁判が歴史的に大きな意義をもったのは、検定制度の合憲性を問うにとどまらなかったこと、換言すればそれを教育をめぐる闘い、憲法問題にまで高めたことにあった。
全体は2部3グループ構成であ。第Ⅰ部「家永三郎先生の精神と学問の今日的意義」で主に理論的な側面を記録した文章が、第Ⅱ部「自由・平和・民主主義を求めて-家永三郎先生の遺志と活動の継承」で実践的な側面からの文章が並んでいる。全体がとても重視していてどの文章にも感銘を受けたが、家永史学について論じた「家永史学を支えるもの(江村栄一)」、家永先生が勤務していた東京教育大学での闘いについて書かれた「東京教育大学闘争における家永先生(大江志乃夫)」、家永先生の憲法論の意義をあつかった「家永憲法論の業績と特質(小林直樹)」、杉本判決の積極的な意味を浮き彫りにした「家永先生の『高尚な生涯』と教科書裁判の意義(太田堯)」「家永教科書裁判と教育学(堀尾輝久)」「家永教科書裁判の今日的意義(尾山宏)」から多くのことを学んだ。
国家と教育の関係を問い直し、精神の自由を前提する子どもの学習権[文化的生存権]とそれを中核とした国民の教育権と教育の自由論を展開し、国家は教育内容や教科書記述に立ち入ってはならないことを明示的に述べた杉本判決の意義は、教育にたずさわるものとして忘れてはならないものである。
他に2・3の論稿には検定内容の具体的やりとりが紹介されているが、検定内容のあまりのお粗末さにあきれてしまった。教育の反動化は強まっている。教育現場の一部にみられる荒廃には目に余るものがある。両者は無関係でない。家永先生が残された遺産の継承しそれを深化させることは、わたしたち国民一人ひとりの課題である。
最新の画像[もっと見る]




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます