薪ストーブ暮らしが好きでブログ書いてます/燃焼のこと、薪作りやメンテナンスのこと、そんな写真と駄文で毎日更新!
薪ストーブ|薪焚亭
雨ざらし

良い薪を作るには、雨ざらした方が良いのか、いやいや、そうではなくて、雨ざらししない方がいいのかってことは、よく見かける話題なんだけれども、実際のところどっちがベストなのか、薪作りを始めて10年近く、いまだに自分も確信はありません。
雨ざらしの期間についても、いろんな意見があるしね。
結局、自分がたどり着いたベストはビニールハウスだったんですが、実はこれも、少し雨ざらししてから保管するのと、割ったら直ぐに保管するのとではまた違うような気がしないでもないし、とまぁ終始こんな調子でして、さっぱりワカリマセン(笑)
まぁ要するに乾けばいいんです! と、言ってしまってはお話にならないんで、少し、いや、今日はダラダラと書いてみましょうかね(笑)
数年前に長期雨ざらしってのをやったことがあったんですが、あれは大失敗でした。
割った薪を1年近く雨ざらしたんですがほとんど乾燥しなかった。 て言うか、半分朽ちてしまったことがあります。 もちろん地面に放置ではなくて、少し浮かせて重ねて並べておいたんですがね。 ダメでした。 で、とうぜん見てくれも真っ黒ですね(笑)
この時の反省点としては、屋根が全く無かったってことなんですが、原因はそれだけじゃないような気がします。 先日紹介した ウッドバック は九州の薪屋さんです。 そして自分は福島県郡山市です。 つまり、気候風土がまったく違うと思うんですよ。
春は遅く梅雨が長くて夏は短いし、秋も直ぐに終わって冬が長い。
薪割隊仲間に新潟のパートナーさんがいるんですが、彼のところもまた違った環境でして、日照時間はここよりも少ないはずです。 でも、その代わりにすばらしい? 強風の力を借りられる。 薪の乾燥ってのは日照と風ですからね。
そういう意味ではウッドバックは乾燥にとても良いアイデアだと思います。 ただ問題は使う地域によって雨ざらし期間が違ってくるんじゃないかと言うことです。 郡山でウッドバッグを使うなら、1~2ヶ月がベストかも知れない。 長くても春から秋まで?
このウッドバッグは寸法が丁度良いと思ってて、これより大きかったら風が通らない。
たとえば割った薪を無造作に山盛り積み上げておいたら1ヶ月経っても表面の薪しか乾かず、中身はほとんど割った時のまんま、下手すりゃカビだらけです。

薪の乾燥・保管については、最終的にビニールハウスに行き着いた自分なんだけれども、雨ざらしを否定しない理由は3つあって、一つは、これは主観的なことだけど、雨があたることで樹皮から染み出た樹液が切り口に流れて、そして太陽に焼かれると、キレイな茶褐色になって薪として美しくなること。
二つ目は、それによって虫がつきにくくなること。 三つ目は、何となくではあるけれども、やはり乾燥が少し早くなるように感じること。 この三つ目の理由として自分が想像するのは、おそらく浸透圧の影響なんじゃないかと思うんですよね。
導管の水分は直ぐに乾くけど、逆に直ぐにまた吸い込みもします。 これは高温多湿に適した日本家屋、木造住宅の優れた点でもある訳です。 しかし、細胞レベルの水分はというと、これはなかなか抜けてくれない。
木の細胞の内側と外側、含んでる同じ水でも内側のそれは樹液で何らかの成分を含んでると思うので、外側の雨水との間で浸透圧が生まれてるんじゃないかなと?
雨を吸い込んでは吐き出し、それが繰り返されてやがて細胞壁が破壊される? みたいな。 まぁ想像でしかないんですが、間違ってたらごめんなさいね(笑)
ただ、もしそう言うことなら、せっかく細胞内に水を溜め込んで時間をかけて樹脂成分に変化させた木の中心部分から、それらも抜けてしまうのか?
なんだか長くなりました。 だらだら書くにも程があるよね。 なので、つづく・・・

まきたきてー発電所 毎日の発電実績





コメント ( 6 ) | Trackback ( )
| « 薪ストーブ以... | 雨ざらしはほ... » |
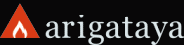
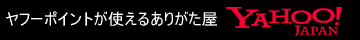








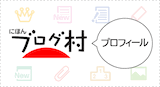








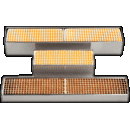

夏はくそ熱く、冬は晴天で空っ風、そして台風や地震の災害も無く
考えてみたら薪を乾燥させるには、いいところなんじゃないのかな?
関東全域に言えることだと思います
いっそのことこちらに薪場を移設させますか(笑)
ところで、年間6トンずつ切って割って補給してくれる?(笑)
災害が少ないのはありがたいよね。
ここいらも少ない方だったんですが、あの震災だ(苦笑)
しかし、水分と共に性根も抜けますね。俗に言うと脂分。従って火力と燃焼時間が格段に減少しますネ。
多少ジュウジュウ言う方が火力もあり燃焼時間も持ちますね。(生薪はダメですよ)やはり、雨に当てず乾燥したマキが最上級品ですね。キノコはえてたら完全に性根ぬけてスカスカですね。
気に障る方いたらごめんなさいね。
同じかどうかわかりませんが建物の構造材を乾燥する方法の一つに水中乾燥と言うのがあります。
丸太ごと海などに浮かべておいて乾燥させる方法です。
そうする事によって海水と木材内部の水分が混ざり合い乾く時に内部の結合水まで乾燥しやすくすると言うものです。
それによって木の割れを軽減したり色艶がよくなる効果があるとか。
地域にもよるかもしれませんが昔からの貯木場が海だったり湖だったりしたのはそう言う狙いもあったのかもしれません。
薪もそれと同じで雨に濡らされていくらか内部の水分まで乾きやすくなるのかもしれませんね。
樹脂成分、自分もそう思います。
で、今日の記事が、それを含めて書いてんですが、
一応結論です。
「雨ざらしはほどほどに」
ただ、文中でも書いてますが、
自分の住む郡山市での経験則でのことです。
丸太のまま水に浸けておく話は聞いたことがあります。
ただ、あれは腐食防止のためだと記憶してたんですが、
陸に上げた時の乾燥速度がかわるんですかね。
東京佃島の確か3年に1回の祭りがあるんですが、
その時に使う御柱は港の海中に沈めてありました。
これは腐食させないためです。
薪の雨ざらしも、その土地土地での言い伝え、
先人の知恵が受け継がれているのでしょうから、
何か理由があるのでしょう。
自分は想像でしかありませんが、
今日の記事で結論です(笑)