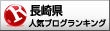日野江城は、標高60~70メートルの丘陵上にある有馬氏の居城でした。
当時は足下まで有明海が入り込み、その海岸にそそり立つ舌状台地上に築かれていました。
築城は初代領主経澄が建保年間(1200年代)に築いたと言われていますが、山城の構造や型式から見ても南北朝時代(1300年代)以降と思われます。
宣教師の訪問記に「有馬氏の見事な館が置かれ、いくつもの部屋と戸(襖)には優雅な絵があって、広間からは海を臨むことが出来た。よく整った庭には池、さらには茶室があって・・・」と書かれ、豪華さが伺われます。

現在再び発掘調査中で、次第にその謎の部分が解明されています。
黄金を塗った棟瓦が発見されたり、城門の階段に仏石をはめ込んだり、石垣の築き方に南蛮の影響があったりと、発見が続いています。
この日野江城も原城と共に、松倉重政によって島原城が築城された時に廃城となり解体されました。
当時は足下まで有明海が入り込み、その海岸にそそり立つ舌状台地上に築かれていました。
築城は初代領主経澄が建保年間(1200年代)に築いたと言われていますが、山城の構造や型式から見ても南北朝時代(1300年代)以降と思われます。
宣教師の訪問記に「有馬氏の見事な館が置かれ、いくつもの部屋と戸(襖)には優雅な絵があって、広間からは海を臨むことが出来た。よく整った庭には池、さらには茶室があって・・・」と書かれ、豪華さが伺われます。

現在再び発掘調査中で、次第にその謎の部分が解明されています。
黄金を塗った棟瓦が発見されたり、城門の階段に仏石をはめ込んだり、石垣の築き方に南蛮の影響があったりと、発見が続いています。
この日野江城も原城と共に、松倉重政によって島原城が築城された時に廃城となり解体されました。