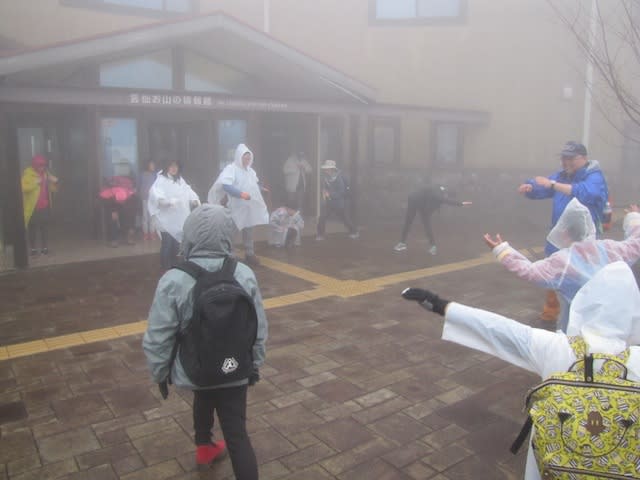21.7.26(月) 天気;晴れ 気温;31℃
4連休が終わった途端、誰も登ってこなくなりました・・・。
24日(土)リユース工作教室「手作りスノードーム」を開催しました。 実はこの企画、2018年に雲仙で一度実施しています。 しかし、企画立案したのは私なのに私は私用により参加できませんでした。 恒例でない限り毎年続けて同じ企画はやらないので、3年ぶりの開催になります。
やっぱり実際にやってみないと分からない事があるもので、今回も盲点があったことに気づきました。 次回(8/28はすでに定員いっぱいです)までには修正します。
さて、子供たちの反応はというと「上々」でした。 接着剤やのりを使うものの割と簡単に作れますし、完成すると綺麗なんですよね。 材料や道具も家や100円ショップで手に入るものばかりなので、長い夏休み是非お家で作ってもらいたいと思います。
4連休が終わった途端、誰も登ってこなくなりました・・・。
24日(土)リユース工作教室「手作りスノードーム」を開催しました。 実はこの企画、2018年に雲仙で一度実施しています。 しかし、企画立案したのは私なのに私は私用により参加できませんでした。 恒例でない限り毎年続けて同じ企画はやらないので、3年ぶりの開催になります。
やっぱり実際にやってみないと分からない事があるもので、今回も盲点があったことに気づきました。 次回(8/28はすでに定員いっぱいです)までには修正します。
さて、子供たちの反応はというと「上々」でした。 接着剤やのりを使うものの割と簡単に作れますし、完成すると綺麗なんですよね。 材料や道具も家や100円ショップで手に入るものばかりなので、長い夏休み是非お家で作ってもらいたいと思います。