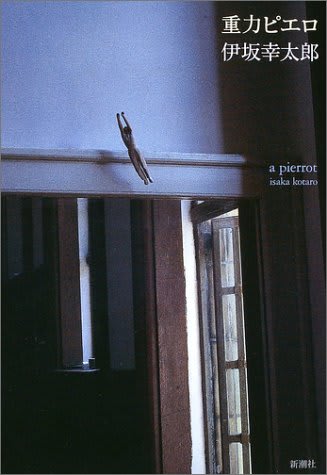 半分しか血のつながりがない「私」と、弟の「春」。春は、私の母親がレイプされたときに身ごもった子である。ある日、出生前診断などの遺伝子技術を扱う私の勤め先が、何者かに放火される。町のあちこちに描かれた落書き消しを専門に請け負っている春は、現場近くに、スプレーによるグラフィティアートが残されていることに気づく。連続放火事件と謎の落書き、レイプという憎むべき犯罪を肯定しなければ自分が存在しない、という矛盾を抱えた春の危うさは、やがて交錯し…。
半分しか血のつながりがない「私」と、弟の「春」。春は、私の母親がレイプされたときに身ごもった子である。ある日、出生前診断などの遺伝子技術を扱う私の勤め先が、何者かに放火される。町のあちこちに描かれた落書き消しを専門に請け負っている春は、現場近くに、スプレーによるグラフィティアートが残されていることに気づく。連続放火事件と謎の落書き、レイプという憎むべき犯罪を肯定しなければ自分が存在しない、という矛盾を抱えた春の危うさは、やがて交錯し…。
前作「ラッシュライフ」と「オーデュボンの祈り」(絶版)をそろえて一気に読み進めるべきだ。登場人物が相互乗り入れを行っていて、特別出演みたいでこれがなかなか楽しい。特に探偵兼泥棒兼カウンセラーである黒澤の再登場はうれしかった。
この作家の特徴は、とにかく大量の警句(ワイズ・クラック)を仕込んでいることで、日本の作家には珍しくいい感じ。例えば、癌に倒れた父親を兄弟が見舞うシーン。
「推理小説を買ってこいだとか、地図を買ってこいだとか、父さんが言うからね。歴史の参考書まで買ってきた」
「そんなの、何に使うんだよ」
「小説に嘘が書いていないか、チェックするんだ」父が笑う。癌のせいでもないだろうが、歯が先細っているように見えた。
「小説を読むのは、でたらめを楽しむためじゃないか」
……このあと、父親は作中でもっとも泣かせるセリフ「(兄弟)二人で遊んできたのか?」をつぶやく。兄弟の物語に弱いわたしは、はやウルウルである。
ただ、ミステリとしてはどうだろう。暗号解読はいかにもとってつけたみたいだし(そのことで兄はあることに気づくのだが)、おまけに肝心の動機が……この動機だからこそ感動できる、それはわかるんだが。「氷点」じゃないんだからさ(笑)。
ミステリとしては不満の残る出来だけれど、家族小説、そして仙台という街の物語としてなら、これは素晴らしく気持ちのいい作品。でたらめを、ぜひ楽しんでほしい。
 「重力ピエロ」や「アヒルと鴨のコインロッカー」などで軽快にとばす伊坂の新作がまさか“政治小説”だったとは。キーワードは「違和感」。ワイドショー化したマスコミ報道やネット情報に踊り、カリスマの匂いのする政治家があっという間に首相にのぼりつめる日本。そのことに違和感を抱いた兄弟はそれぞれに行動を起こす。しかし、究極の“魔王”となるのは……。
「重力ピエロ」や「アヒルと鴨のコインロッカー」などで軽快にとばす伊坂の新作がまさか“政治小説”だったとは。キーワードは「違和感」。ワイドショー化したマスコミ報道やネット情報に踊り、カリスマの匂いのする政治家があっという間に首相にのぼりつめる日本。そのことに違和感を抱いた兄弟はそれぞれに行動を起こす。しかし、究極の“魔王”となるのは……。









 日本で「殺し屋」の物語を成立させるのは、かなり難しい。
日本で「殺し屋」の物語を成立させるのは、かなり難しい。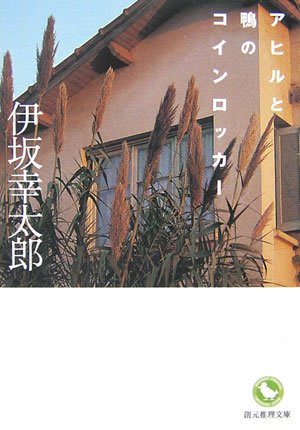 絶好調伊坂幸太郎。相変わらず皮肉な口調と醒めた文体が効きまくっている。ただし、ミステリとしてみれば穴だらけ。メイントリックに途中で気づいてしまう読者も多いだろうし(わたしはP186で気づきました。早いんだか遅いんだか)、そのことで興ざめ、とする偏狭なミステリおたくもいるだろう。わたしにしたって、悲劇を予感させる展開に、“もうひとりの”主人公に向かって「とりあえずお前は早く警察に行け!」と突っ込みながら読んでました。本屋を襲うシーンは、まるで【村上春樹が描く、
絶好調伊坂幸太郎。相変わらず皮肉な口調と醒めた文体が効きまくっている。ただし、ミステリとしてみれば穴だらけ。メイントリックに途中で気づいてしまう読者も多いだろうし(わたしはP186で気づきました。早いんだか遅いんだか)、そのことで興ざめ、とする偏狭なミステリおたくもいるだろう。わたしにしたって、悲劇を予感させる展開に、“もうひとりの”主人公に向かって「とりあえずお前は早く警察に行け!」と突っ込みながら読んでました。本屋を襲うシーンは、まるで【村上春樹が描く、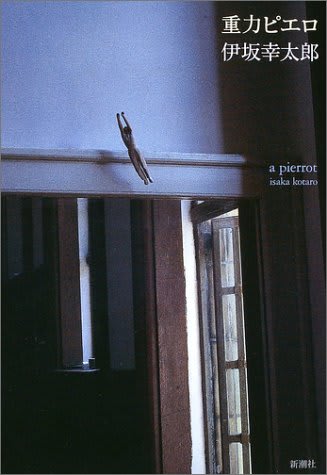 半分しか血のつながりがない「私」と、弟の「春」。春は、私の母親がレイプされたときに身ごもった子である。ある日、出生前診断などの遺伝子技術を扱う私の勤め先が、何者かに放火される。町のあちこちに描かれた落書き消しを専門に請け負っている春は、現場近くに、スプレーによるグラフィティアートが残されていることに気づく。連続放火事件と謎の落書き、レイプという憎むべき犯罪を肯定しなければ自分が存在しない、という矛盾を抱えた春の危うさは、やがて交錯し…。
半分しか血のつながりがない「私」と、弟の「春」。春は、私の母親がレイプされたときに身ごもった子である。ある日、出生前診断などの遺伝子技術を扱う私の勤め先が、何者かに放火される。町のあちこちに描かれた落書き消しを専門に請け負っている春は、現場近くに、スプレーによるグラフィティアートが残されていることに気づく。連続放火事件と謎の落書き、レイプという憎むべき犯罪を肯定しなければ自分が存在しない、という矛盾を抱えた春の危うさは、やがて交錯し…。




