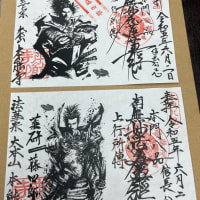『歴史群像』2009年2月号に近江高取山城が紹介されていました。
その存在は江戸時代の記録にも書かれながら、滋賀県の調査ですらその存在が発見できず近年になってやっと発見された山城。
2007年6月に管理人も『どんつき瓦版』の調査取材を行い記事を書いていますので、その記事に多少の追加を加えてご紹介します。
日本がまだ神話の時代で語られる頃、日本列島を産んだ神様である伊邪那美命が自らの入山地(入山とは亡くなる事だそうです)として選んだ山が“比婆之山”と呼ばれ、その山頂には比婆神社が建立されています。
比婆神社は、『古事記』の伝承が残る全国各地に残っていますが、近くに多賀大社がある彦根にも比婆神社があるのです。そしてこの山は神話に登場する高天原ではないかとも言われていてその本殿は標高669m地点のすぐ下に位置しています。
ある記録では、そんな比婆神社から東へ進む年貢道といわれる山道を1㎞ほど進んだ高取山の山頂に山城が築城されていたのだとか・・・それが男鬼城です。
比婆神社から人が殆ど通る事もない山道を方位磁石の針を頼りに東に進み、途中で野生の鹿に出会いながら2つ目の山の頂上直前に小さな堀切が見つかります。その向こうの急斜面を登りきると明らかに人の手の加わった盛土で囲まれた広場に到着します。これこそが男鬼城の入り口となる虎口でした。
その郭と思われる広場を越えるとまた急な2mほどの傾斜がある。これを進むとまた・・・といった感じの尾根を利用した階段状に連郭式となった遺構が残っているのです。
一旦頂上まで到着し安心すると、その向こうに降って、堀切を越えてまた登った先に後世の本丸と呼ばれるに相応しい郭に出会うことができます。もしかしたら西の城と東の城が二つで一つの機能を果たした“別城一郭”の様式を使った戦国初期に湖北地方で見られる様式だったのかもしれません。
本丸には25cm×15㎝くらいの大きさの石を1.5m近い高さに積み上げたと予想される石垣の遺構も見る事ができ驚きますが、その先には10m弱の深さの大堀切と2筋の小さな堀切が並ぶ3列の堀切という珍しい光景にも出会えたのでした。
山城はその立地条件の悪さから遺構が残りやすい傾向にはありますがこれほどまで見事に残ると感動を覚えてしまいます。
しかし、そんなハッキリした城郭に対して、どんな歴史を持っているのかが全然解らないのが高取城です。古い記録の中に『男鬼城主河原豊後守』という名前が登場する事からこの辺りに城があった事が判明しただけなのです。
標高673mの高取城が戦に使われたとは考え難いですが、(たぶん)中世城郭を身近に感じる貴重な歴史史跡には間違いないのではないでしょうか?
麓の男鬼町で聞いた話では、高取城の麓に勘定谷という場所があり、勘定奉行の屋敷(時代は不明)があったとの事ですから、今後の調査が期待されます。
この後に彦根の資料を漁っていると、城主である河原一族は江戸時代に大棟梁として日光東照宮の造営・改築に関わる甲良氏の一族である事がわかり、「甲良庄」のことを「河原庄」とも呼んでいたので“甲良”と“河原”の両方の姓があるようです(と言いますか読みが似ていたから両方ある可能性もあります)。
歴史上に“甲良豊後守宗広”と言う人物が居ます。
甲良宗広こそが、藤堂高虎から徳川家康へと紹介された先に記した大棟梁の始まりとなる人物ですが、その甲良一族は佐々木高氏(京極道誉)の子孫と言われています。
もしこの辺りを合わせて考えるなら、河原豊後守は甲良宗広の祖先か一族であり京極家の一族が男鬼城を築城したとも考えられるのです。この家が代々“豊後守”を称していたのなら戦国期辺りの京極家の没落と共に城主も本貫地の甲良庄に戻り、築城術を磨いたとも考えらえます。
そういえば『歴史群像』でも京極高広・高吉の築城説が挙げられていました。
甲良一族に繋げるなら彼らの3代前に枝分かれした京極高秀の系統になってしまうのですが、この辺りはこれからの調査を望むところです。
その存在は江戸時代の記録にも書かれながら、滋賀県の調査ですらその存在が発見できず近年になってやっと発見された山城。
2007年6月に管理人も『どんつき瓦版』の調査取材を行い記事を書いていますので、その記事に多少の追加を加えてご紹介します。
日本がまだ神話の時代で語られる頃、日本列島を産んだ神様である伊邪那美命が自らの入山地(入山とは亡くなる事だそうです)として選んだ山が“比婆之山”と呼ばれ、その山頂には比婆神社が建立されています。
比婆神社は、『古事記』の伝承が残る全国各地に残っていますが、近くに多賀大社がある彦根にも比婆神社があるのです。そしてこの山は神話に登場する高天原ではないかとも言われていてその本殿は標高669m地点のすぐ下に位置しています。
ある記録では、そんな比婆神社から東へ進む年貢道といわれる山道を1㎞ほど進んだ高取山の山頂に山城が築城されていたのだとか・・・それが男鬼城です。
比婆神社から人が殆ど通る事もない山道を方位磁石の針を頼りに東に進み、途中で野生の鹿に出会いながら2つ目の山の頂上直前に小さな堀切が見つかります。その向こうの急斜面を登りきると明らかに人の手の加わった盛土で囲まれた広場に到着します。これこそが男鬼城の入り口となる虎口でした。
その郭と思われる広場を越えるとまた急な2mほどの傾斜がある。これを進むとまた・・・といった感じの尾根を利用した階段状に連郭式となった遺構が残っているのです。
一旦頂上まで到着し安心すると、その向こうに降って、堀切を越えてまた登った先に後世の本丸と呼ばれるに相応しい郭に出会うことができます。もしかしたら西の城と東の城が二つで一つの機能を果たした“別城一郭”の様式を使った戦国初期に湖北地方で見られる様式だったのかもしれません。
本丸には25cm×15㎝くらいの大きさの石を1.5m近い高さに積み上げたと予想される石垣の遺構も見る事ができ驚きますが、その先には10m弱の深さの大堀切と2筋の小さな堀切が並ぶ3列の堀切という珍しい光景にも出会えたのでした。
山城はその立地条件の悪さから遺構が残りやすい傾向にはありますがこれほどまで見事に残ると感動を覚えてしまいます。
しかし、そんなハッキリした城郭に対して、どんな歴史を持っているのかが全然解らないのが高取城です。古い記録の中に『男鬼城主河原豊後守』という名前が登場する事からこの辺りに城があった事が判明しただけなのです。
標高673mの高取城が戦に使われたとは考え難いですが、(たぶん)中世城郭を身近に感じる貴重な歴史史跡には間違いないのではないでしょうか?
麓の男鬼町で聞いた話では、高取城の麓に勘定谷という場所があり、勘定奉行の屋敷(時代は不明)があったとの事ですから、今後の調査が期待されます。
この後に彦根の資料を漁っていると、城主である河原一族は江戸時代に大棟梁として日光東照宮の造営・改築に関わる甲良氏の一族である事がわかり、「甲良庄」のことを「河原庄」とも呼んでいたので“甲良”と“河原”の両方の姓があるようです(と言いますか読みが似ていたから両方ある可能性もあります)。
歴史上に“甲良豊後守宗広”と言う人物が居ます。
甲良宗広こそが、藤堂高虎から徳川家康へと紹介された先に記した大棟梁の始まりとなる人物ですが、その甲良一族は佐々木高氏(京極道誉)の子孫と言われています。
もしこの辺りを合わせて考えるなら、河原豊後守は甲良宗広の祖先か一族であり京極家の一族が男鬼城を築城したとも考えられるのです。この家が代々“豊後守”を称していたのなら戦国期辺りの京極家の没落と共に城主も本貫地の甲良庄に戻り、築城術を磨いたとも考えらえます。
そういえば『歴史群像』でも京極高広・高吉の築城説が挙げられていました。
甲良一族に繋げるなら彼らの3代前に枝分かれした京極高秀の系統になってしまうのですが、この辺りはこれからの調査を望むところです。