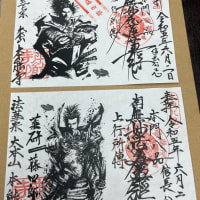2009年1月1日より2月3日まで彦根城博物館では『吉祥のデザイン―鶴と亀―』というテーマ展が行われています。
今回は1月10日に行われたギャラリートークで聞いてきた概要の簡単な紹介と展示物を一つ紹介します。
この展示でも前回同様注目している物が数点ありますので、何回かに分けてご紹介します。
まずは概要…
鶴と亀は、「鶴は千年亀は万年(最初は1200年くらいだった)」と言われるように長寿の証ですが、これは古代中国の鶴や亀を神格化した思想だったそうです。
それを日本風にアレンジされているのです。
中国では長生きすることが基本でこれは中国が現世を大切にする為だったようです。
鶴と亀はその代表でした。
特に鶴は鳥の中では長生きで、しかもつがいの仲が良く、片方を喪うともう片方はその後もずっと一人で過ごすことからつがいで描かれることが多いのです。
日本では現世よりも来世を大切にしていました。
また中国では仙人も長生きの象徴とされ多く描かれ、これも日本に入ってきたのです。
中国と日本では感覚の違いもあります。
たとえば牡丹の花
中国では富貴でおめでたい象徴ですが、日本では鑑賞の対象であり現実の美しさが愛でられるのです。
鶴も『万葉集』では、鳴き声が物悲しい感情に訴える生き物として歌が作られていました。
そんな鶴と亀を使った物は圧倒的に鶴が多く、亀の場合は鶴と一緒に描かれることが多いのです。
また松竹梅などの縁起物と一緒に描かれることもあります。
「中啓金地浜松白鶴図」
展示を見に行きますと、確かに鶴が多く、鶴は現実の物であるのに対し亀は四神思想に出てくる玄武のようなイメージが付いたデザインの方が多いのが特徴です。
亀に関しては尾の辺りに毛が付いている物が描かれますが、これは「蓑亀」といって、あまり動かない亀の背中に苔が付いてしっぽのように見える現象で非常に縁起がいい物がったそうです。
中啓とは能などで使う扇の事ですが、これは消耗品の為に残る事はほとんどありません。そしてこの展示物のデザインは亀が岩を背負っていてその上に松竹梅が生えている、亀自体がお目出度い島になっている物なのです。
これは『翁』専用で使われたものでした。
能は戦国期末期辺りの豊臣秀吉や徳川家康といった武将に愛され、江戸時代に入ってから徳川秀忠も能を好んだために幕府の式楽となり諸大名もこぞって学び能役者を抱えたり能道具を揃え、その頃のストーリー性がある能がイメージとして浮かびますが、元々は神に捧げる神事であった為にストーリー性はありませんでした。
『翁』はそんな古い形を残した能なのです。
今回は1月10日に行われたギャラリートークで聞いてきた概要の簡単な紹介と展示物を一つ紹介します。
この展示でも前回同様注目している物が数点ありますので、何回かに分けてご紹介します。
まずは概要…
鶴と亀は、「鶴は千年亀は万年(最初は1200年くらいだった)」と言われるように長寿の証ですが、これは古代中国の鶴や亀を神格化した思想だったそうです。
それを日本風にアレンジされているのです。
中国では長生きすることが基本でこれは中国が現世を大切にする為だったようです。
鶴と亀はその代表でした。
特に鶴は鳥の中では長生きで、しかもつがいの仲が良く、片方を喪うともう片方はその後もずっと一人で過ごすことからつがいで描かれることが多いのです。
日本では現世よりも来世を大切にしていました。
また中国では仙人も長生きの象徴とされ多く描かれ、これも日本に入ってきたのです。
中国と日本では感覚の違いもあります。
たとえば牡丹の花
中国では富貴でおめでたい象徴ですが、日本では鑑賞の対象であり現実の美しさが愛でられるのです。
鶴も『万葉集』では、鳴き声が物悲しい感情に訴える生き物として歌が作られていました。
そんな鶴と亀を使った物は圧倒的に鶴が多く、亀の場合は鶴と一緒に描かれることが多いのです。
また松竹梅などの縁起物と一緒に描かれることもあります。
「中啓金地浜松白鶴図」
展示を見に行きますと、確かに鶴が多く、鶴は現実の物であるのに対し亀は四神思想に出てくる玄武のようなイメージが付いたデザインの方が多いのが特徴です。
亀に関しては尾の辺りに毛が付いている物が描かれますが、これは「蓑亀」といって、あまり動かない亀の背中に苔が付いてしっぽのように見える現象で非常に縁起がいい物がったそうです。
中啓とは能などで使う扇の事ですが、これは消耗品の為に残る事はほとんどありません。そしてこの展示物のデザインは亀が岩を背負っていてその上に松竹梅が生えている、亀自体がお目出度い島になっている物なのです。
これは『翁』専用で使われたものでした。
能は戦国期末期辺りの豊臣秀吉や徳川家康といった武将に愛され、江戸時代に入ってから徳川秀忠も能を好んだために幕府の式楽となり諸大名もこぞって学び能役者を抱えたり能道具を揃え、その頃のストーリー性がある能がイメージとして浮かびますが、元々は神に捧げる神事であった為にストーリー性はありませんでした。
『翁』はそんな古い形を残した能なのです。