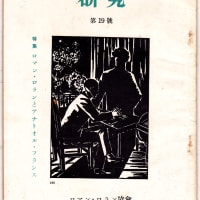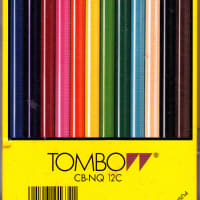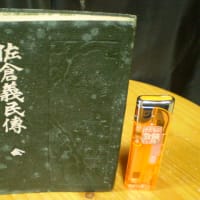無役地(むやくち)って、何だろう。それに、正しくは、これを何と読むのだろう。国語辞典にも日本史辞典にもなく、聞いたことのない言葉だ。はじめはさっぱりわからなかった。喧嘩や騒動は大好きだが、むずかしい理屈は苦手だ。しかも、市村敏麿が無役地事件に関わってからは、個人の史料もなくなる(わずかに新聞記事のみ)。
無役地というのは、庄屋の土地だ。庄屋が村役人として、村政を見るための、役給としてあてられた土地。村民のための政治をするための、いわば公務員にあてられた土地だから、村民にとっては、村の共有地である、という考え方も成り立つ。一方、代々世襲であった庄屋にしてみれば、これは自分の私有地だと思っている。
野村騒動は、庄屋の不正、横暴を糾弾した一揆でもあった。藩は、騒動の直後、庄屋の権限をとりあげ、村政は、横目や年行事など村役人たちの協議で運営するようにした。また、庄屋の無役地の調査にとりかかった。明治4年3月、藩は、庄屋の無役地(田畑)をすべてひきあげることにしたが、その直後、すべてをとりあげては庄屋も生活に困るだろうから、という理由で、その40パーセントを庄屋にあたえ、60パーセントをとりあげることにした。しかし、明治5年、間島冬道は、この60パーセントの土地も庄屋に返し、無役地は、すべて庄屋の私有地になる。
くわしくは、また、史料をあげて、逐次、書いていくつもりだが(書けるかわからないけど)、無役地事件は、これが発端だ。その後、農民たちは、無役地は農民の共有地だとして、無役地返還運動を起こす。この運動(裁判闘争)の代表になったのが(代表にさせられる)、市村敏麿であり、明治20年代の終わりまで続く。
さて、この無役地事件や野村騒動、一般用の「愛媛の歴史」ではどう書かれているのか調べてみた(県史や市史はのぞいたことがない)。
昭和48年刊の県史シリーズの「愛媛県の歴史」(田中歳雄)。
野村騒動について2行あり。
「たとえば、明治3年3月下旬、宇和郡の村から動きはじめて4月から5月には宇和島藩内の宇和・松柏地域にまで拡大した奥野郷一揆(参加人数1万5,6千人)、さらにはその影響をうけて蜂起した吉田藩三間騒動は、大豆銀納制という旧藩時代の貢租を継続していたことに端を発していたが、それだけでなく、庄屋組頭層の不正追及からその罷免要求にまで発展していた。これに対して、両藩とも藩兵を繰り出して鎮圧するのであるが、こうした農民たちの動向は、藩籍奉還という形だけの統一では現実の地方行政が円滑に推進されないことを示していた」
無役地事件については記事はなし。
同じく山川出版社。1988年の「愛媛県の百年」(島津豊幸編)。
野村騒動については、「南予をゆるがせた奥野郷一揆」の見出しのもとに、地図、写真も含め、5ページにわたって、書かれている(ただし、頭取鶴太郎の名はなし)。この本は明治後の100年の歴史を書いたものだが、野村騒動に5ページを使っているものの、無役地事件についてはいっさい記入なし。
同じく山川出版社。一番新しい県史シリーズで2003年刊の「愛媛県の歴史」(内田九州男編)。
野村騒動の記事はいっさいなし。ついでだが、武左衛門一揆についての記事もたったの6行。ただ、この版ではじめて無役地事件が登場している。「南予の無役地事件」という見出しで、3ページにわたって書いてある。ただ、記事は「市村敏麿の面影」に所収の東京自由新聞の記事を要約紹介したもので、新しい研究成果はないようだ。市村敏麿の写真ものせているので、無役地事件という存在を世に知らせた意義はある。松山藩領、東、中予にも、無役地と似たような「庄屋抜け地」というのがあったようで、「庄屋抜け地」を村の共有地にするような裁判闘争があったことをはじめて知った。この項を書いたのは矢野達雄という学者で、松山地方裁判所の裁判記録を調べて、このことを明らかにしたようだ。
それにしても、無役地事件、概要だけでは、とてもとてもよくわからん。わからないまま書いていこう。
無役地というのは、庄屋の土地だ。庄屋が村役人として、村政を見るための、役給としてあてられた土地。村民のための政治をするための、いわば公務員にあてられた土地だから、村民にとっては、村の共有地である、という考え方も成り立つ。一方、代々世襲であった庄屋にしてみれば、これは自分の私有地だと思っている。
野村騒動は、庄屋の不正、横暴を糾弾した一揆でもあった。藩は、騒動の直後、庄屋の権限をとりあげ、村政は、横目や年行事など村役人たちの協議で運営するようにした。また、庄屋の無役地の調査にとりかかった。明治4年3月、藩は、庄屋の無役地(田畑)をすべてひきあげることにしたが、その直後、すべてをとりあげては庄屋も生活に困るだろうから、という理由で、その40パーセントを庄屋にあたえ、60パーセントをとりあげることにした。しかし、明治5年、間島冬道は、この60パーセントの土地も庄屋に返し、無役地は、すべて庄屋の私有地になる。
くわしくは、また、史料をあげて、逐次、書いていくつもりだが(書けるかわからないけど)、無役地事件は、これが発端だ。その後、農民たちは、無役地は農民の共有地だとして、無役地返還運動を起こす。この運動(裁判闘争)の代表になったのが(代表にさせられる)、市村敏麿であり、明治20年代の終わりまで続く。
さて、この無役地事件や野村騒動、一般用の「愛媛の歴史」ではどう書かれているのか調べてみた(県史や市史はのぞいたことがない)。
昭和48年刊の県史シリーズの「愛媛県の歴史」(田中歳雄)。
野村騒動について2行あり。
「たとえば、明治3年3月下旬、宇和郡の村から動きはじめて4月から5月には宇和島藩内の宇和・松柏地域にまで拡大した奥野郷一揆(参加人数1万5,6千人)、さらにはその影響をうけて蜂起した吉田藩三間騒動は、大豆銀納制という旧藩時代の貢租を継続していたことに端を発していたが、それだけでなく、庄屋組頭層の不正追及からその罷免要求にまで発展していた。これに対して、両藩とも藩兵を繰り出して鎮圧するのであるが、こうした農民たちの動向は、藩籍奉還という形だけの統一では現実の地方行政が円滑に推進されないことを示していた」
無役地事件については記事はなし。
同じく山川出版社。1988年の「愛媛県の百年」(島津豊幸編)。
野村騒動については、「南予をゆるがせた奥野郷一揆」の見出しのもとに、地図、写真も含め、5ページにわたって、書かれている(ただし、頭取鶴太郎の名はなし)。この本は明治後の100年の歴史を書いたものだが、野村騒動に5ページを使っているものの、無役地事件についてはいっさい記入なし。
同じく山川出版社。一番新しい県史シリーズで2003年刊の「愛媛県の歴史」(内田九州男編)。
野村騒動の記事はいっさいなし。ついでだが、武左衛門一揆についての記事もたったの6行。ただ、この版ではじめて無役地事件が登場している。「南予の無役地事件」という見出しで、3ページにわたって書いてある。ただ、記事は「市村敏麿の面影」に所収の東京自由新聞の記事を要約紹介したもので、新しい研究成果はないようだ。市村敏麿の写真ものせているので、無役地事件という存在を世に知らせた意義はある。松山藩領、東、中予にも、無役地と似たような「庄屋抜け地」というのがあったようで、「庄屋抜け地」を村の共有地にするような裁判闘争があったことをはじめて知った。この項を書いたのは矢野達雄という学者で、松山地方裁判所の裁判記録を調べて、このことを明らかにしたようだ。
それにしても、無役地事件、概要だけでは、とてもとてもよくわからん。わからないまま書いていこう。