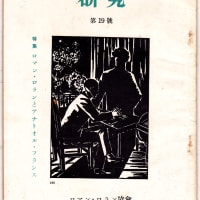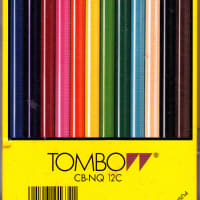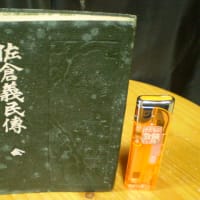今回は余談。
>それに弁官とは何だろう。東京の新政府の役なのだろうか?不明。12月26日、弁官から、二人に島流し(沖ノ島)10年に処すべきの指令が来る。
前回、こう書いたけど、「弁官」についてわかりました。今日、たまたま毛利敏彦の「江藤新平」を見てみたら、こう説明してあった。
「弁官の職務内容は、今日の内閣官房に法制局を併せたようなものであって、太政官最高首脳あての書類は弁官の事前審査を経由しなければならない仕組みであり、また、太政官が発する布告・達しや指令類の起案も弁官の任務であった。つまり、弁官は政府事務の中枢部を占め、太政官の意思決定に重要な役割を果たす存在であった」
死罪を伴う騒動については、弁官に伺いを立てる必要があったのかもしれない。
弁官には大弁(公家がなる)、中弁(次官級)、小弁とからなるが、この明治3年明治3年12月の中弁には江藤新平がいる。
江藤新平は、裁判制度の創設者だ。まだ、この時期には、裁判制度はできていなかったが、人民の権利のために裁判に訴える道を示した江藤の司法の精神にこの後の市村は共感をしめしたかもしれない。市村のその後の裁判闘争にかける情熱は、民権にかける理想を感じるからだ。明治5年江藤新平は初代司法郷になる。
市村と江藤新平にもなにかつながりがあるかもしれない(会ったことがなくても)。江藤は佐賀の乱に敗れたあと、宇和島に立ち寄っている。むろん、市村とは関係はないだろうが、なんでも市村と結びつける昨今、こんな空想も楽しい(笑)。
野村騒動のあと、宇和島藩庁は、4月にさっそく民部省に届け出ている。このころは、藩政府と新政府はこんな関係にあったのだろう。
「(なかば、省略。)本月3日頃、漸々承服随い、残らず帰村、自今にてはまず鎮静つかまつり候。始終、暴挙などは一切ござなく候えども、支配地内、静謐ならず、恐れ入り候につき、とりあえず、お届け、仕置き、巨細は追って取調べ申し上げ候」とある。
民部省につながりのある市村が書いたものだろう。
明治初期となると、すぐに征韓論、西南戦争から始まることが多い。征韓論前の、明治2年、3年、4年、5年のころの時代を調べた本がほしいのだが、あまりないようだ。この頃こそ、維新の最も革新的な改革は次々になされたのに、と思う。人事も官制もクルクル変わり、大事件も続出で、いわくいいがたしの時代だったのかもしれない。
>それに弁官とは何だろう。東京の新政府の役なのだろうか?不明。12月26日、弁官から、二人に島流し(沖ノ島)10年に処すべきの指令が来る。
前回、こう書いたけど、「弁官」についてわかりました。今日、たまたま毛利敏彦の「江藤新平」を見てみたら、こう説明してあった。
「弁官の職務内容は、今日の内閣官房に法制局を併せたようなものであって、太政官最高首脳あての書類は弁官の事前審査を経由しなければならない仕組みであり、また、太政官が発する布告・達しや指令類の起案も弁官の任務であった。つまり、弁官は政府事務の中枢部を占め、太政官の意思決定に重要な役割を果たす存在であった」
死罪を伴う騒動については、弁官に伺いを立てる必要があったのかもしれない。
弁官には大弁(公家がなる)、中弁(次官級)、小弁とからなるが、この明治3年明治3年12月の中弁には江藤新平がいる。
江藤新平は、裁判制度の創設者だ。まだ、この時期には、裁判制度はできていなかったが、人民の権利のために裁判に訴える道を示した江藤の司法の精神にこの後の市村は共感をしめしたかもしれない。市村のその後の裁判闘争にかける情熱は、民権にかける理想を感じるからだ。明治5年江藤新平は初代司法郷になる。
市村と江藤新平にもなにかつながりがあるかもしれない(会ったことがなくても)。江藤は佐賀の乱に敗れたあと、宇和島に立ち寄っている。むろん、市村とは関係はないだろうが、なんでも市村と結びつける昨今、こんな空想も楽しい(笑)。
野村騒動のあと、宇和島藩庁は、4月にさっそく民部省に届け出ている。このころは、藩政府と新政府はこんな関係にあったのだろう。
「(なかば、省略。)本月3日頃、漸々承服随い、残らず帰村、自今にてはまず鎮静つかまつり候。始終、暴挙などは一切ござなく候えども、支配地内、静謐ならず、恐れ入り候につき、とりあえず、お届け、仕置き、巨細は追って取調べ申し上げ候」とある。
民部省につながりのある市村が書いたものだろう。
明治初期となると、すぐに征韓論、西南戦争から始まることが多い。征韓論前の、明治2年、3年、4年、5年のころの時代を調べた本がほしいのだが、あまりないようだ。この頃こそ、維新の最も革新的な改革は次々になされたのに、と思う。人事も官制もクルクル変わり、大事件も続出で、いわくいいがたしの時代だったのかもしれない。