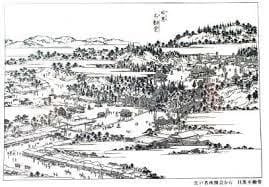前回は、女坂だった。
だから、当然、今回は、男坂となるのだが、男坂を上がると上の境内にあがってしまうので、男坂はパス、下の境内の石造物をめぐりたい。
下の境内を一巡りした後、男坂に戻り、石段を上がって本堂へ向かうつもり。
目黒不動尊の名物といえば、まず、「独鈷の滝」だろう。
「滝」というには、水量が不足だが、「瀧泉寺」の寺号はこの滝に由来している。

「独鈷」には、高僧がこれを投げ上げると、突き刺さった地面に何か不思議なことが起こるというイメージがある。

例えば、伊豆修善寺の独鈷の湯は、空海の投げた独鈷杵によって湧き出たことになっています。

目黒不動尊では、開山者慈覚大師の投じた独鈷杵によって二筋の水が、崖地から噴出した。
だから「独鈷の滝」。
不動明王を祀る寺の境内に流れ落ちる滝、しかもそれか江戸のど真ん中にあるのだから、山岳修行者がこれを見逃すわけがない。
滝行の名所として、目黒不動は名を馳せることになります。
名所だから、当然、広重の浮世絵にも描かれている。

絵の左、白い瀑布の下に立つふんどし姿が滝行中の修験者です。

現在では、浮世絵ほど、滝の水量がない。

だからか、滝行は行われていないが、では、いつ頃まで、滝行は行われていたのだろうか。
目黒区立八雲中央図書館で調べてみた。
昭和58年(1983)の『目黒区史跡散歩』には、「数は減ったが、今でも目黒不動で滝行をする姿がある」と載っている。
昭和34年(1959)の『郷土目黒第三巻』には、独鈷の滝での寒修行の記事があるので、転載しておきます。
「上目黒八丁目大橋近くの倉方国蔵と称する大工の棟梁の処には、東京者ばかりでない地方出の若い衆も弟子として住み込んでいた。其の若者たちは、毎年不動中心の寒参り修行を競争的に捨て身に命がけでやった。その姿は白衣に身を固め、白鉢巻で素足にわらじがけで、腰に屋号入りの提灯を下げ、六根清浄を唱えながら走った。

イメージ映像
道順は大橋から氏神氷川神社に先ず参拝し、日向通りを西郷山の下から、別所中目黒と田圃道を越え、八幡前から大鳥神社を過ぎ、目黒不動にと進んだ。その曲がりくねった路、当時の田圃や目黒川沿岸などは、夜道には相当淋しい処もあった。それを信心の一念で寒三十日の苦行を通したのである。若い衆達は不動尊の滝に心身を清浄になし、本堂前で甘酒一杯をねぎらわれ、又来た路を引き返して行った。」(「原田鍬三「目黒不動門前解雇後十年」)
では、滝行の写真はあるのだろうか。
八雲図書館の司書さんたちにも手伝ってもらって、探し回るが、ない。
昭和時代の、東京の年中行事の写真がないなどということは、信じられない。
目黒不動尊の社務所に電話をして、写真があるか尋ねるが、答えは「NO」。
滝行を止めた時期については、「10年前まで、一人やっていたが、それ以降は禁止している」との返事。
21世紀になっても、目黒不動尊では、滝行が行われていたことになる。
にもかかわらず、写真が見当たらないのだから、不思議というしかない。
このブログのテーマは、石造物。
独鈷の滝と水行場での石造物といえば、まずは「水かけ不動」でしょう。

説明板があります。
「當山の開基は天台座主第三祖慈覚大師圓仁で、一千二百有余年前の大同3年(808)大師自ら御本尊を彫刻し安置されたことに創まります。天安2年、大師が法具 「獨鈷」を投じて堂宇造営の敷地を卜されたところ、泉が忽ち湧出。涸れることのないその瀧泉は「獨鈷の瀧」と称されました。大師はお堂の棟札に、「大聖不動明王心身安養呪願成就瀧泉長久」と認め「瀧泉寺」と号され、「泰睿」の勅願を賜りし清和の御代に「泰叡山」が山号と定められました。春に花、夏瀧しぶき、秋紅葉、冬積もる雪と、関東最古の不動霊場は四季折折の風情が輝き、善男善女の心に安らぎをもたらします。「獨鈷の瀧」は不動行者の水垢離場となり、江戸幕末には西郷南洲翁が薩摩藩主島津斉彬公の當病平癒を祈願されました。「目黒不動尊御詠歌…清らけき 目黒の杜の獨鈷瀧 災厄難を除ける不動尊」。ここに、身代りで瀧泉に打たれてくださる「水かけ不動明王」が造立され、より清らかな心と身で目黒のお不動さまに参詣できることとなりました。合掌礼拝して「獨鈷の瀧」の霊水をかけ、洗心浄魂されて、大慈大悲の不動明王と大願成就のご縁をお結びください。平成8年5月吉日目黒不動尊別當泰叡山瀧泉寺』
水行場の向こう側、崖地のスロープには、いくつもの石造物が見えます。

近寄って刻文などをチェックしたいのですが、立ち入り禁止でダメ。

私のカメラの望遠機能では、ワンショットの写真を撮ることもできず、情けないが、この区域の石造物については、ノータッチということになります。
≪参考資料≫
◇目黒区郷土研『郷土目黒第3巻』昭和34年