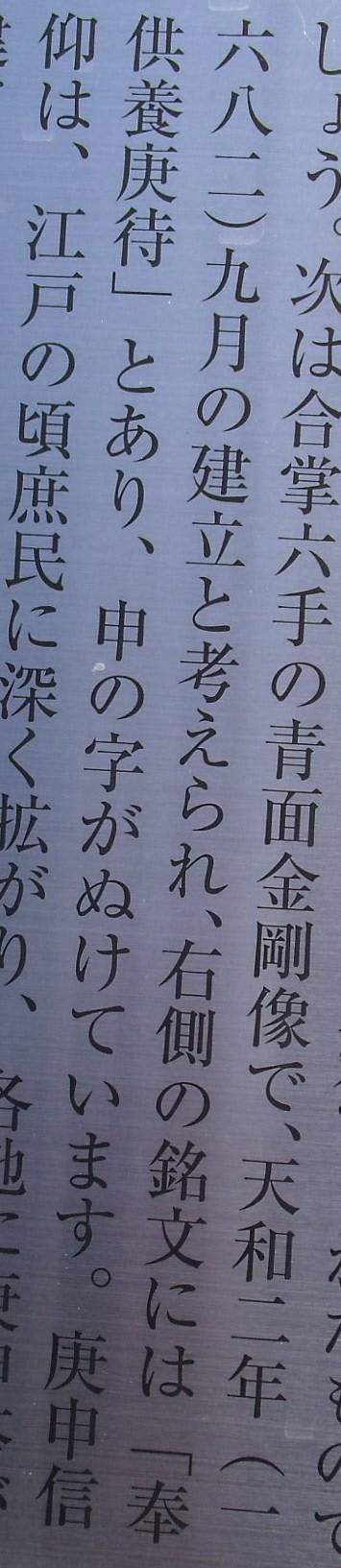「亀趺」は「きふ」と読む。
語意は、「〔名〕かめの形に刻んだ碑の台石。転じて、碑の異称。」(日本国語大辞典)
古来、中国では、亀は万年の寿齢を保つ霊獣とされてきた。
石で亀の形を作り、その背に碑を載せることで、その碑が永遠に後世に残ることを念じて建てられるのが、亀趺。
多くの場合、行状碑(特定の人物の業績を記した碑)として用いられますが、墓標として使用されることもあります。
初めて亀趺を見たのは、墨田区向島の弘福寺でした。
石仏めぐりの手段として、都内の寺を順繰りに訪ねている途中のことでした。
亀趺の何たるかも知らず、「へえ、変わったお墓だなあ」と思った覚えがあります。


池田冠山の墓 池田冠山の行状碑
因幡若桜(いなばわかさ)藩主であり、儒学者でもある池田冠山の墓と行状碑、二つとも亀趺であるのが珍しい。
写真を整理していて、亀趺という言葉をこの時初めて知りました。
不思議なもので、間を置かずして、次の亀趺に出会うことになります。
春日通りから少し引っ込んだ所にある麟祥院は、都会の喧騒とは無縁な森閑としたしじまの中にあります。

麟祥院(文京区)
春日通りは春日局に因んだ名前ですが、麟祥院はその春日局の菩提寺です。
山門を入ると左前方に寺の顕彰碑があり、台石が亀趺となっています。


麟祥院の亀趺
造立は、宝暦8年(1758)。
肝心の顕彰の中身は?と問われると困ってしまう。
刻字が読みにくいというのは弁解で、刻文が読みとれないのです。
弘福寺の亀趺も同じこと。
誠になさけない。
石造物と接していると、いつもこの「読めない」問題に直面します。
造立した江戸の人たちも、後世の日本人がこんなに読解力に欠けるなんて思いもしなかったに違いない。
話しを元に戻そう。
上野の寛永寺にも亀趺が1基ある。
1基ある、と書いたが、本音を云えば、1基しかない、と書きたいのです。
というのは、亀趺は中国生まれですが、その建立は貴族階級以上にしか認められませんでした。
このシステムは、そのまま日本にも持ち込まれました。
亀趺が流行ったのは江戸時代からですが、江戸時代は身分社会が花盛り。
当然徳川将軍家の墓地に亀趺が群れをなしていてもおかしくありません。
ところが、寛永寺にはたった1基、それも徳川家とは無縁な僧侶の顕彰碑としての亀趺があるだけです。


了翁禅師塔碑(寛永寺)
増上寺には亀趺はありません。
では、徳川家は亀趺と無縁かというとそんなことはない。
水戸徳川家の墓地には、いくつも亀趺がみられるのです。
現在、東京には亀趺はわずかしかありません。
おそらく10基未満でしょう。
なぜ、こんなに少ないのか、不思議でなりません。
亀趺を見れば、故人のステータスが分かる。
そんな正統的シンボル装置が何故流行しなかったのか、亀趺を見るたびにいつも疑問に思うのです。
以下は、たまたま出会った東京とその近郊の亀趺の写真です。


品川寺(品川区)の亀趺
品川寺の近くの東海寺大山墓地には、開山沢庵和尚を顕彰する亀趺があります。


東海寺大山墓地の沢庵和尚顕彰碑


浅草寺(台東区)の亀趺
浅草寺の亀趺碑にはびっしりと3面に文字が刻んであります。
浅草寺の金石文を解説する『浅草寺のいしぶみ』によれば、四季を詠んだ狂歌36首だとか。
大垣市人を撰者として、文化14年(1817)に建立されたものですが、顕彰碑や行状碑ではない歌を刻んだ亀趺は極めて珍しい(らしい)。
さいたま市では、個人の墓に亀趺が使用されている。


長伝寺(さいたま市中央区)の亀趺の墓標
亀の下に、松竹梅、その下に邪鬼。
どういう意味が込められているのだろうか。
墓ではないが、供養塔の亀趺が秩父にあります。
秩父観音霊場の4番札所金昌寺は石仏の寺として有名。

4番札所金昌寺(秩父市)
石仏の数1200基とか1300基とか。
中に1基、お地蔵さんが亀趺の上に座しています。


金昌寺の亀趺供養塔
亀の背中の石柱には「三界万霊 六親眷族 七世父母」の文字。
先祖の追善供養塔であることは明らかです。

良く見ると亀の顔がおかしい。
亀というよりは龍の顔に似ています。
平瀬氏の「日本の亀趺」というHPによれば、中国では亀首だけなのに、朝鮮では亀首と獣首があって、日本は朝鮮の影響で2種類の首があるのだそうです。
ここまでの7基の亀趺を振り返ってみても、亀と龍と両方があることが分かります。
中央線武蔵境駅南口前の観音禅寺には平成12年の新しい亀趺が2基建っています。

観音禅寺(武蔵野市)の亀趺
寺伝碑ですが、碑に比べて亀の大きさが目立ちます。


頭は獣首、なぜ亀首ではないのかお寺に訊いてみたい気がします。
平成12年造立の観音禅寺が最も新しい亀趺ではないかと思っていたら、もっと新しい亀趺がありました。
飯能市の智観寺。
先祖供養を兼ねた鐘楼改修記念碑が平成16年の建立です。


智観寺(飯能市)の亀趺
智観寺には開基者中山氏の次男信吉の顕彰碑が収蔵庫に保管されているが、その顕彰碑は木製で亀趺座に立っているという。
収蔵庫の中の亀趺に因んで、中国に発注して製作したのがこの石造亀趺らしい。
川越の喜多院にも亀趺がある。
場所は、川越藩主松平大和守歴代藩主の廟所の入り口。

石碑のない喜多院(川越市)の亀趺
亀趺であることは確かだが、上にあるべき石碑がないので、碑文が不明です。
喜多院の社務所に問い合わせしたが、分からないという返事。
ご存知の方、教えてください。
このブログ作成中、江戸東京博物館へ「発掘された日本列島2012」を観に行った。
入り口への長いアプローチの右側に亀趺に乗った徳川家康像があることに初めて気づきました。


江戸東京博物館(墨田区)の徳川家康像
とても大きな亀です。
これまで何度も見かけたはずなのに、気付かなかったのは、亀趺に興味がなかったからでしょう。
関心を持っていれば、こうして容易に発見できるのだから、都内だけでも10指を越える亀趺があるのではないかと推測するのです。
このブログを書いて9カ月、池上本門寺にも亀趺があることを知りました。
教えてくれたのは、昔の勤め先での若い同僚夫婦の友人女性。
大田区のボランティア観光ガイドでもある彼女の案内で、本門寺を回ってきました。

本門寺(大田区池上1)
石仏巡りをしていると、日蓮宗と真宗寺院は避けることが多くなります。
境内に見るべき石仏がないのが普通だからです。
だから、本門寺を中心とする池上界隈には寺院は多いのですが、行ったことはありません。
本門寺へも1度行ったきりで、その時も墓地に入ることはなかったので、亀趺があることに気付きませんでした。
石仏に興味を持つ以前のことですから、亀趺を知っているはずもなく、見たとしても記憶に残っている訳がありません。
本門寺の墓地は広い境内に分散しています。
だから亀趺もあちこちにあるのですが、とりわけ宝塔のそばの絵師・狩野派の墓域に多く見られます。


面白いのは、極端にデザイン化した亀趺があること。


これが亀だとピンと来る人は、少ないのではないでしょうか。
施主の希望なのか、石工のアイデアなのか、それとも経費が安いからか、こうした亀趺が出来た経緯を知りたいものです。