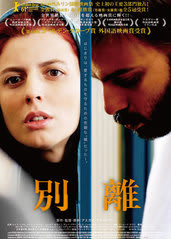世の中には映画ファンを自認している人はけっこういると思うが、当然のことながら映画に対するスタンスはそれぞれ違う。私みたいに、面白そうだと思う映画はジャンル関係なく観てしまう者もいれば、ハリウッド製アクション映画が好きな人、あるいは時代劇に関して一家言持っていたり、ミニシアターの熱心な観客もいるだろう。ただし、中には“困った人達”も存在する。その“困り具合”は各人さまざまだが(笑)、一番始末に負えないのは“古い映画にしか価値を見出さない者”だと思う。
もちろん、古い映画が好きでも一向に構わない。私だって昔の映画を観て感心することは多々あるし、若い時分に観た映画を思い出して感慨に浸ることもある。しかしその“困った人達”は、古い映画こそが最上のものであると信じ込んでいる。さらにそのことを周囲の者に向かって(誰も頼みもしないのに)滔々と言い募る。
昔は偉大な監督達が顔を揃え、綺羅星のごとき名優が多数存在し、まことに素晴らしかった云々と述べた後、決まって出るのは“今の映画はダメだねぇ”というセリフだ。
映画に限らず、音楽でも演劇でも娯楽小説でもマンガでも何でもそうだが、“昔のものは良かった。対して最近の○○はつまらん”と無節操に吹聴する者は、大抵その“最近の○○”を知らない。さらに彼らの言う“素晴らしかった古き良き時代”というのは“自分が若かった頃”である場合が多い。つまり意地悪な言い方をすれば、彼らの頭の中はある意味“若い頃で停止している”ということだ。
映画は娯楽であるが、時代性を照射していなければ娯楽足り得ることは難しい。映画は過去の遺物ではなく、現在進行形である。過去に拘泥するばかりでは、新鮮な感動は得られない。今作られているものは、今観てこそ価値があるのだ。
ハッキリ言って、昔の映画のことばかり話す人は、総じて退屈である。昔の価値観でしか物事を捉えられていない。そんなことは自分の心の中にとどめておくか、せいぜい自身のブログか何かに書くだけでよろしい。こっちが聞きたくもないのに延々と話しかけないでいただきたい。
ともあれ趣味の世界において、自身の見解を他人に押し付けるほど不粋なことは無い。昔の映画ばかり褒めそやし、現在の映画を(ロクに観もしないのに)頭から否定するような者は、逆に言えば今の映画を素直に楽しんでいる多くの観客をバカにしているも同様だ。
自分だけを高みに置いたように現在の映画を軽く見る者に対しては、自身はそれほど御大層な人間なのか一度考えてみろと言いたいが、それを実際に口に出すと剣呑な話になりかねないのでやらない(笑)。ただ、そんな“古い映画ばかりに執着する奴”は他者からは距離を置かれるのは確実。知らぬは当人ばかりというのは、何とも情けない話である。




もちろん、古い映画が好きでも一向に構わない。私だって昔の映画を観て感心することは多々あるし、若い時分に観た映画を思い出して感慨に浸ることもある。しかしその“困った人達”は、古い映画こそが最上のものであると信じ込んでいる。さらにそのことを周囲の者に向かって(誰も頼みもしないのに)滔々と言い募る。
昔は偉大な監督達が顔を揃え、綺羅星のごとき名優が多数存在し、まことに素晴らしかった云々と述べた後、決まって出るのは“今の映画はダメだねぇ”というセリフだ。
映画に限らず、音楽でも演劇でも娯楽小説でもマンガでも何でもそうだが、“昔のものは良かった。対して最近の○○はつまらん”と無節操に吹聴する者は、大抵その“最近の○○”を知らない。さらに彼らの言う“素晴らしかった古き良き時代”というのは“自分が若かった頃”である場合が多い。つまり意地悪な言い方をすれば、彼らの頭の中はある意味“若い頃で停止している”ということだ。
映画は娯楽であるが、時代性を照射していなければ娯楽足り得ることは難しい。映画は過去の遺物ではなく、現在進行形である。過去に拘泥するばかりでは、新鮮な感動は得られない。今作られているものは、今観てこそ価値があるのだ。
ハッキリ言って、昔の映画のことばかり話す人は、総じて退屈である。昔の価値観でしか物事を捉えられていない。そんなことは自分の心の中にとどめておくか、せいぜい自身のブログか何かに書くだけでよろしい。こっちが聞きたくもないのに延々と話しかけないでいただきたい。
ともあれ趣味の世界において、自身の見解を他人に押し付けるほど不粋なことは無い。昔の映画ばかり褒めそやし、現在の映画を(ロクに観もしないのに)頭から否定するような者は、逆に言えば今の映画を素直に楽しんでいる多くの観客をバカにしているも同様だ。
自分だけを高みに置いたように現在の映画を軽く見る者に対しては、自身はそれほど御大層な人間なのか一度考えてみろと言いたいが、それを実際に口に出すと剣呑な話になりかねないのでやらない(笑)。ただ、そんな“古い映画ばかりに執着する奴”は他者からは距離を置かれるのは確実。知らぬは当人ばかりというのは、何とも情けない話である。