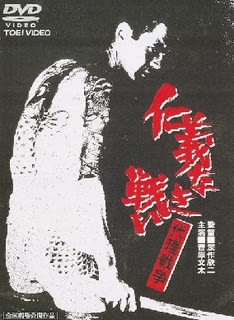(原題:JURASSIC WORLD: DOMINION)概ね納得できる内容だと思う。もちろん、突っ込みどころは多々あり、ウェルメイドな出来とは言えないだろう。しかし、長きに渡って続いたこのシリーズの完結編としては容認できる。今までの辻褄をすべて合わせようとすれば、一本の映画ではカバーできない。かといって、今さら別の方向にストーリーラインを変えて目新しさを狙うのもリスクが高い。だから、今回のようなレベルで丁度いいのだ。
4年前、かつてジュラシック・ワールドがあったイスラ・ヌブラル島が噴火で壊滅し、救出された恐竜たちは逃げ出して世界各地で繁殖するようになってしまった。ジュラシック・ワールドの元恐竜監視員のオーウェン・グレイディと同ワールドの管理者であったクレア・ディアリングは、パークの創設者ロックウッドの孫娘(実はロックウッドの死亡した娘のクローン)メイジーを守りながら、シエラネバダ山脈の人里離れた山小屋で暮らしていた。

ある日、オーウェンは子連れのヴェロキラプトルのブルーと再会。しかし、その子供とメイジーが何者かに誘拐され、オーウェンはクレアと共に救出に向かう。一方、恐竜の研究を総合的に引き受けている巨大バイオテクノロジー企業のバイオシンに関する醜聞を追うエリー・サトラー博士は、旧友のアラン・グラント博士の協力を得て、同社の研究所に乗り込む。そこにすでに勤務していたイアン・マルコム博士は2人に手を貸すが、バイオシン社のCEOであるルイス・ドジスンは、それを妨害する。
オーウェンが設立を目指している恐竜保護区が、とても恐竜の生存に適しているとは言えないエリアだったり、彼が恐竜を捕獲するシーンも違和感満載だ。バイオシン社の目的(悪だくみ)は“誰でも考え付くようなレベル”でしかない。そもそも、途中で一時的にクリーチャーの“主役”が恐竜からバイオシン社謹製の巨大イナゴに置き換わるという筋書きも、完全に無理筋である。
しかしながら、少なくない欠点があることを承知の上で本作を認めたい。それは、恐竜をあえて“脇役”に据え、生身の人間中心のアクション編に徹しているからだ。恐竜の造形などは前作までにアイデアが出尽くしていて、今さら重要視しても第一作(93年)のインパクトには及ばない。その意味で、この割り切り方は賢明だ。

世界を股にかけて(?)飛び回るオーウェンとクレア、そして謎の研究所に潜入するエリーとアランの描き方は、まるでジェームズ・ボンド映画のノリだ。特にマルタ島でのチェイス・シーンはかなり盛り上がる。クライマックスの大炎上も、007シリーズでよく見かけるバターンだ。ラストはSDGsを意識したと思われる処置だが(笑)、これで良いと思う。
コリン・トレボロウの演出は突出したものは感じられないが、147分という尺を退屈させずに乗り切っている。キャスト面で嬉しいのは、前回から引き続き登板のクリス・プラットとブライス・ダラス・ハワードをはじめ、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラム、サム・ニール、B・D・ウォンと、今までのシリーズの出演陣がカーテンコールのように顔を揃えていること。最終作に相応しい扱いだ。ディワンダ・ワイズにマムドゥ・アチー、イザベラ・サーモン、キャンベル・スコット等の他の面子も悪くない。
4年前、かつてジュラシック・ワールドがあったイスラ・ヌブラル島が噴火で壊滅し、救出された恐竜たちは逃げ出して世界各地で繁殖するようになってしまった。ジュラシック・ワールドの元恐竜監視員のオーウェン・グレイディと同ワールドの管理者であったクレア・ディアリングは、パークの創設者ロックウッドの孫娘(実はロックウッドの死亡した娘のクローン)メイジーを守りながら、シエラネバダ山脈の人里離れた山小屋で暮らしていた。

ある日、オーウェンは子連れのヴェロキラプトルのブルーと再会。しかし、その子供とメイジーが何者かに誘拐され、オーウェンはクレアと共に救出に向かう。一方、恐竜の研究を総合的に引き受けている巨大バイオテクノロジー企業のバイオシンに関する醜聞を追うエリー・サトラー博士は、旧友のアラン・グラント博士の協力を得て、同社の研究所に乗り込む。そこにすでに勤務していたイアン・マルコム博士は2人に手を貸すが、バイオシン社のCEOであるルイス・ドジスンは、それを妨害する。
オーウェンが設立を目指している恐竜保護区が、とても恐竜の生存に適しているとは言えないエリアだったり、彼が恐竜を捕獲するシーンも違和感満載だ。バイオシン社の目的(悪だくみ)は“誰でも考え付くようなレベル”でしかない。そもそも、途中で一時的にクリーチャーの“主役”が恐竜からバイオシン社謹製の巨大イナゴに置き換わるという筋書きも、完全に無理筋である。
しかしながら、少なくない欠点があることを承知の上で本作を認めたい。それは、恐竜をあえて“脇役”に据え、生身の人間中心のアクション編に徹しているからだ。恐竜の造形などは前作までにアイデアが出尽くしていて、今さら重要視しても第一作(93年)のインパクトには及ばない。その意味で、この割り切り方は賢明だ。

世界を股にかけて(?)飛び回るオーウェンとクレア、そして謎の研究所に潜入するエリーとアランの描き方は、まるでジェームズ・ボンド映画のノリだ。特にマルタ島でのチェイス・シーンはかなり盛り上がる。クライマックスの大炎上も、007シリーズでよく見かけるバターンだ。ラストはSDGsを意識したと思われる処置だが(笑)、これで良いと思う。
コリン・トレボロウの演出は突出したものは感じられないが、147分という尺を退屈させずに乗り切っている。キャスト面で嬉しいのは、前回から引き続き登板のクリス・プラットとブライス・ダラス・ハワードをはじめ、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラム、サム・ニール、B・D・ウォンと、今までのシリーズの出演陣がカーテンコールのように顔を揃えていること。最終作に相応しい扱いだ。ディワンダ・ワイズにマムドゥ・アチー、イザベラ・サーモン、キャンベル・スコット等の他の面子も悪くない。