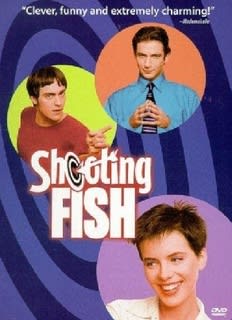(原題:Shallow Grave )94年イギリス作品。ダニー・ボイル監督の長編映画デビュー作で、ヒッチコック作品を思わせるような内容と、独特の演出リズムが印象付けられる一本。ただし、出来の方はそれほど高く評価するようなものではなく、作り手の気負った態度が垣間見える。まあ、今は著名な演出家であるダニー・ボイルのフィルモグラフィをチェックする上での“資料的な”意味合いはあるだろう。
グラスゴーの広いマンションの一室で共同生活をするジャーナリストのアレックスと医師のジュリエット、そして会計士のデイヴィッドの3人は、新たなルームメイトを募集していた。そこにやってきたのが自称作家のヒューゴーで、ジュリエットは彼を気に入ってしまう。

ところがある日、部屋からなかなか出てこないヒューゴーを心配した3人が中に入ると、彼の死体と麻薬、そして札束が満載のスーツケースを発見。金に目が眩んだ3人は、警察に通報せずに死体を遺棄する。だが、ヒューゴーを追う麻薬組織の殺し屋が3人に迫り、やがて警察も事件をかぎつける。切羽詰まった彼らは自暴自棄な行動に出る。ジョン・ホッジによるオリジナル脚本の映画化だ。
表面的には仲良くしていた登場人物たちが、大金を前にして理性を失っていくという筋書きは、よくあるパターンながら悪くない。当のアレックスが新聞社から、この事件の取材を命じられるあたりも面白い。しかしながら、彼らが死体を処分したぐらいでバレないと思い込んでいるのは、いかにも浅はかだ。やるならやるで、もっと綿密な計画を練ってくれないと観る方は納得しない。
そもそもこの所業は当初から互いに裏切らないと踏んでの話でなければならず、各人が疑心暗鬼を露わにするのが早すぎるのは愉快になれない。また、それを不自然に思わせないだけの各キャラクターの内面描写が覚束ない。とはいえ、小気味良い作劇とスタイリッシュな画面造形は、次作の「トレインスポッティング」(96年)にも引き継がれており、そのあたりは興味深い。
ユアン・マクレガーにクリストファー・エクルストン、ケリー・フォックスというキャストは万全で、特に若い頃のマクレガーは無鉄砲に粋がっている売文屋をうまく表現していた。ブライアン・テュファノのカメラとサイモン・ボスウェルの音楽も及第点である。
グラスゴーの広いマンションの一室で共同生活をするジャーナリストのアレックスと医師のジュリエット、そして会計士のデイヴィッドの3人は、新たなルームメイトを募集していた。そこにやってきたのが自称作家のヒューゴーで、ジュリエットは彼を気に入ってしまう。

ところがある日、部屋からなかなか出てこないヒューゴーを心配した3人が中に入ると、彼の死体と麻薬、そして札束が満載のスーツケースを発見。金に目が眩んだ3人は、警察に通報せずに死体を遺棄する。だが、ヒューゴーを追う麻薬組織の殺し屋が3人に迫り、やがて警察も事件をかぎつける。切羽詰まった彼らは自暴自棄な行動に出る。ジョン・ホッジによるオリジナル脚本の映画化だ。
表面的には仲良くしていた登場人物たちが、大金を前にして理性を失っていくという筋書きは、よくあるパターンながら悪くない。当のアレックスが新聞社から、この事件の取材を命じられるあたりも面白い。しかしながら、彼らが死体を処分したぐらいでバレないと思い込んでいるのは、いかにも浅はかだ。やるならやるで、もっと綿密な計画を練ってくれないと観る方は納得しない。
そもそもこの所業は当初から互いに裏切らないと踏んでの話でなければならず、各人が疑心暗鬼を露わにするのが早すぎるのは愉快になれない。また、それを不自然に思わせないだけの各キャラクターの内面描写が覚束ない。とはいえ、小気味良い作劇とスタイリッシュな画面造形は、次作の「トレインスポッティング」(96年)にも引き継がれており、そのあたりは興味深い。
ユアン・マクレガーにクリストファー・エクルストン、ケリー・フォックスというキャストは万全で、特に若い頃のマクレガーは無鉄砲に粋がっている売文屋をうまく表現していた。ブライアン・テュファノのカメラとサイモン・ボスウェルの音楽も及第点である。