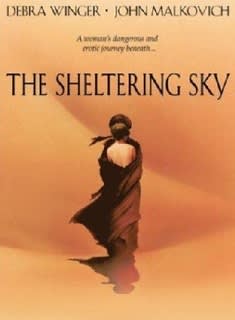(原題:i Three Amigos! )86年作品。お手軽すぎる邦題は、監督ジョン・ランディスの代表作「ブルース・ブラザーズ」(80年)の二番煎じを狙ったものだ。内容もそれに相応しく(?)超ライトで歯ごたえのない、観た後すぐに忘れてしまいそうになる脱力系コメディである。だが、本作は内容自体よりも“周辺のネタ”の方が興味深い。その意味ではコメントするに値するシャシンである。
1916年のメキシコ。辺境の地にあるサント・ポコ村は、エル・グアポ率いる盗賊団のために危機的状況にあった。そのため村長の娘カルメンは盗賊団を撃退してくれる用心棒を探していたが、たまたま町の教会で上映されていたサイレント活劇映画「スリーアミーゴス」を観て実在の英雄のドキュメンタリー映像だと勘違いし、ハリウッドにスリーアミーゴスへの救いを求める電報を打った。これを受け取った件の映画の主演3人組は、これはメキシコでの新作映画のオファーだと思い込み、嬉々として現地へ向かう。
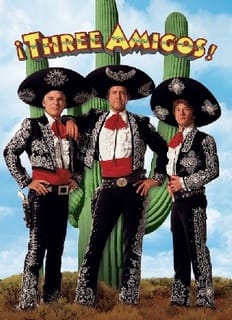
要するに黒澤明の「七人の侍」のパロディで、知らぬ間に盗賊団に立ち向かうハメになった落ち目の俳優たちの悪戦苦闘を賑々しく描こうという作戦だ。設定は悪くなく、上手く作ればかなりウケの良いお笑い編に仕上がったところだが、ドラマの建付けがガタガタでギャグのキレも悪く、出るのはタメ息と失笑のみだ。
ジョン・ランディスの演出は「ブルース・ブラザーズ」を撮った者と同一人物であることが信じられないほど覇気が無い。特にスティーヴ・マーティンにチェビー・チェイス、マーティン・ショートという当時人気絶頂にあった喜劇役者を起用していながら、ほとんど良さが出ていないことには閉口する。事実、その頃の本国の批評家の一致した見解は“つまらない”というものだったらしい。
だが前述の通り、この映画は関連するネタの方が面白い。まず、当初予定されていたキャスティングがダン・エイクロイドにジョン・ベルーシ、ビル・マーレイ、ロビン・ウィリアムズ、リック・モラニスであり、監督にはスピルバーグが検討されていたとか。そんな大物たちが参加するような題材なのか疑わしいが、もしも実現していたならば“大作”に仕上がっていたかもしれない。
そしてこの映画、何と日本公開時は地方ではオリバー・ストーン監督のアカデミー受賞作「プラトーン」との二本立てだったのだ。ベトナム戦争を扱った超シリアスな問題作と、能天気なおちゃらけ映画とのコラボレーションという、今から考えると究極的にシュールな状態が現出していたことを考えると、この映画の存在感(?)も捨てたものではないと思わせる。なお、本作は三谷幸喜が絶賛しており、なるほど生ぬるい展開の三谷作品と通じるものはあるようだ(苦笑)。
1916年のメキシコ。辺境の地にあるサント・ポコ村は、エル・グアポ率いる盗賊団のために危機的状況にあった。そのため村長の娘カルメンは盗賊団を撃退してくれる用心棒を探していたが、たまたま町の教会で上映されていたサイレント活劇映画「スリーアミーゴス」を観て実在の英雄のドキュメンタリー映像だと勘違いし、ハリウッドにスリーアミーゴスへの救いを求める電報を打った。これを受け取った件の映画の主演3人組は、これはメキシコでの新作映画のオファーだと思い込み、嬉々として現地へ向かう。
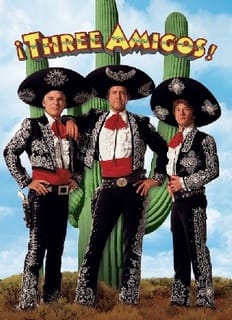
要するに黒澤明の「七人の侍」のパロディで、知らぬ間に盗賊団に立ち向かうハメになった落ち目の俳優たちの悪戦苦闘を賑々しく描こうという作戦だ。設定は悪くなく、上手く作ればかなりウケの良いお笑い編に仕上がったところだが、ドラマの建付けがガタガタでギャグのキレも悪く、出るのはタメ息と失笑のみだ。
ジョン・ランディスの演出は「ブルース・ブラザーズ」を撮った者と同一人物であることが信じられないほど覇気が無い。特にスティーヴ・マーティンにチェビー・チェイス、マーティン・ショートという当時人気絶頂にあった喜劇役者を起用していながら、ほとんど良さが出ていないことには閉口する。事実、その頃の本国の批評家の一致した見解は“つまらない”というものだったらしい。
だが前述の通り、この映画は関連するネタの方が面白い。まず、当初予定されていたキャスティングがダン・エイクロイドにジョン・ベルーシ、ビル・マーレイ、ロビン・ウィリアムズ、リック・モラニスであり、監督にはスピルバーグが検討されていたとか。そんな大物たちが参加するような題材なのか疑わしいが、もしも実現していたならば“大作”に仕上がっていたかもしれない。
そしてこの映画、何と日本公開時は地方ではオリバー・ストーン監督のアカデミー受賞作「プラトーン」との二本立てだったのだ。ベトナム戦争を扱った超シリアスな問題作と、能天気なおちゃらけ映画とのコラボレーションという、今から考えると究極的にシュールな状態が現出していたことを考えると、この映画の存在感(?)も捨てたものではないと思わせる。なお、本作は三谷幸喜が絶賛しており、なるほど生ぬるい展開の三谷作品と通じるものはあるようだ(苦笑)。