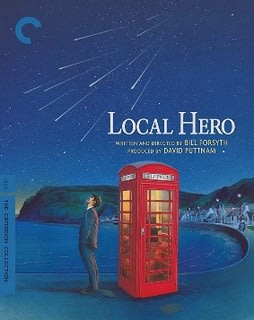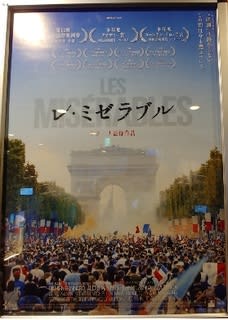(原題:RAMBO:LAST BLOOD)鑑賞前は映画の出来にはほとんど期待しておらず、実際観た後も内容の薄さが印象付けられる結果になったが、観て損したとはまったく思わない。82年に製作された第一作から、私はすべてリアルタイムで観ている。このシリーズがこれで終わりだという事実は、感慨深いものがある。そして、改めて主人公のキャラクターが浮き彫りになった点も認めたい。
ミャンマーでの死闘を終えて久々に故郷のアリゾナに帰ったジョン・ランボーは、古くからの友人マリアとその孫娘ガブリエラと一緒に、まるで家族のように暮らすようになって約10年が経っていた。だが、高校を卒業したガブリエラは自分を捨てた実の父親がメキシコにいると知り、ランボーとマリアの反対を押し切って一人でメキシコに旅立ってしまう。かつて別れた父には会えたが、相手はガブリエラを今も邪魔者だと思っていた。傷心の彼女は悪友の誘いで危険な地域に踏み込むと、人身売買カルテルに掠われてしまう。ランボーはガブリエラを救出すべく、単身メキシコに乗り込む。
前回までの敵役は、正式に組織された軍隊であった。だからさすがのランボーも苦戦し、そこから逆襲に転じるプロセスにカタルシスを覚えたものだ。しかし、今回の敵は単なるヤクザ、つまりはアマチュアに近い。元グリーンベレーのランボーの相手としてはまるで力不足である。メキシコまで出向くならば、大手麻薬カルテルの武装組織ぐらい持って来て欲しかった。
戦いの段取りにしても、敵方はわざわざランボーの仕掛けた罠に面白いようにハマってれるし、そもそも前段階でメキシコの敵のアジトに正面から乗り込んでボコボコにされるあたりも、観ていて脱力する。しかしながら、今まで戦いに明け暮れたランボーの苦悩が上手く表現されている点は認めたい。
彼は、アリゾナの牧場での平穏な暮らしの中にあっても、家の周囲に地下壕を掘りトラップを仕掛ける。そう、いつ敵が攻めてくるか分からないからだ。今回はたまたまメキシコの犯罪組織とのバトルにおいてそれらは役に立ったが、たとえ彼の残りの人生で戦いが起こらなくても、永遠に武装し続けるのだろう。
そして彼を助けた女流ジャーリストとの会話で“復讐なくしては先に進めない”とまで断言してしまう。その悲しい性には胸に詰まるものがある。エンディングのタイトルバックでそれまでの戦いがリプライズされるのも効果的だ。エイドリアン・グランバーグの演出は大味だが許容出来るレベル。パス・ベガにアドリアナ・バラーサ、イヴェット・モンレアルといった脇の面子も悪くない。