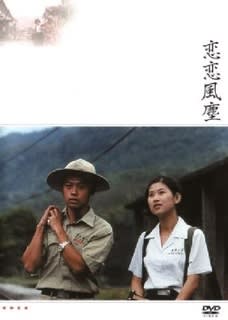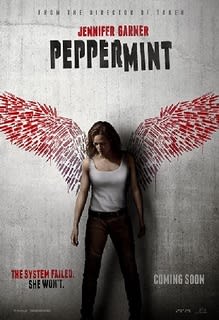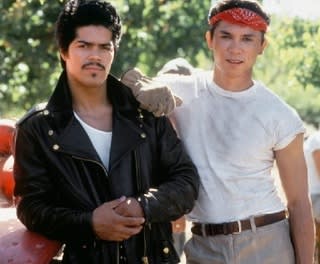(原題:LOVE AND MONSTERS )2021年4月よりNetflixより配信。他愛の無いSFサバイバルスリラーだとは思うが、上手く作ってあり最後まで飽きさせない。また、困難を乗り越えて主人公が成長してゆくというビルドゥングスロマン的な興趣もあり、話が表層的にならないのも好印象。
近未来、地球に衝突しようとした小惑星をミサイルで破壊した際に、有害な化学物質が地上に降り注ぎ、小動物の遺伝子に影響を与えた結果、巨大化したモンスターが大量に出現。そいつらは人間を襲い始め、7年後には人類の大半が死に絶え、運よく生き残った者たちは地下シェルターで生活せざるを得なくなる。その中の一人ジョエルは、無線を通じて恋人のエイミーが別の避難所で生存していることを知る。彼女に会いたい一心で、彼はモンスターが跳梁跋扈する地上に出て、遠く離れた場所にいるエイミーのもとに向かうのだった。
ジョエルは絵に描いたようなヘタレ野郎で、エイミーと離ればなれになって長い時間が経過しているにも関わらず、再会すればまた昔の関係を取り戻せると信じて疑わない。ただ、その一途な思い込みが彼を冒険に駆り立てるのだから、結果オーライである(笑)。道中ではタフなサバイバーたちに出会ったり、犬のボーイ(好演!)と行動を共にしたりと、的確なモチーフが付与される。
そしてもちろん、モンスターたちの襲撃もてんこ盛りだ。こいつらは確かに不気味なのだが、見た目がどこか古い特撮映画のようなテイストが感じられて悪くない。苦難の果てに彼はエイミーと会うことが出来るのだが、それからの展開が切ない。ただ、そんな感傷に浸っているヒマは無く、新たなバトルに身を投じるという筋書きは(定番ながら)申し分ない。
マイケル・マシューズの演出はテンポが良く、ドラマが停滞しない。アクション場面も段取りは万全で、繰り出されるアイデアは非凡だ。また、過去の諸作のネタが挿入されているのも嬉しい。主演のディラン・オブライエンは、一見頼りないがピンチになると力を発揮するという、好ましいキャラクターを上手く演じている。
ヒロインのジェシカ・ヘンウィックが東洋系だったのには少し驚いたが、昨今のアメリカ映画ではよくあるパターンなのだろう。マイケル・ルーカーにダン・ユーイングといった脇の面子も良く機能している。しかしながら、この手の映画は劇場のスクリーンで対峙したいというのが本音。ネット配信だけになったのは残念だ。