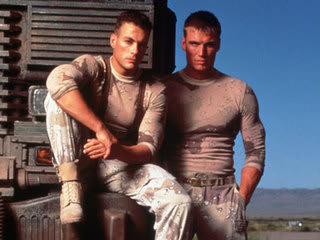この映画の“外観”は、かなり危なっかしい。主人公の若い男女は自己陶酔型のモノローグと意味ありげな仕草を延々と垂れ流す。その芝居がかったワザとらしさに拒否反応を起こす観客も少なくないだろう。映像的なケレンも満載で、まさに独り善がりの駄作に繋がりそうな雰囲気だ。ところが、本作はギリギリのところで踏み止まる。これはひとえに、作者が描きたいテーマをハッキリと捉えていることに尽きる。奇態なエクステリアはあくまでその“小道具”として機能させているに過ぎない。
看護婦の美香は昼間は病院に勤務する傍ら、夜はガールズバーで働く。言葉にできない不安や孤独を抱えているが、周囲の誰とも打ち解けられず、悶々とした日々を送っている。工事現場で日雇いの仕事をしている慎二は、学生時代は成績優秀であったにも関わらず、左目が不自由というハンデを負っていることから能動的な生き方を放棄したように見える。そんな2人が、偶然が重なり何度も会うことになる。
美香は患者の最期に何度も立ち会い、また母親も早く亡くしている。慎二の同僚達は明日が見えない境遇に身を置いており、さらには仲の良かった智之が突然に命を落とすのを目の当たりにする。つまりは2人とも死や絶望と隣り合わせに生きており、何とかそれらに巻き込まれないように心の中に高い壁を作っている。
ところが、そんな似たもの同士の彼らがめぐり逢うと、互いの立ち位置を客観的に見据えることになり、思わぬ“化学反応”を見せる。それは、相手の視点から“外部”を睥睨することであり、初めて自分の存在とこの世界との距離感を認識することである。努力が報われず先の見えない社会において、彼らはどう世の中と折り合いを付けるのか。その過程をポジティヴに描くことにより、尽きせぬ映画的興趣を呼び込む。
本作にはラブシーンは存在せず、それどころか2人は手も握らないのだ。それでいて、この重くたれ込めた世界に立ち向かう“同士”としての熱いパッションが溢れている。原作は最果タヒの同名の詩集で、監督の石井裕也はそこからインスピレーションを得て物語を構築したという。かなりの難事業であったと思われるが、そのチャレンジは意欲的で頼もしい。
慎二に扮する池松壮亮は、今まで一番と思われるパフォーマンスを披露している。美香を演じる石橋静河はぶっきらぼうな演技しかできず、容貌も母親の原田美枝子の若い頃には及ばないが、存在感はある。智之役の松田龍平も同じ二世俳優ながら、最初は大根だったことを考え合わせると、この石橋も期待できるかもしれない。他のキャストでは慎二の先輩に扮した田中哲司が最高だ。食えない中年男を実に楽しそうに演じている。希望を持たせた幕切れも含めて、鑑賞後の印象は良い。