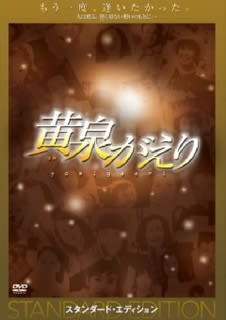題名通り、正面から見ているだけでは分からない、人間の“横顔”を容赦なく暴き立てた快作だ。その手法には幾分強引な部分があるが、作者は力業で押し切っている。キャストの仕事ぶりも万全で、これは本年度の日本映画の収穫だと思う。
訪問看護師の白川市子は、その確かな手腕で顧客からも仕事仲間からも信頼されていた。私生活では医師との結婚も控え、充実した毎日だ。彼女は訪問先の大石家の長女で介護福祉士志望の基子のために勉強まで見てやっていたが、ある日、次女のサキが誘拐されるという事件が起きる。サキは間もなく解放されるが、犯人は市子の甥の辰男だった。その事実がいつの間にか明るみになり、市子は職場を追われて婚約も破棄される。数年後、市子はリサと名を変え、基子の交際相手である美容師の和道に接近する。
結局、他人を正面からしか見ていなかったのは市子だけで、周囲の人間は上辺とは違う“横顔”を持っていたという皮肉。アクシデントによってそのことに気付き、今度は市子自身が巧妙な“横顔”をフィーチャーして“復讐”に乗り出すという、倒錯した構図が面白い。また、基子は市子に対して同性愛的な感情を抱いており、その恋愛ベクトルがほんの少しズレだだけで、どんどん自分が追い込まれてゆくというディレンマの描出も見上げたものだ。
深田晃司監督の前作「淵に立つ」(2016年)は“策に溺れた”という感があって評価出来なかったが、本作はそのニューロティックな演出が冴え渡る。異なる時制を巧みに同時進行させ、登場人物の裏表を容赦なく暴く。インターフォンや横断歩道、そしてラスト近くのクラクションなど、サウンドの扱いが実に効果的だ。
中盤での市子を追いかけるマスコミの扱いには無理があり、市子と婚約者との関係はどうもぎこちないが、そういう瑕疵が気にならなくなるほど、本作の“後ろ向きの”求心力は強烈だ。市子を演じる筒井真理子は、ハッキリ言って凄い。何もかも放り出したような、まさに捨て身の怪演で、彼女が邦画界屈指の実力者であることを強く印象付けた。
基子役の市川実日子、和道に扮した池松壮亮、こちらも目を見張るパフォーマンス。吹越満に大方斐紗子、若手の小川未祐など、脇の面子も良い。根岸憲一のカメラによる清澄でキレの良い映像、小野川浩幸の音楽も効果的だ。