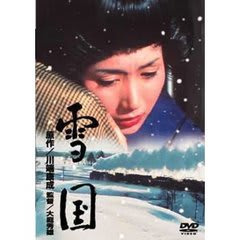(原題:Kis Uykusu)インテリぶったオッサンが、延々とグチをこぼす映画。別にそれ自体がイケナイということではないが、セリフの扱い方には興趣が乏しく、映画として面白味が無い。これで3時間16分も引っ張ってもらっては、観る側にとっては辛いものがある。
トルコの景勝地カッパドキアにあるホテル・オセロを経営する元舞台俳優のアイドゥンは、父の遺産を受け継いで何不自由ない暮らしを送っている。しかも妻は場違いなほど若く、妹は嫁ぎ先から出戻ってはいるが、それによって彼の生活に何か支障が生じるわけでもない。しかし、冬が訪れて観光客は一人また一人と去って行き、次第にホテルが雪に閉ざされていくにつれ、それぞれが胸に秘めていた思いが表面化する。

アイドゥンはなかなか進まないトルコ演劇史の執筆に思い煩い、同時に“自分の人生はこれで良いのか”という気持ちも時折浮かび上がっていく。妻は無為に過ごすことに嫌気がさし、僻地の学校を支援する運動に没頭するようになる。妹は慇懃無礼な兄の態度に何かと難癖を付ける回数が多くなった。一方、アイドゥンから土地と家を借りている一家は借賃を滞納するようになり、家主との関係はギクシャクしている。
主人公の気持ちは分からないでも無い。いくら生活に困っていないといっても、住んでいるところは外界から離れたリゾート地で、一般社会にコミット出来ないという焦りがある。だが、彼一人でホテル業を立ち上げたわけでは無く、演劇界にもさほど大きな実績を残していない。妻や妹にしても然りで、現状に不満があるといっても、それは自分のまいた種によりそういう境遇にいるだけの話であり、そこから抜け出すだけの度量も勇気も無い。そういうことを自覚するためだけに、この長大な上映時間と山のようなセリフが必要なのだったかというと、いささか疑問だ。

ハッキリ言ってしまえば、同様のネタをたとえばウディ・アレンあたりが扱うと、ウィットと笑いと捻りを利かせつつも、1時間半程度に収めてしまうのではないか。道に迷ったインテリおやじの独白よりも、生活に困窮している借家の一家にもっとスポットを当てて描いた方が、ドラマティックな展開になったかもしれない。
監督はトルコの巨匠と言われるヌリ・ビルゲ・ジェイランだが、日本公開は本作が初めて。第67回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞しているが、大きなアワードの受賞作が必ずしも良い映画とは限らないというのは毎度のことだ。
主演のハルク・ビルギナーをはじめメリサ・ソゼン、デメット・アクバァといった顔ぶれは馴染みは無いが、いずれも悪くない演技だ。カッパドキアの景観は見もので、バックに流れるシューベルトのピアノ・ソナタも効果的。しかしながら、映画自体が無駄に冗長なので、あまり積極的に評価はしたくはない。
トルコの景勝地カッパドキアにあるホテル・オセロを経営する元舞台俳優のアイドゥンは、父の遺産を受け継いで何不自由ない暮らしを送っている。しかも妻は場違いなほど若く、妹は嫁ぎ先から出戻ってはいるが、それによって彼の生活に何か支障が生じるわけでもない。しかし、冬が訪れて観光客は一人また一人と去って行き、次第にホテルが雪に閉ざされていくにつれ、それぞれが胸に秘めていた思いが表面化する。

アイドゥンはなかなか進まないトルコ演劇史の執筆に思い煩い、同時に“自分の人生はこれで良いのか”という気持ちも時折浮かび上がっていく。妻は無為に過ごすことに嫌気がさし、僻地の学校を支援する運動に没頭するようになる。妹は慇懃無礼な兄の態度に何かと難癖を付ける回数が多くなった。一方、アイドゥンから土地と家を借りている一家は借賃を滞納するようになり、家主との関係はギクシャクしている。
主人公の気持ちは分からないでも無い。いくら生活に困っていないといっても、住んでいるところは外界から離れたリゾート地で、一般社会にコミット出来ないという焦りがある。だが、彼一人でホテル業を立ち上げたわけでは無く、演劇界にもさほど大きな実績を残していない。妻や妹にしても然りで、現状に不満があるといっても、それは自分のまいた種によりそういう境遇にいるだけの話であり、そこから抜け出すだけの度量も勇気も無い。そういうことを自覚するためだけに、この長大な上映時間と山のようなセリフが必要なのだったかというと、いささか疑問だ。

ハッキリ言ってしまえば、同様のネタをたとえばウディ・アレンあたりが扱うと、ウィットと笑いと捻りを利かせつつも、1時間半程度に収めてしまうのではないか。道に迷ったインテリおやじの独白よりも、生活に困窮している借家の一家にもっとスポットを当てて描いた方が、ドラマティックな展開になったかもしれない。
監督はトルコの巨匠と言われるヌリ・ビルゲ・ジェイランだが、日本公開は本作が初めて。第67回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞しているが、大きなアワードの受賞作が必ずしも良い映画とは限らないというのは毎度のことだ。
主演のハルク・ビルギナーをはじめメリサ・ソゼン、デメット・アクバァといった顔ぶれは馴染みは無いが、いずれも悪くない演技だ。カッパドキアの景観は見もので、バックに流れるシューベルトのピアノ・ソナタも効果的。しかしながら、映画自体が無駄に冗長なので、あまり積極的に評価はしたくはない。