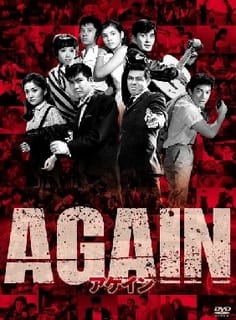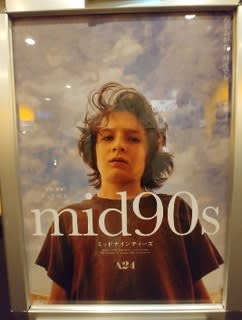(原題:21 BRIDGES)クライムミステリー映画としては標準的な出来で、取り立てて高評価するほどもない作品だが、2020年に若くして世を去ったチャドウィック・ボーズマン主演の最後の劇場公開作となると、勝手が違ってくる。新作で彼の雄姿をスクリーンで拝める機会はもうないのだと思うと、居たたまれない気持ちになってしまう。
ニューヨークのマンハッタン島で、2人組による麻薬強奪事件が発生。駆けつけた警察隊と銃撃戦になり、警官8人が死亡。犯人たちは逃走する。捜査に当たったのは、警察官だった父を殺された過去を持つアンドレ・デイヴィス刑事だった。彼は上層部に、事件が解決するまでのマンハッタンの全面封鎖を提案する。与えられた時間は夜明けまでの数時間だ。麻薬課の女性刑事フランキー・バーンズと共に犯人を追うアンドレは、やがてこの事件の裏には重大な陰謀があることを嗅ぎ付ける。

事件の背後にある“闇の部分”については、序盤の展開を見ていればだいたい予想がつく。そもそも、21か所もある橋をすべて封鎖することが、ドラマの大きなモチーフとなり得ていないのは不満だ(実際には橋は17しかなく、あとの4つはトンネルらしい)。とはいえ、犯人のキャラクターは掘り下げられており、ただのチンピラではないことが示され、ニューヨークの裏社会における資金事情も興味深い。
アンドレは悪に対して異常な敵意を持っており、ならず者を容赦なく始末することに躊躇は無い。その激しい性格のためか中年になっても独身で、認知症の始まった母親と二人暮らしだ。このように各モチーフは十分に肉付けされており、話が通り一遍に進むことはない。
そして何といっても主役のボースマンである。仕事熱心だが、どこか捨て鉢な素振りを見せる一匹狼の刑事をリアリティを持って演じている。撮影当時は体調が万全ではなかったせいか、「ブラックパンサー」(2018年)のような肉体アクションは控えめで活劇のメインは銃撃戦になっているが、それでも存在感は光っている。まったく、惜しい人材を失ったものだ。
フランキー役のシエナ・ミラーをはじめ、ステファン・ジェームズやキース・デイヴィッド、テイラー・キッチュといった顔ぶれも良い。そしてJ・K・シモンズがクセものぶりを発揮しているのも見ものだ。ブライアン・カークの演出は取り立てて才気走ったところはないが、ドラマ運びは堅実だ。なお、主人公が地下鉄の駅で犯人の一人を追う場面は、「フレンチ・コネクション」(71年)を思い出してしまった。
ニューヨークのマンハッタン島で、2人組による麻薬強奪事件が発生。駆けつけた警察隊と銃撃戦になり、警官8人が死亡。犯人たちは逃走する。捜査に当たったのは、警察官だった父を殺された過去を持つアンドレ・デイヴィス刑事だった。彼は上層部に、事件が解決するまでのマンハッタンの全面封鎖を提案する。与えられた時間は夜明けまでの数時間だ。麻薬課の女性刑事フランキー・バーンズと共に犯人を追うアンドレは、やがてこの事件の裏には重大な陰謀があることを嗅ぎ付ける。

事件の背後にある“闇の部分”については、序盤の展開を見ていればだいたい予想がつく。そもそも、21か所もある橋をすべて封鎖することが、ドラマの大きなモチーフとなり得ていないのは不満だ(実際には橋は17しかなく、あとの4つはトンネルらしい)。とはいえ、犯人のキャラクターは掘り下げられており、ただのチンピラではないことが示され、ニューヨークの裏社会における資金事情も興味深い。
アンドレは悪に対して異常な敵意を持っており、ならず者を容赦なく始末することに躊躇は無い。その激しい性格のためか中年になっても独身で、認知症の始まった母親と二人暮らしだ。このように各モチーフは十分に肉付けされており、話が通り一遍に進むことはない。
そして何といっても主役のボースマンである。仕事熱心だが、どこか捨て鉢な素振りを見せる一匹狼の刑事をリアリティを持って演じている。撮影当時は体調が万全ではなかったせいか、「ブラックパンサー」(2018年)のような肉体アクションは控えめで活劇のメインは銃撃戦になっているが、それでも存在感は光っている。まったく、惜しい人材を失ったものだ。
フランキー役のシエナ・ミラーをはじめ、ステファン・ジェームズやキース・デイヴィッド、テイラー・キッチュといった顔ぶれも良い。そしてJ・K・シモンズがクセものぶりを発揮しているのも見ものだ。ブライアン・カークの演出は取り立てて才気走ったところはないが、ドラマ運びは堅実だ。なお、主人公が地下鉄の駅で犯人の一人を追う場面は、「フレンチ・コネクション」(71年)を思い出してしまった。