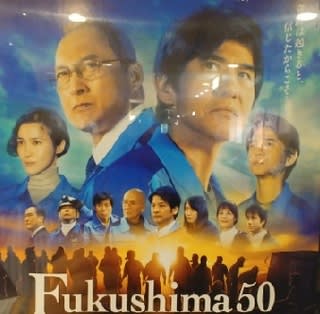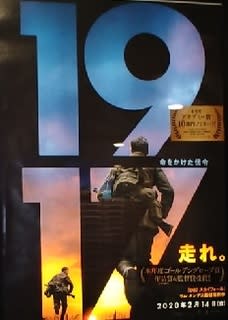(原題:WAVES )二部構成になっているのを知らずに観て、いささか面食らった。結論から言うと、第一部はつまらない。第二部はそれなりに見応えがある。だから前半の内容は適当に端折って(ナレーションや短い回想場面だけで構わない)、後半だけで映画の中身を組み立てた方が数段良かったと思う。
フロリダに住む高校生のタイラーは、工務店を営む父と医者である母、そして優しい妹と、裕福な家庭で何一つ不自由の無い生活を送っていた。学校では成績は優秀でレスリング部のレギュラー選手。何もかも順風満帆に見えた。しかし次第に彼は肩に違和感を覚えるようになる。医者の忠告を無視して強行出場した試合で、タイラーは選手生命を閉ざさせるケガを負う。さらに同じ頃にガールフレンドの妊娠が発覚。捨て鉢になった彼は、取り返しの付かないトラブルを起こす(ここまでが第一部)。
不祥事を起こした兄のため家庭は暗くなり、口数が少なくなった妹のエミリーは、生きる気力を失ったような日々を送っていた。ある日、彼女は兄と同じレスリング部のルークから声を掛けられる。彼はすべての事情を知ってはいたが、それでもエミリーに好意を寄せていた。シャイだがナイスガイのルークと付き合ううち、エミリーは少しずつ前を向き始める。だが、ルークも心に大きな傷を抱えていたのだ。ルークの辛い過去を清算するため、2人は旅に出る。
タイラーは、まったくどうしようもない奴だ。自分がどれだけ恵まれた環境にいるのか理解せず、学業やクラブ活動での名声は全て自分一人の手柄だと思っている。それどころか実の母が亡くなって後妻を迎えた父親を、内心バカにしている。その驕りが肩の故障を軽視し、恋人に対して威圧的な態度を取らせ、結果として人生が早々と詰んでしまう。こんな人間には同情出来ないし、また斯様なキャラクターを映画が延々と追うこと自体、不快感を覚える。
対して、エミリーとルークが主人公になる第二部は、けっこう感慨深い。乗り越えられない過去など無いという、ポジティヴなスタンスには納得だ。ロードムービーの形式を取っているあたりもポイントが高い。ただ、この第二部の中身が第一部の低調ぶりをカバー出来ないばかりか、映画自体のスタイルを不格好にしている。
ケルヴィン・ハリソン・Jrや、ルーカス・ヘッジズ、テイラー・ラッセルといった若手キャストは良くやっているとは思う。ただトレイ・エドワード・シュルツの演出はスタイリッシュではあるが、画面サイズがシークエンスによって変わるのは小賢しくて愉快になれない。ただしテーム・インパラやフランク・オーシャン、ケンドリック・ラマーなどの楽曲を集めたサントラ盤はオススメだろう。