95年作品。映画としての質は評価するに値しないレベルだが、製作された頃の時代の雰囲気とヒロイン役の女優の魅力により、何とか記憶に残っている作品だ。また、印象的なセリフがあり、それだけでも存在価値はあるだろう。監督の利重剛は、なぜか本作で95年度日本映画監督協会新人賞を受賞しているが、これも“時代の空気”のなせる技だと思う。
某放送局の撮影クルーは、風俗業に関するドキュメンタリー番組を制作していた。彼らがネタとして採用したのは、キョーコと名乗るホテトル嬢だ。彼女は風俗店に1年半ほど在籍した後、突如として姿を消した。しかし、彼女を慕う者は意外なほど多い。取材中に撮影班はキョーコが住んでいたアパートに張り込むが、そこに現れたのは鉄夫という青年だった。彼はキョーコと一緒に住んでいたが、数ヶ月前に彼女は出て行ったという。鉄夫もまた、キョーコを忘れられない男の一人だった。何とか彼女を見つけ出そうとする撮影スタッフの奮闘は、いつしか番組制作会社の社長まで巻き込んでいく。
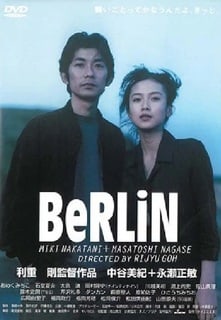
まず、どうして登場人物たちがキョーコを追い求めるのか、さっばり分からない。彼女は“壁”のかけらが入っているという袋をお守りのように首から下げていたというが、それが何らかのメタファーになっているわけでもない。そもそも数多い関係者へのインタビューを経ても、キョーコの具体像が一向に見えてこないのには閉口した。
後半に映し出される鉄夫とキョーコのアバンチュールみたいなくだりも、描き方が弛緩していて退屈極まりない。それに、取材を受ける面子が石堂夏央に大島渚、岡村隆、鴻上尚史、松岡俊介、福岡芳穂など不自然なほど多彩な顔ぶれであり、疑似ドキュメンタリーとしての妙味がスポイルされてしまった。
ただし、このワケのわからない曖昧なものを漫然と追いかけ、そうすることによって何とかなるだろうといった、不確実な楽観性は90年代の雰囲気をよくあらわしている。当時はバブルが崩壊して世の中全体が沈静化していた頃だ。それでも前向きになれる物があるはずだといった、アテにならない願望だけはあった。この映画のキョーコの存在、そしてフワフワとした思わせぶりな映像は、まさにその感覚だ。しかし、しばらくすると儚い期待は打ち破られ、真に衰退に向かって行くことになるのは皮肉なものである。
キョーコに扮した中谷美紀はこの年に映画デビューしており、そのフレッシュな魅力は忘れがたい。ただし永瀬正敏にダンカン、山田辰夫、あめくみちこ、萩原聖人といった他のキャストは精彩を欠く。撮影は篠田昇だが、どうも小綺麗な展開に終始しているようで、訴求力は万全ではない。
某放送局の撮影クルーは、風俗業に関するドキュメンタリー番組を制作していた。彼らがネタとして採用したのは、キョーコと名乗るホテトル嬢だ。彼女は風俗店に1年半ほど在籍した後、突如として姿を消した。しかし、彼女を慕う者は意外なほど多い。取材中に撮影班はキョーコが住んでいたアパートに張り込むが、そこに現れたのは鉄夫という青年だった。彼はキョーコと一緒に住んでいたが、数ヶ月前に彼女は出て行ったという。鉄夫もまた、キョーコを忘れられない男の一人だった。何とか彼女を見つけ出そうとする撮影スタッフの奮闘は、いつしか番組制作会社の社長まで巻き込んでいく。
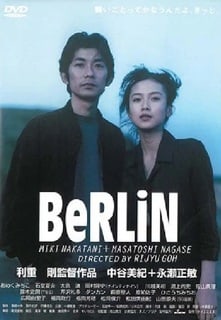
まず、どうして登場人物たちがキョーコを追い求めるのか、さっばり分からない。彼女は“壁”のかけらが入っているという袋をお守りのように首から下げていたというが、それが何らかのメタファーになっているわけでもない。そもそも数多い関係者へのインタビューを経ても、キョーコの具体像が一向に見えてこないのには閉口した。
後半に映し出される鉄夫とキョーコのアバンチュールみたいなくだりも、描き方が弛緩していて退屈極まりない。それに、取材を受ける面子が石堂夏央に大島渚、岡村隆、鴻上尚史、松岡俊介、福岡芳穂など不自然なほど多彩な顔ぶれであり、疑似ドキュメンタリーとしての妙味がスポイルされてしまった。
ただし、このワケのわからない曖昧なものを漫然と追いかけ、そうすることによって何とかなるだろうといった、不確実な楽観性は90年代の雰囲気をよくあらわしている。当時はバブルが崩壊して世の中全体が沈静化していた頃だ。それでも前向きになれる物があるはずだといった、アテにならない願望だけはあった。この映画のキョーコの存在、そしてフワフワとした思わせぶりな映像は、まさにその感覚だ。しかし、しばらくすると儚い期待は打ち破られ、真に衰退に向かって行くことになるのは皮肉なものである。
キョーコに扮した中谷美紀はこの年に映画デビューしており、そのフレッシュな魅力は忘れがたい。ただし永瀬正敏にダンカン、山田辰夫、あめくみちこ、萩原聖人といった他のキャストは精彩を欠く。撮影は篠田昇だが、どうも小綺麗な展開に終始しているようで、訴求力は万全ではない。























