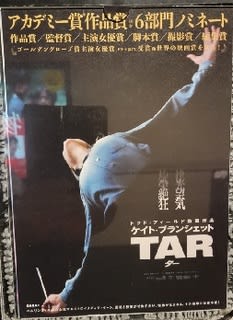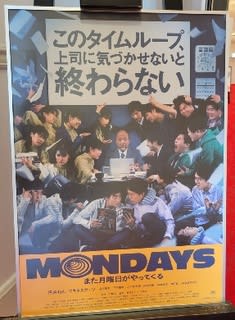ジャズを題材にした石塚真一の同名コミックの映画化だが、当然のことながら原作には“音”が無い。だから映像化に際してはサウンドデザインを一から立ち上げる必要がある。しかもアニメーションでの音楽表現は難しいのではないかと予想して観るのを躊躇していたのだが、評判の良さに敢えて接してみたところ、かなり良く出来ているので感心した。今年度の日本映画の中でも記憶に残る内容だ。
仙台に住んでいた高校生の宮本大はジャズにハマって毎日一人で河原でテナーサックスを吹き続けてきた。卒業した大は上京し、高校の同級生で大学生活を送っている玉田俊二のアパートに転がり込む。何とかミュージシャンとして人前でプレイしたいと思っていた彼は、ある日抜群のテクニックを持つピアニストの沢辺雪祈と出会う。そして意外にリズム感が良かった俊二がドラマーとして加わり、3人でバンド“JASS”を結成。一流ジャズクラブのステージに立つため練習に明け暮れる。

主人公がジャズに魅せられた切っ掛けとか、どのようにスキルを上げていったのかなど、そういう物語の前段になるモチーフはカットされている。それは別に不手際ではなく、作劇のポイントを大の東京での活動に収斂させるための措置なので気にならない。そして何より、演奏シーンが圧倒的だ。
オリジナルのスコアを我が国屈指のピアニストである上原ひろみが担当しているのが実に効果的で、いかにもこのキャラクターたちが奏でそうな闊達なサウンドを提供している。演奏時に故意に画面を歪ませる処理は異論がありそうだが、音楽と見事にシンクロしていて引き込まれる。これならジャズに興味を持たない観客も満足させられるだろう。
サックス担当の馬場智章とドラムの石若駿という気鋭の若手をサウンドトラックに起用しているのも好感触だ。“JASS”の歩みは順調ではないが、スポ根路線よろしく困難を一つ一つ乗り越えていく展開は観ていて気持ちが良い。立川譲の演出は淀みが無く、ストレートな筋書きを正攻法に練り上げている。アニメーションのクォリティも問題は無く、ロトスコービングなどの手法を駆使して飽きさせない。
山田裕貴に間宮祥太朗、岡山天音という主要キャラの声の出演は良好で、木下紗華に青山穣、乃村健次、木内秀信ら声優陣も良い仕事をしている。主人公の“その後”の生き方を暗示させるエピローグが挿入されているが、本作の評価の高さを考えると続編も作られる可能性は大きい。その際はまた劇場に足を運びたいものだ。
仙台に住んでいた高校生の宮本大はジャズにハマって毎日一人で河原でテナーサックスを吹き続けてきた。卒業した大は上京し、高校の同級生で大学生活を送っている玉田俊二のアパートに転がり込む。何とかミュージシャンとして人前でプレイしたいと思っていた彼は、ある日抜群のテクニックを持つピアニストの沢辺雪祈と出会う。そして意外にリズム感が良かった俊二がドラマーとして加わり、3人でバンド“JASS”を結成。一流ジャズクラブのステージに立つため練習に明け暮れる。

主人公がジャズに魅せられた切っ掛けとか、どのようにスキルを上げていったのかなど、そういう物語の前段になるモチーフはカットされている。それは別に不手際ではなく、作劇のポイントを大の東京での活動に収斂させるための措置なので気にならない。そして何より、演奏シーンが圧倒的だ。
オリジナルのスコアを我が国屈指のピアニストである上原ひろみが担当しているのが実に効果的で、いかにもこのキャラクターたちが奏でそうな闊達なサウンドを提供している。演奏時に故意に画面を歪ませる処理は異論がありそうだが、音楽と見事にシンクロしていて引き込まれる。これならジャズに興味を持たない観客も満足させられるだろう。
サックス担当の馬場智章とドラムの石若駿という気鋭の若手をサウンドトラックに起用しているのも好感触だ。“JASS”の歩みは順調ではないが、スポ根路線よろしく困難を一つ一つ乗り越えていく展開は観ていて気持ちが良い。立川譲の演出は淀みが無く、ストレートな筋書きを正攻法に練り上げている。アニメーションのクォリティも問題は無く、ロトスコービングなどの手法を駆使して飽きさせない。
山田裕貴に間宮祥太朗、岡山天音という主要キャラの声の出演は良好で、木下紗華に青山穣、乃村健次、木内秀信ら声優陣も良い仕事をしている。主人公の“その後”の生き方を暗示させるエピローグが挿入されているが、本作の評価の高さを考えると続編も作られる可能性は大きい。その際はまた劇場に足を運びたいものだ。