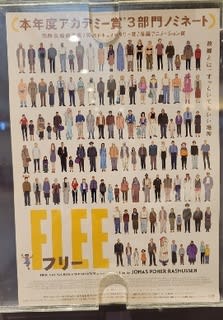(原題:TRE PIANI )面白い部分もあるのだが、全体的にはピンと来ない。有り体に言えば、目的と手法がマッチしているようには思えないのだ。深く描きたいのならば登場人物と劇中経過時間を削るべきだし、群像劇に徹するには段取りが万全ではない。監督ナンニ・モレッティは今回初めて原作ものを手掛けたのだが、その点も影響しているのかもしれない。
ローマの高級住宅地にあるアパートの3階に住むジョバンニとドーラの判事夫婦の息子アンドレアの運転する車が、ある晩近所で死亡事故を起こしてしまう。同じアパートの2階に住む妊娠中の主婦モニカは、ちょうどその時陣痛が始まってしまい、夫が出張中で不在のため一人で病院に向かう。1階に住むルーチョとサラの夫婦は、事情により一晩幼い娘を向かいの老夫婦に預けるが、その老夫は認知症気味で、娘と一緒に行方不明になってしまう。イスラエルの作家エシュコル・ネボによる小説の映画化だ。

とある事件を切っ掛けにして高級アパートに住む人々の悩み多き人生を浮き彫りにしようとしたのだろうが、この仕掛けは上手くいっていない。そもそも、くだんの事故は犠牲者も出ている重大なものだ。よって、ドラマの中心は判事夫婦とそのバカ息子に据えるという筋書き以外は考えられず、他の住民のことは関知する必要は無い。どうしても話を集団劇に誘導したいのならば、交通事故などを導入部に持ってくるべきではない。もっと平易なモチーフを採用した方が良かった。
それでも、個々のエピソードには興味を惹かれる部分はある。特にルーチョの迷走には苦笑してしまった。しかし、映画は各登場人物の戸惑いを無視するかのごとく、勝手に時制を数年単位で進めてしまい、何となく解決したような雰囲気を醸し出そうとしているのだから呆れる。ラストの処理など、御都合主義の最たるものだろう。
モレッティの演出は原作を意識しすぎているのか切れ味に欠け、ここ一番の見せ場が存在しない。それでもマルゲリータ・ブイやリッカルド・スカマルチョ、アルバ・ロルバケル、アドリアーノ・ジャンニーニ、エレナ・リエッティ、アレッサンドロ・スペルドゥーティといったキャストは健闘しているし、ルーチョを翻弄する若い女シャルロットに扮するデニーズ・タントゥッキはすごく可愛い。そういった面では観る価値はあるのだろうが、作品としてはさほど評価出来ない。
ローマの高級住宅地にあるアパートの3階に住むジョバンニとドーラの判事夫婦の息子アンドレアの運転する車が、ある晩近所で死亡事故を起こしてしまう。同じアパートの2階に住む妊娠中の主婦モニカは、ちょうどその時陣痛が始まってしまい、夫が出張中で不在のため一人で病院に向かう。1階に住むルーチョとサラの夫婦は、事情により一晩幼い娘を向かいの老夫婦に預けるが、その老夫は認知症気味で、娘と一緒に行方不明になってしまう。イスラエルの作家エシュコル・ネボによる小説の映画化だ。

とある事件を切っ掛けにして高級アパートに住む人々の悩み多き人生を浮き彫りにしようとしたのだろうが、この仕掛けは上手くいっていない。そもそも、くだんの事故は犠牲者も出ている重大なものだ。よって、ドラマの中心は判事夫婦とそのバカ息子に据えるという筋書き以外は考えられず、他の住民のことは関知する必要は無い。どうしても話を集団劇に誘導したいのならば、交通事故などを導入部に持ってくるべきではない。もっと平易なモチーフを採用した方が良かった。
それでも、個々のエピソードには興味を惹かれる部分はある。特にルーチョの迷走には苦笑してしまった。しかし、映画は各登場人物の戸惑いを無視するかのごとく、勝手に時制を数年単位で進めてしまい、何となく解決したような雰囲気を醸し出そうとしているのだから呆れる。ラストの処理など、御都合主義の最たるものだろう。
モレッティの演出は原作を意識しすぎているのか切れ味に欠け、ここ一番の見せ場が存在しない。それでもマルゲリータ・ブイやリッカルド・スカマルチョ、アルバ・ロルバケル、アドリアーノ・ジャンニーニ、エレナ・リエッティ、アレッサンドロ・スペルドゥーティといったキャストは健闘しているし、ルーチョを翻弄する若い女シャルロットに扮するデニーズ・タントゥッキはすごく可愛い。そういった面では観る価値はあるのだろうが、作品としてはさほど評価出来ない。