雪文様

家の裏の田んぼの雪。今日は雪が降らなかった。用水の流れが雪を斑に融かして、リズミカルな面白い形を造形している。この黒と白の境界が作る線の、柔らかくふくよかな線は、音楽である、と言ってもいい。一日中曇っていて、お正月の村はいつもと変りなく森閑としている。やっぱり雨垂れの音がするのは、これは雪融けのせいで、どうも雨樋が壊れているせいだろう。雪が去って、春の暖かい日和になったら屋根に上って見て見ようか。
これを書いている時間、もう、辺りが薄暗くなってきた。一日の終わりがあまりにも早過ぎはしないだろうか、もう少し「森閑」の余韻を吸っていてもいいと思うが、でも、もう夕暮れの時間が許さないのである。さすがにもう暗くなったから、障子窓を閉めて明かりを灯さなければならない。一日、『 音楽と生活 兼常清佐随筆集 』(杉本秀太郎編 1992年岩波文庫版) を、時間をマダラ(斑)に使用して読んでいた。マダラの間には掃除もし、勿論、昼飯も喰い、そして、もうクラシック曲になった「なごり雪」も聴いたのである。結局、読書時間はそんなにはなかったようであるが … 。
ショパンの『練習曲』の中で私が勝手に “ L'etude domestique ” とよんでいるのがあります。作品第二十五の第七番です。あの左手のふしは若い男、右手のふしは若い女、中の和弦はそれを結ぶ愛の和弦です。曲の中頃のあの大波瀾は正に恋のなやみ、愛のもだえです。そのすぐ後に来る右手のふしのたとえようもない美しさ、綺麗さは実に若き妻のささやきです。そしてピアノはこの二人の曲折ある生涯を描き尽して、最後に愛の和弦で穏かに終りを告げます。誠に美しい、物悲しい、あわれ深い曲です。私はこの曲のふしはみな好きです。
この引用文は『音楽と生活』の中の「愛する」というエッセーの一節で、このエッセーは音楽学者・兼常清佐 (かねつねきよすけ 1885-1957) が1937年に岩波書店から出版した『残響』という本に納められている。それにしても、左と右の手が男と女であるというのは、素敵な感性である。













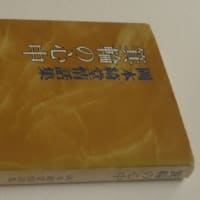

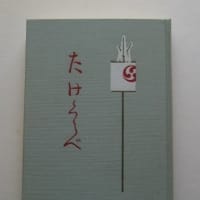




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます