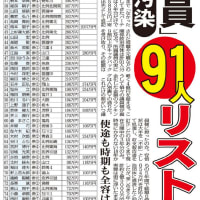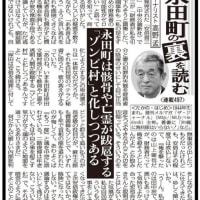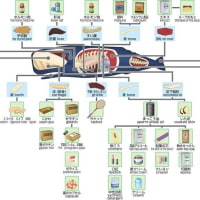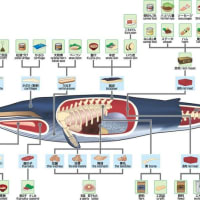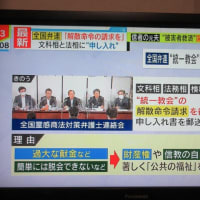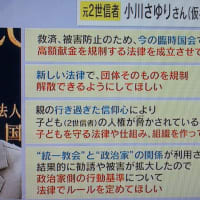8月28日(月): 
250ページ 所要時間3:05 アマゾン550(293+257)円
著者44歳(1967生まれ)。佐賀県生まれ。1990年東京大学法学部卒業。現在、東京大学社会科学研究所教授。専攻は労働法学。
アマゾンの評価4.8の本書がどうしても欲しかった。そして、とにかく目を通しておきたかった。夢かない、無理やり眺め読みをして最後までいった。無数の付箋をしたが、まともに理解できるわけはない。
それでも本書が、非常に優れたテキストであることは十分に分かった。感想4は、俺の読み取り能力の問題であって、本書は評価5のテキストである。素人の読者に対して、これほど「読んでほしい」「わかりやすく伝えたい」という気持ちが伝わってくる岩波新書も珍しい。今後いつでも目のいくところに置いておいて、折に触れて読み直していきたい。
日本の労働法をめぐる歴史や社会的背景から説き起こし、欧米の労働法とのバックボーンの違いなどを懇切に説明しつつ、必ずしも日本の労働法体系が劣っているとは言わない。ただ、せっかく持っている宝を使うことを知らずに、持ち腐れ状態にしているのではないか。もっと労働法を活用していくべきだ。
労働法は生き物であり、どうやって生かすかがすごく大事である。特に「労働組合」の存在は絶対的である。日本では企業内組合が一般的だが、欧米では産業別組合が一般的だ。それぞれ良い点、悪い点がある。その部分をしっかりと押さえて意識することが大事だ。また組合は、たとえ小さいものであっても大きな力になるので、必ずしも大きな組合が良いと考えることはないが、労働組合の存在を抜きにして労働問題について語ることはできない。
・実際の労働の現場では、労働法の教科書に書いてあることとは程遠い、ひどい事件が数多く起きている。略。法と実態の乖離が日本の労働法の大きな特徴となっている。/不条理な事態に直面したときに、泣き寝入りしたのでは自分の権利や新年は守れない。それだけでなく、法と乖離したことを容認することは、会社側に法は守らなくてもよい、さらには、法を守っていては激しい競争に生き残れないという意識を植えつけ、公正な競争の前提自体が損なわれる事態を生む。207ページ
【目次】 第1章 労働法はどのようにして生まれたかー労働法の歴史/第2章 労働法はどのような枠組みからなっているかー労働法の法源/第3章 採用、人事、解雇は会社の自由なのかー雇用関係の展開と法/第4章 労働者の人権はどのようにして守られるのかー労働者の人権と法/第5章 賃金、労働時間、健康はどのようにして守られているのかー労働条件の内容と法/第6章 労働組合はなぜ必要なのかー労使関係をめぐる法/第7章 労働力の取引はなぜ自由に委ねられないのかー労働市場をめぐる法/第8章 「労働者」「使用者」とは誰かー労働関係の多様化・複雑化と法/第9章 労働法はどのようにして守られるのかー労働紛争解決のための法/第10章 労働法はどこへいくのかー労働法の背景にある変化とこれからの改革に向けて
【内容情報】 働くことはどういう意味をもつのか。働くことをめぐってさまざまな問題を抱える労働者に、労働法はどう役立つのか。採用・人事・解雇・賃金・労働時間・雇用差別・労働組合・労働紛争などの基礎知識をはじめ、欧米諸国との比較や近年の新しい動きも満載。労働法の根幹と全体像をやさしく説き明かす、社会人のための入門書。

250ページ 所要時間3:05 アマゾン550(293+257)円
著者44歳(1967生まれ)。佐賀県生まれ。1990年東京大学法学部卒業。現在、東京大学社会科学研究所教授。専攻は労働法学。
アマゾンの評価4.8の本書がどうしても欲しかった。そして、とにかく目を通しておきたかった。夢かない、無理やり眺め読みをして最後までいった。無数の付箋をしたが、まともに理解できるわけはない。
それでも本書が、非常に優れたテキストであることは十分に分かった。感想4は、俺の読み取り能力の問題であって、本書は評価5のテキストである。素人の読者に対して、これほど「読んでほしい」「わかりやすく伝えたい」という気持ちが伝わってくる岩波新書も珍しい。今後いつでも目のいくところに置いておいて、折に触れて読み直していきたい。
日本の労働法をめぐる歴史や社会的背景から説き起こし、欧米の労働法とのバックボーンの違いなどを懇切に説明しつつ、必ずしも日本の労働法体系が劣っているとは言わない。ただ、せっかく持っている宝を使うことを知らずに、持ち腐れ状態にしているのではないか。もっと労働法を活用していくべきだ。
労働法は生き物であり、どうやって生かすかがすごく大事である。特に「労働組合」の存在は絶対的である。日本では企業内組合が一般的だが、欧米では産業別組合が一般的だ。それぞれ良い点、悪い点がある。その部分をしっかりと押さえて意識することが大事だ。また組合は、たとえ小さいものであっても大きな力になるので、必ずしも大きな組合が良いと考えることはないが、労働組合の存在を抜きにして労働問題について語ることはできない。
・実際の労働の現場では、労働法の教科書に書いてあることとは程遠い、ひどい事件が数多く起きている。略。法と実態の乖離が日本の労働法の大きな特徴となっている。/不条理な事態に直面したときに、泣き寝入りしたのでは自分の権利や新年は守れない。それだけでなく、法と乖離したことを容認することは、会社側に法は守らなくてもよい、さらには、法を守っていては激しい競争に生き残れないという意識を植えつけ、公正な競争の前提自体が損なわれる事態を生む。207ページ
【目次】 第1章 労働法はどのようにして生まれたかー労働法の歴史/第2章 労働法はどのような枠組みからなっているかー労働法の法源/第3章 採用、人事、解雇は会社の自由なのかー雇用関係の展開と法/第4章 労働者の人権はどのようにして守られるのかー労働者の人権と法/第5章 賃金、労働時間、健康はどのようにして守られているのかー労働条件の内容と法/第6章 労働組合はなぜ必要なのかー労使関係をめぐる法/第7章 労働力の取引はなぜ自由に委ねられないのかー労働市場をめぐる法/第8章 「労働者」「使用者」とは誰かー労働関係の多様化・複雑化と法/第9章 労働法はどのようにして守られるのかー労働紛争解決のための法/第10章 労働法はどこへいくのかー労働法の背景にある変化とこれからの改革に向けて
【内容情報】 働くことはどういう意味をもつのか。働くことをめぐってさまざまな問題を抱える労働者に、労働法はどう役立つのか。採用・人事・解雇・賃金・労働時間・雇用差別・労働組合・労働紛争などの基礎知識をはじめ、欧米諸国との比較や近年の新しい動きも満載。労働法の根幹と全体像をやさしく説き明かす、社会人のための入門書。