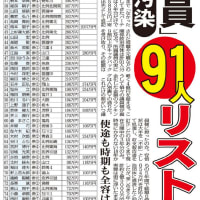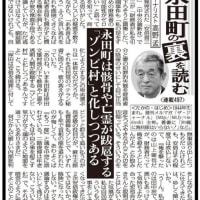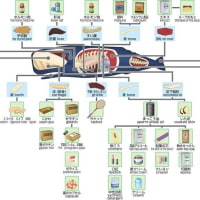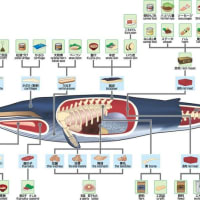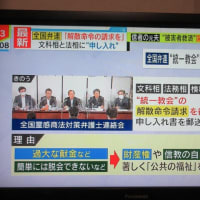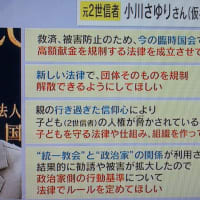8月30日(水): 


202ページ 所要時間6:00 アマゾン260(3+257)円
著者46歳(1946生まれ)。福岡市生まれ。九州大学医学部卒。PMS(ペシャワール会医療サービス)総院長。1984年パキスタンのペシャワールに赴任、現在に至るまでハンセン病を柱に貧困層の診療に当たる。89年からアフガニスタンに活動範囲を広げ、2000年からは大旱魃に対して、井戸1300本を掘ると共に大規模な潅漑用水路も建設中。
1978年、32歳でティリチ・ミール遠征隊参加。道々、病人たちを診ながらキャラバン。1979年、33歳、夫婦でペシャワールからカイバル峠へ。1984年、38歳で家族とともに「らい根絶計画」のため、ペシャワールに着任。1988年、ソ連軍撤退。1989年43歳、アフガニスタンに活動を延長。1991年45歳、湾岸戦争勃発。1992年46歳、怒涛のアフガン難民帰還が本格化。
著者の著作の特徴だが、ただ冷静に事実が書き連ねられ、その時々の思いや感じたことを書いているだけなのだが、著者の価値観、視点がぶれない座標となって記されることによって、かなり踏み込んだ厳しい見方が出てきたりする。ハッとさせられるが、問題は読者の側、日本や欧米的近代社会の視点の側にあるのであって、よく読めば著者の座標は全くぶれていない。そして、改めて「そうだよなあ」と深く教えられることになる。
当初、感想4と思っていたが、理屈を超えた内容や事実の本というのはやっぱりあるのだ。ボランティア活動について、また国連をはじめとする国際社会の援助活動について、わかっていてつもりでいたのが、じつわわかっていなかったことを思い知らされる。著者は騒がずに、静かにひたすら挑戦的医療活動にのめり込んでいく。
本書には著者と、彼を支えるペシャワール会の現地スタッフと日本のスタッフの活動が記されているだけである。風呂敷を広げた大言壮語は一切出てこない。ある意味狭い範囲の実践の記録である。世界のごく一部の記述であるが、「この本の中に人間として必要な知恵のすべてが語られている」と読みながら思った。
読了後、ほとんどすべてのページに貼られた付箋と引いた横線を見ながら、感想5以外は考えられなかった。この本の描かれた約10年後、数百年に一度あるか無いかの大干ばつがアフガニスタンを襲い、著者はさらなる大きな挑戦として用水路開削工事に挑戦していくのだが、本書の内容を見れば、著者ははじめから全くぶれることなく「患者本位」でひたすら挑戦を繰り返していたことがよくわかった。
若き中村医師の活躍を記した本書は、これはこれですごく興味深く読めた。また、後の著作では、当たり前として簡単に記されている著者の考え方、立ち位置、スタンスが本書ではより明瞭に説明し、語られていて大変新鮮で良かった。
本書の内容について、梗概をもう少しきちんと書けたらいいのだが、俺の調子が良くないので書けない。ただ、本書の内容については太鼓判を押します。中村哲医師は、<知の人>ではなく、明確に<情の人>である。<知の人>であれば、結果だけ知れば終わるが、<情の人>の本については、結果がわかっていても、その時々のその人の<情>、どんなことを思い・考えたのかを何度でも読み返すことができる。繰り返すが、本書の感想は5である。これは、今後何度読み返しても感想5であり続けると思う。本書は<情の人>が書いた<真理の書>である。
【目次】 帰郷ーカイバル峠にて/縁ーアフガニスタンとのかかわり/アフガニスタンー闘争の歴史と風土/人びととともにーらい病棟の改善と患者たちとのふれあい/戦乱の中でー「アフガニスタン計画」の発足/希望を求めてーアフガニスタン国内活動へ/平和を力へーダラエ・ヌール診療所/支援の輪の静かな拡大ー協力者たちの苦闘/そして日本は…/あとがき
【内容紹介】*「アフガニスタン」では、貧困、内乱、難民、近代化による伝統社会の破壊、人口・環境問題など、発展途上国の悩みすべてが見られるだけでなく、数千年を凝縮したさまざまな世界がそのまま息づいています。近代化された日本でとうの昔に忘れ去られた人情、自然な相互扶助、古代から変わらぬ風土-歴史の荒波にもまれてきた人々は、てこでも動かぬ保守性や人間相応の分とでもいうべきものを身に付けています。「アフガニスタン」に象徴される発展途上国の実情を紹介し、動乱の中で現地の一般庶民がどう感じ、どう生きてきたか、そこから見える日本と「欧米国際社会」の光景や国際協力のひとつの現実を伝え、私たちの脚下をかえりみます。
*幾度も戦乱の地となり、貧困、内乱、難民、人口・環境問題、宗教対立等に悩むアフガニスタンとパキスタンで、ハンセン病治療に全力を尽くす中村医師。ペシャワールで「らい根絶治療」にたずさわり、難民援助のためにアフガニスタンに診療所を開設、現地スタッフを育成して農村医療・らい治療に力をつくす1人の日本人医師。貧困、政情不安、宗教対立、麻薬、戦争、難民。アジアのすべてが凝縮したこの地で、小さな民間の支援団体がはたす国際協力の真のあり方が見えてくる。



202ページ 所要時間6:00 アマゾン260(3+257)円
著者46歳(1946生まれ)。福岡市生まれ。九州大学医学部卒。PMS(ペシャワール会医療サービス)総院長。1984年パキスタンのペシャワールに赴任、現在に至るまでハンセン病を柱に貧困層の診療に当たる。89年からアフガニスタンに活動範囲を広げ、2000年からは大旱魃に対して、井戸1300本を掘ると共に大規模な潅漑用水路も建設中。
1978年、32歳でティリチ・ミール遠征隊参加。道々、病人たちを診ながらキャラバン。1979年、33歳、夫婦でペシャワールからカイバル峠へ。1984年、38歳で家族とともに「らい根絶計画」のため、ペシャワールに着任。1988年、ソ連軍撤退。1989年43歳、アフガニスタンに活動を延長。1991年45歳、湾岸戦争勃発。1992年46歳、怒涛のアフガン難民帰還が本格化。
著者の著作の特徴だが、ただ冷静に事実が書き連ねられ、その時々の思いや感じたことを書いているだけなのだが、著者の価値観、視点がぶれない座標となって記されることによって、かなり踏み込んだ厳しい見方が出てきたりする。ハッとさせられるが、問題は読者の側、日本や欧米的近代社会の視点の側にあるのであって、よく読めば著者の座標は全くぶれていない。そして、改めて「そうだよなあ」と深く教えられることになる。
当初、感想4と思っていたが、理屈を超えた内容や事実の本というのはやっぱりあるのだ。ボランティア活動について、また国連をはじめとする国際社会の援助活動について、わかっていてつもりでいたのが、じつわわかっていなかったことを思い知らされる。著者は騒がずに、静かにひたすら挑戦的医療活動にのめり込んでいく。
本書には著者と、彼を支えるペシャワール会の現地スタッフと日本のスタッフの活動が記されているだけである。風呂敷を広げた大言壮語は一切出てこない。ある意味狭い範囲の実践の記録である。世界のごく一部の記述であるが、「この本の中に人間として必要な知恵のすべてが語られている」と読みながら思った。
読了後、ほとんどすべてのページに貼られた付箋と引いた横線を見ながら、感想5以外は考えられなかった。この本の描かれた約10年後、数百年に一度あるか無いかの大干ばつがアフガニスタンを襲い、著者はさらなる大きな挑戦として用水路開削工事に挑戦していくのだが、本書の内容を見れば、著者ははじめから全くぶれることなく「患者本位」でひたすら挑戦を繰り返していたことがよくわかった。
若き中村医師の活躍を記した本書は、これはこれですごく興味深く読めた。また、後の著作では、当たり前として簡単に記されている著者の考え方、立ち位置、スタンスが本書ではより明瞭に説明し、語られていて大変新鮮で良かった。
本書の内容について、梗概をもう少しきちんと書けたらいいのだが、俺の調子が良くないので書けない。ただ、本書の内容については太鼓判を押します。中村哲医師は、<知の人>ではなく、明確に<情の人>である。<知の人>であれば、結果だけ知れば終わるが、<情の人>の本については、結果がわかっていても、その時々のその人の<情>、どんなことを思い・考えたのかを何度でも読み返すことができる。繰り返すが、本書の感想は5である。これは、今後何度読み返しても感想5であり続けると思う。本書は<情の人>が書いた<真理の書>である。
【目次】 帰郷ーカイバル峠にて/縁ーアフガニスタンとのかかわり/アフガニスタンー闘争の歴史と風土/人びととともにーらい病棟の改善と患者たちとのふれあい/戦乱の中でー「アフガニスタン計画」の発足/希望を求めてーアフガニスタン国内活動へ/平和を力へーダラエ・ヌール診療所/支援の輪の静かな拡大ー協力者たちの苦闘/そして日本は…/あとがき
【内容紹介】*「アフガニスタン」では、貧困、内乱、難民、近代化による伝統社会の破壊、人口・環境問題など、発展途上国の悩みすべてが見られるだけでなく、数千年を凝縮したさまざまな世界がそのまま息づいています。近代化された日本でとうの昔に忘れ去られた人情、自然な相互扶助、古代から変わらぬ風土-歴史の荒波にもまれてきた人々は、てこでも動かぬ保守性や人間相応の分とでもいうべきものを身に付けています。「アフガニスタン」に象徴される発展途上国の実情を紹介し、動乱の中で現地の一般庶民がどう感じ、どう生きてきたか、そこから見える日本と「欧米国際社会」の光景や国際協力のひとつの現実を伝え、私たちの脚下をかえりみます。
*幾度も戦乱の地となり、貧困、内乱、難民、人口・環境問題、宗教対立等に悩むアフガニスタンとパキスタンで、ハンセン病治療に全力を尽くす中村医師。ペシャワールで「らい根絶治療」にたずさわり、難民援助のためにアフガニスタンに診療所を開設、現地スタッフを育成して農村医療・らい治療に力をつくす1人の日本人医師。貧困、政情不安、宗教対立、麻薬、戦争、難民。アジアのすべてが凝縮したこの地で、小さな民間の支援団体がはたす国際協力の真のあり方が見えてくる。