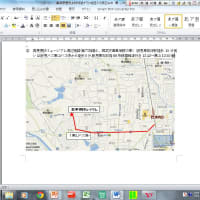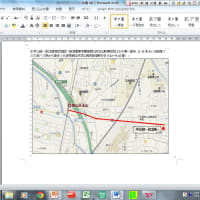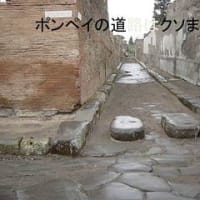東海例会お疲れ様!と思ったらよろしくお願いします。
2月2・3日の二日間に亘って行った考古学研究会東海例会が終わった。

(初めての190番教室でしたが、少し前の方が寒いのが難点でしたがとてもいい感じでした。また使おう!ッと)
延べ130人の参加者が南は宮崎、北は群馬、西は島根からの参加を得て無事終わった。
遠路お出で頂いた皆様、また近隣でも雪の中をお出で頂きました皆様、有り難うございました。特に御報告いただきました10人の先生方には心から御礼申し上げます。

(最前線の研究者の方々にお出で頂きとても緊張しました。学生曰く、「引用文献の先生が並んでる!」(笑)とても充実した二日間でした。学生達もとてもよく動いてくれ、皆さんから高い評価を得ました。こんなことが社会に出てから役に立てばいいですね。)
先に申しましたとおり内容の濃いレジュメ集(A4版160頁)もできあがり、三重に来て10年間、いろいろな場で調査し、暖めて参りました成果をまとめることができたように思います。これも一重にご協力いただきました皆さん方のお陰と心から御礼申し上げます。

(そしてこれがレジュメ集。A4版160頁 送料とも千円 〒514-8507 津市栗真町屋町1577 三重大学人文学部 Tel/Fax 059-231-9148までお申し込み下さいね。)
成果はこれから少しずつ具体化してくるものと思われますが、取り急ぎ当日の報告のご紹介をしておきます。
第1日目2月2日(土)
第1テーマ:「聖武王権と東国行幸」
(1)基調報告 13:10~14:10 榎村寛之(斎宮歴史博物館)「古代行幸論―特に伊勢・志摩地域との関わりから―」
倭姫命伝承の成立過程を当時の天皇行幸観から読み解いた上で、聖武天皇伊勢行幸時にひときわ目立っている河口頓宮での和遅野遊猟の意味について考察した。聖武行幸に関して『続日本紀』には一人の在地有力者の褒賞記事がある。外少初位上一志君埃古麻呂が一挙に外従五位下に昇叙されるのである。この様な地方有力首長層への叙位こそ、行幸の持つもう一つの大きな目的であったというのである。
和遅野遊猟には当然在地の人間でなければ果たし得ない案内が不可欠である。そうした役割を課すことによって、王権との繋がりを実体的に保持させるとすると、日本の王権の持つ特異な性格をこの点でも見出すことができるのかもしれない、と感じた。
(2)研究報告-1 14:15~15:00 天野三恵子(京都大学・院)「聖武伊勢行幸論」
聖武天皇東国行幸の研究史的位置、背景、目的、その本質などについて資料を渉猟して詳細に分析した力作であった。特に独自の視点として、河口頓宮跡の発掘調査を経験した視点から、川口という空間の持つ意味を分析し、河口頓宮宿泊に込める聖武の意図を高く評価した。その結果、聖武の東国行幸が広嗣の乱に驚いて東へ逃避したなどという通説を痛烈に批判し、計画的で、壮大な計画の下に実行された行幸であったと主張した。
榎村氏同様川口における一志君古麻呂への褒賞記事に注目し、在地首長層との関係強化という側面を強調する点は偶然とはいえ共通する。私はこの後の村居報告での伊勢国内における聖武朝の瓦の供給体制のあり方が大変参考になると思っている。即ち、和遅野遊猟だけではなく、考古学的資料で実証できるように、在地の造瓦体制を利用して頓宮の瓦を焼かせている点である(もちろん場合によっては鈴鹿関や川口の関という国家的施設の造営に在地首長層を動員することもあったと思われるが)。予め川口、一志に命令を下し(造伊勢国行宮司。それぞれ(川口関と一志郡が命令対象か)。聖武のために聖武の象徴である重圈文軒丸瓦を焼成させたと考えるのである。こちらの方が考古資料とも重なってより説得力が流と思われるのだがどうだろう。
(3) 研究報告-2 15:15~16:15 山中 章(三重大学)「古代頓宮の基本構造~聖武伊勢行幸頓資料を素材に~」
私の報告はこれまで見つかった伊勢国内の頓宮(推定)跡を整理し、二つのモデルを提示することにあった。第1モデルが関を利用した河口・赤坂頓宮タイプである。第2モデルが傾斜地を利用した朝明頓宮タイプである。もちろん発掘調査されいないその他の頓宮があるはずであるが、今はその一端すら想定できないので、とりあえずこの2タイプのあることを提示した。
2タイプに共通して言えることは衛禁律に規定された厳重な警備体制の必要性である。関には二日目の報告で詳細に論じられたように極めて厳重な防御態勢が敷かれていた。これを利用すれば大した造作もともなわず長期間滞在する施設を確保することは可能である。川口、鈴鹿、不破の滞在期間が東国行幸において長期であることもこれでうなずける。
頓宮の施設配置にも当然のことながら立地による制約があるものの、王の身辺警護は最も重要な課題である。これを容易にするためには伊勢国、美濃国に所在する関を利用すという発想は極めて合理的だと言える。鈴鹿関が発見され、三関の防備体制の強固さが実証された今の時点では、さらにこのことを強く主張することができるのではないかと思う。
(3)調査報告 16:20~17:05 大崎哲人(滋賀県文化財保護協会)「粟津頓宮跡の発掘調査」
膳所城下町遺跡を発掘調査された大崎氏よりその現場の詳細を報告いただいた。特にその後の発掘調査で明らかになった本遺跡の南に展開する関津遺跡の成果はとても興味深かった。聖武行幸を評価するとき忘れてはならないのは行幸ルートである。発見された田原道はそのルートとして意図的に設定された可能性も含めて、検討すべき課題であろう。
以前から気になるのが、次の時期に掘削されたという周りに出現する堀状遺構であるが、出土瓦が時期建物に伴うことが説明されたが、これらはあくまで堀状遺構の廃棄時の資料であって、建設の時期は一般的にも難しい野ではないかと思う。構造的にもこれがあるかないかでは禾津頓宮のイメージも随分異なるので、今少し検討が必要ではないかと思えた。

(会場の先生方からもご意見をいろいろお伺いしたかったのですが、とても時間がありませんでした。ごめんなさい。)
(4)ミニシンポ 17:15~18:15 「文献・考古資料からみた聖武東国行幸」司会山中 章
コメント 山田邦和(同志社女子大学)「聖武・天武両天皇の首都構想」
誌上参加 仁藤智子「聖武天皇行幸論へむけて」
最後に報告者の間で議論するミニシンポを開いた。最初に山田邦和さんから聖武東国行幸の最終目標であった遷都についてコメントを頂いた。山田さんの説は、天武皇統を意識する聖武の当初から目指すのが難波遷都であったという点であった。
ミニシンポは当初から1時間しか取れなかったので無理は承知だったのだが、結果的にももう30分は欲しかった。
討論の主軸として①聖武天皇の東国行幸とはどういう性格のものであったのか、②特に広嗣の乱との関係をどう評価するのか、③頓宮とはどんな構造をしていたのかなどについて議論した。また④山田提案の難波遷都の意味についても若干の討論をした。
いずれも、聖武東国行幸の計画性を主張し、広嗣乱逃亡説など一笑に付された観がある。この点はとても強力なインパクトを与えられた。特にその中でも興味深かったのは、広嗣の乱勃発・収束予想説であった。広嗣を大宰府に追いやった時点である程度の反攻は様相指定いたのではないか、この機に乗じて一気に聖武の政権構想を実現するために行幸を計画していたのではないかというのである。
この点に関しては天野氏が、川口という場所の特殊性も考慮すべきではないかと強調し、川口は平城京からの情報が正確に入りやすい空間であった。だからこの地を予め長期滞在場所として設定していたのだというのである。
頓宮の構造については残念ながら新しい意見をお聞きすることができなかったが、これも今後の課題と言うことであろうか。いずれにしろ、広嗣の乱による逃亡などという誠しやかに語り継がれてきた聖武の東国行幸が、ようやく歴史的に評価されるきっかけを作ることだけはできたのではないかと思った。
そうした意味では、誌上参加に留まった仁藤智子氏から直接的に聖武の伊勢行幸、古代の天皇行幸の持つ意味をおうかがいし、ぐたいてきなこうこしりょうとつきあわせてどう評価できるのかお伺いしたかったが、果たせずとても残念だった。なかなか次の機会と言うこともないので、是非これを本にして世に問えればと思っている。
まだ二日目があるのだが長くなるので一端ここで初日の報告とさせていただきます。二日目の報告はまた明日。乞うご期待!!
なお、資料集を1000円で販売しています是非お買い求め頂きたくお願い申し上げます。
申込先 〒514-8507 津市栗真町屋町1577 三重大学人文学部 Tel/Fax 059-231-9148 考古学研究会事務局 資料集希望としてご送金下さい。送料込みで1000円で販売しています。
なお、同時に刊行されました『久留倍官衙遺跡と朝明郡』も送料込みで1000円で販売いたしております上記三重大学考古学研究室へお申し込み下さい。

(もちろん久留倍遺跡の冊子も忘れないでね。送料共で1000円です。同じく〒514-8507 津市栗真町屋町1577 三重大学人文学部 Tel/Fax 059-231-9148へ)
資料集・冊子共によろしくお願いします/b>
2月2・3日の二日間に亘って行った考古学研究会東海例会が終わった。

(初めての190番教室でしたが、少し前の方が寒いのが難点でしたがとてもいい感じでした。また使おう!ッと)
延べ130人の参加者が南は宮崎、北は群馬、西は島根からの参加を得て無事終わった。
遠路お出で頂いた皆様、また近隣でも雪の中をお出で頂きました皆様、有り難うございました。特に御報告いただきました10人の先生方には心から御礼申し上げます。

(最前線の研究者の方々にお出で頂きとても緊張しました。学生曰く、「引用文献の先生が並んでる!」(笑)とても充実した二日間でした。学生達もとてもよく動いてくれ、皆さんから高い評価を得ました。こんなことが社会に出てから役に立てばいいですね。)
先に申しましたとおり内容の濃いレジュメ集(A4版160頁)もできあがり、三重に来て10年間、いろいろな場で調査し、暖めて参りました成果をまとめることができたように思います。これも一重にご協力いただきました皆さん方のお陰と心から御礼申し上げます。

(そしてこれがレジュメ集。A4版160頁 送料とも千円 〒514-8507 津市栗真町屋町1577 三重大学人文学部 Tel/Fax 059-231-9148までお申し込み下さいね。)
成果はこれから少しずつ具体化してくるものと思われますが、取り急ぎ当日の報告のご紹介をしておきます。
第1日目2月2日(土)
第1テーマ:「聖武王権と東国行幸」
(1)基調報告 13:10~14:10 榎村寛之(斎宮歴史博物館)「古代行幸論―特に伊勢・志摩地域との関わりから―」
倭姫命伝承の成立過程を当時の天皇行幸観から読み解いた上で、聖武天皇伊勢行幸時にひときわ目立っている河口頓宮での和遅野遊猟の意味について考察した。聖武行幸に関して『続日本紀』には一人の在地有力者の褒賞記事がある。外少初位上一志君埃古麻呂が一挙に外従五位下に昇叙されるのである。この様な地方有力首長層への叙位こそ、行幸の持つもう一つの大きな目的であったというのである。
和遅野遊猟には当然在地の人間でなければ果たし得ない案内が不可欠である。そうした役割を課すことによって、王権との繋がりを実体的に保持させるとすると、日本の王権の持つ特異な性格をこの点でも見出すことができるのかもしれない、と感じた。
(2)研究報告-1 14:15~15:00 天野三恵子(京都大学・院)「聖武伊勢行幸論」
聖武天皇東国行幸の研究史的位置、背景、目的、その本質などについて資料を渉猟して詳細に分析した力作であった。特に独自の視点として、河口頓宮跡の発掘調査を経験した視点から、川口という空間の持つ意味を分析し、河口頓宮宿泊に込める聖武の意図を高く評価した。その結果、聖武の東国行幸が広嗣の乱に驚いて東へ逃避したなどという通説を痛烈に批判し、計画的で、壮大な計画の下に実行された行幸であったと主張した。
榎村氏同様川口における一志君古麻呂への褒賞記事に注目し、在地首長層との関係強化という側面を強調する点は偶然とはいえ共通する。私はこの後の村居報告での伊勢国内における聖武朝の瓦の供給体制のあり方が大変参考になると思っている。即ち、和遅野遊猟だけではなく、考古学的資料で実証できるように、在地の造瓦体制を利用して頓宮の瓦を焼かせている点である(もちろん場合によっては鈴鹿関や川口の関という国家的施設の造営に在地首長層を動員することもあったと思われるが)。予め川口、一志に命令を下し(造伊勢国行宮司。それぞれ(川口関と一志郡が命令対象か)。聖武のために聖武の象徴である重圈文軒丸瓦を焼成させたと考えるのである。こちらの方が考古資料とも重なってより説得力が流と思われるのだがどうだろう。
(3) 研究報告-2 15:15~16:15 山中 章(三重大学)「古代頓宮の基本構造~聖武伊勢行幸頓資料を素材に~」
私の報告はこれまで見つかった伊勢国内の頓宮(推定)跡を整理し、二つのモデルを提示することにあった。第1モデルが関を利用した河口・赤坂頓宮タイプである。第2モデルが傾斜地を利用した朝明頓宮タイプである。もちろん発掘調査されいないその他の頓宮があるはずであるが、今はその一端すら想定できないので、とりあえずこの2タイプのあることを提示した。
2タイプに共通して言えることは衛禁律に規定された厳重な警備体制の必要性である。関には二日目の報告で詳細に論じられたように極めて厳重な防御態勢が敷かれていた。これを利用すれば大した造作もともなわず長期間滞在する施設を確保することは可能である。川口、鈴鹿、不破の滞在期間が東国行幸において長期であることもこれでうなずける。
頓宮の施設配置にも当然のことながら立地による制約があるものの、王の身辺警護は最も重要な課題である。これを容易にするためには伊勢国、美濃国に所在する関を利用すという発想は極めて合理的だと言える。鈴鹿関が発見され、三関の防備体制の強固さが実証された今の時点では、さらにこのことを強く主張することができるのではないかと思う。
(3)調査報告 16:20~17:05 大崎哲人(滋賀県文化財保護協会)「粟津頓宮跡の発掘調査」
膳所城下町遺跡を発掘調査された大崎氏よりその現場の詳細を報告いただいた。特にその後の発掘調査で明らかになった本遺跡の南に展開する関津遺跡の成果はとても興味深かった。聖武行幸を評価するとき忘れてはならないのは行幸ルートである。発見された田原道はそのルートとして意図的に設定された可能性も含めて、検討すべき課題であろう。
以前から気になるのが、次の時期に掘削されたという周りに出現する堀状遺構であるが、出土瓦が時期建物に伴うことが説明されたが、これらはあくまで堀状遺構の廃棄時の資料であって、建設の時期は一般的にも難しい野ではないかと思う。構造的にもこれがあるかないかでは禾津頓宮のイメージも随分異なるので、今少し検討が必要ではないかと思えた。

(会場の先生方からもご意見をいろいろお伺いしたかったのですが、とても時間がありませんでした。ごめんなさい。)
(4)ミニシンポ 17:15~18:15 「文献・考古資料からみた聖武東国行幸」司会山中 章
コメント 山田邦和(同志社女子大学)「聖武・天武両天皇の首都構想」
誌上参加 仁藤智子「聖武天皇行幸論へむけて」
最後に報告者の間で議論するミニシンポを開いた。最初に山田邦和さんから聖武東国行幸の最終目標であった遷都についてコメントを頂いた。山田さんの説は、天武皇統を意識する聖武の当初から目指すのが難波遷都であったという点であった。
ミニシンポは当初から1時間しか取れなかったので無理は承知だったのだが、結果的にももう30分は欲しかった。
討論の主軸として①聖武天皇の東国行幸とはどういう性格のものであったのか、②特に広嗣の乱との関係をどう評価するのか、③頓宮とはどんな構造をしていたのかなどについて議論した。また④山田提案の難波遷都の意味についても若干の討論をした。
いずれも、聖武東国行幸の計画性を主張し、広嗣乱逃亡説など一笑に付された観がある。この点はとても強力なインパクトを与えられた。特にその中でも興味深かったのは、広嗣の乱勃発・収束予想説であった。広嗣を大宰府に追いやった時点である程度の反攻は様相指定いたのではないか、この機に乗じて一気に聖武の政権構想を実現するために行幸を計画していたのではないかというのである。
この点に関しては天野氏が、川口という場所の特殊性も考慮すべきではないかと強調し、川口は平城京からの情報が正確に入りやすい空間であった。だからこの地を予め長期滞在場所として設定していたのだというのである。
頓宮の構造については残念ながら新しい意見をお聞きすることができなかったが、これも今後の課題と言うことであろうか。いずれにしろ、広嗣の乱による逃亡などという誠しやかに語り継がれてきた聖武の東国行幸が、ようやく歴史的に評価されるきっかけを作ることだけはできたのではないかと思った。
そうした意味では、誌上参加に留まった仁藤智子氏から直接的に聖武の伊勢行幸、古代の天皇行幸の持つ意味をおうかがいし、ぐたいてきなこうこしりょうとつきあわせてどう評価できるのかお伺いしたかったが、果たせずとても残念だった。なかなか次の機会と言うこともないので、是非これを本にして世に問えればと思っている。
まだ二日目があるのだが長くなるので一端ここで初日の報告とさせていただきます。二日目の報告はまた明日。乞うご期待!!
なお、資料集を1000円で販売しています是非お買い求め頂きたくお願い申し上げます。
申込先 〒514-8507 津市栗真町屋町1577 三重大学人文学部 Tel/Fax 059-231-9148 考古学研究会事務局 資料集希望としてご送金下さい。送料込みで1000円で販売しています。
なお、同時に刊行されました『久留倍官衙遺跡と朝明郡』も送料込みで1000円で販売いたしております上記三重大学考古学研究室へお申し込み下さい。

(もちろん久留倍遺跡の冊子も忘れないでね。送料共で1000円です。同じく〒514-8507 津市栗真町屋町1577 三重大学人文学部 Tel/Fax 059-231-9148へ)
資料集・冊子共によろしくお願いします/b>