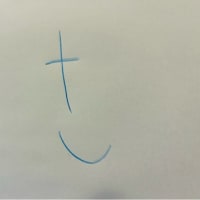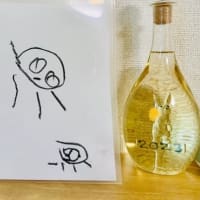後輩の鈴木和正氏から論文「戦前期における「いじめ」問題と教師の対応―「いじめ」問題を語ってこなかった教育史研究」(『子どもの文化』2020年7+8月号、子どもの文化研究所、2020年、148~156頁)が送られてきたのですが、面白かったので紹介します。
鈴木氏は、先般の神戸市立東須磨小の教員間の「いじめ」行為をきっかけに、教員養成に携わる大学教員がどのように「いじめ」問題に向き合ってきたのか、今後どう向き合えるかを考え直す必要があるとして、「いじめ」問題の歴史的研究の可能性を示しています。そして、新潟県高田師範学校附属小学校の『新時代に即せる修身訓練の設営』(1933年)を史料にして、昭和初期の同校尋常第3学年で起きた「いじめ」問題の詳細と、そこに見られる保護者・教師・児童・学級の具体的かかわりについて分析しています。そこから、「「いじめ」に苦しむ被害児童に対して、教師や保護者が日々どのように寄り添い、問題の解決に奔走したのかという歴史的営為」を明らかにし、しかもそれが「児童の「考え」や「議論」を重視した教育実践」であったことを確認しています。鈴木論文は、現代的な課題意識に基づきながらも、史料に即した教育史研究を進め、わかりやすく記述している論考であり、とても興味深く読ませてもらいました。
また、鈴木論文では教育史研究のこれからについても言及しています。これまでの教育史研究が「いじめ」問題に言及してこなかった理由は、史料不足と、学校・教師・教育制度を主な研究対象として「子どもたちの日常生活に潜む複雑な人間関係を歴史的に描きだす」ことをしてこなかったからだと指摘しています。しかし、「いじめ」問題は昭和戦前期にもあったし、学級の「いじめ」について子ども達が考え、議論する実践もありました。戦前の「いじめ」研究が可能なのにもかかわらず、これからも問題に十分向き合っていかない場合、歴史学のように「陰謀論」や「トンデモ説」を生き残らせたり、「特異な凶悪事件」ばかりを強調したりすることにつながってしまうと警鐘を鳴らしています。
鈴木氏は、教職教養としての教育史教育・研究に関する2016年・2019年の拙稿にも言及してくださっています(それで送ってきてくださったのだと思いますが)。私の主張が私より若い世代に響いたということは、ありがたいことです。教育史は実践に無関係な学問ではなく、実践的指導力、そしてその背景にある実践に関する思考力・判断力などの育成に直接・間接に関われる可能性が大いにあります。また、現代的課題に取り組むにも教育史の知識・実践は極めて重要な役割を果たします。鈴木氏は、教育史がその役割を果たすためにも、現代的課題を踏まえた丁寧な研究が必要だと主張されています。私もその通りだと思います。
なお、先行研究のいう通り、今に引き続く問題という意味での「いじめ」問題は、やはり1980年代以降の研究でなければ解けないと思います。とはいえ、1970年代以前の「いじめ」的事実がなかったわけではなく、1980年代以降の「いじめ」問題は1970年代以前の事実に基づいて議論していく必要があるでしょう。そうすることで、「いじめ」問題の歴史性を明らかにすることが可能になります。「いじめ」問題の歴史性の解明は、多様な側面をもつ「いじめ」問題の解決・対処を図るために必要なことだと思われます。そういう意味では鈴木氏の論文は貴重な挑戦です。
1970年代以前、戦前期の「いじめ」的事実を研究するにあたっては、現在の「いじめ」問題研究の概念や方法をそのまま適用することには慎重でなければなりません。そうでないと、戦前期の実践のいたらなさを強調して当事者を断罪したり、実践の意図や背景にあった事情などを無視したりするなど、当事者の名誉毀損につながったり、当時の事実や実践がもっていた教育史的な意義や問題の本質を見失ったりする可能性があります。例えば、現代の「いじめの四層構造」モデルによって戦前期の「いじめ」的事実を分析したところで、研究上それほどの意味があるとは今の私には思えません(もしかしたらあるかもしれませんが)。戦前期の「いじめ」的事象を研究するにあたっては、その方法を慎重に模索する必要があるでしょう。おそらく、基本的な研究姿勢として、史料を尊重して丁寧に解読することや、同時代性への配慮を忘れないようにしなければなりません。そのあたりは鈴木論文はさすがきちんとしています。
それから、歴史の「陰謀論」や「トンデモ説」については、いろいろ思うところがあるのですが、私が解釈するところでは人々の思考法や歴史認識のゆがみを表しているように思います。そのため、これらの論説に向き合うためには、研究者が史料の発見と解釈を積み重ねることも大事なのですが、同時に、「常に教育史の真実を求めようとする思考」を人々が身に付けるような教育史教育が大事なのではないかと思っています。
鈴木氏は、先般の神戸市立東須磨小の教員間の「いじめ」行為をきっかけに、教員養成に携わる大学教員がどのように「いじめ」問題に向き合ってきたのか、今後どう向き合えるかを考え直す必要があるとして、「いじめ」問題の歴史的研究の可能性を示しています。そして、新潟県高田師範学校附属小学校の『新時代に即せる修身訓練の設営』(1933年)を史料にして、昭和初期の同校尋常第3学年で起きた「いじめ」問題の詳細と、そこに見られる保護者・教師・児童・学級の具体的かかわりについて分析しています。そこから、「「いじめ」に苦しむ被害児童に対して、教師や保護者が日々どのように寄り添い、問題の解決に奔走したのかという歴史的営為」を明らかにし、しかもそれが「児童の「考え」や「議論」を重視した教育実践」であったことを確認しています。鈴木論文は、現代的な課題意識に基づきながらも、史料に即した教育史研究を進め、わかりやすく記述している論考であり、とても興味深く読ませてもらいました。
また、鈴木論文では教育史研究のこれからについても言及しています。これまでの教育史研究が「いじめ」問題に言及してこなかった理由は、史料不足と、学校・教師・教育制度を主な研究対象として「子どもたちの日常生活に潜む複雑な人間関係を歴史的に描きだす」ことをしてこなかったからだと指摘しています。しかし、「いじめ」問題は昭和戦前期にもあったし、学級の「いじめ」について子ども達が考え、議論する実践もありました。戦前の「いじめ」研究が可能なのにもかかわらず、これからも問題に十分向き合っていかない場合、歴史学のように「陰謀論」や「トンデモ説」を生き残らせたり、「特異な凶悪事件」ばかりを強調したりすることにつながってしまうと警鐘を鳴らしています。
鈴木氏は、教職教養としての教育史教育・研究に関する2016年・2019年の拙稿にも言及してくださっています(それで送ってきてくださったのだと思いますが)。私の主張が私より若い世代に響いたということは、ありがたいことです。教育史は実践に無関係な学問ではなく、実践的指導力、そしてその背景にある実践に関する思考力・判断力などの育成に直接・間接に関われる可能性が大いにあります。また、現代的課題に取り組むにも教育史の知識・実践は極めて重要な役割を果たします。鈴木氏は、教育史がその役割を果たすためにも、現代的課題を踏まえた丁寧な研究が必要だと主張されています。私もその通りだと思います。
なお、先行研究のいう通り、今に引き続く問題という意味での「いじめ」問題は、やはり1980年代以降の研究でなければ解けないと思います。とはいえ、1970年代以前の「いじめ」的事実がなかったわけではなく、1980年代以降の「いじめ」問題は1970年代以前の事実に基づいて議論していく必要があるでしょう。そうすることで、「いじめ」問題の歴史性を明らかにすることが可能になります。「いじめ」問題の歴史性の解明は、多様な側面をもつ「いじめ」問題の解決・対処を図るために必要なことだと思われます。そういう意味では鈴木氏の論文は貴重な挑戦です。
1970年代以前、戦前期の「いじめ」的事実を研究するにあたっては、現在の「いじめ」問題研究の概念や方法をそのまま適用することには慎重でなければなりません。そうでないと、戦前期の実践のいたらなさを強調して当事者を断罪したり、実践の意図や背景にあった事情などを無視したりするなど、当事者の名誉毀損につながったり、当時の事実や実践がもっていた教育史的な意義や問題の本質を見失ったりする可能性があります。例えば、現代の「いじめの四層構造」モデルによって戦前期の「いじめ」的事実を分析したところで、研究上それほどの意味があるとは今の私には思えません(もしかしたらあるかもしれませんが)。戦前期の「いじめ」的事象を研究するにあたっては、その方法を慎重に模索する必要があるでしょう。おそらく、基本的な研究姿勢として、史料を尊重して丁寧に解読することや、同時代性への配慮を忘れないようにしなければなりません。そのあたりは鈴木論文はさすがきちんとしています。
それから、歴史の「陰謀論」や「トンデモ説」については、いろいろ思うところがあるのですが、私が解釈するところでは人々の思考法や歴史認識のゆがみを表しているように思います。そのため、これらの論説に向き合うためには、研究者が史料の発見と解釈を積み重ねることも大事なのですが、同時に、「常に教育史の真実を求めようとする思考」を人々が身に付けるような教育史教育が大事なのではないかと思っています。