晴れ。段の上に腰を下ろすと熱いほど。
先日切った庭の木の根っこを意味なく掘る。
ミミズを2匹発見。
こんなところにもいるのねといった趣き。
やはり根っこはしっかりしていて。
とてもじゃないが掘り出せない(スコップ1丁のせいもあるが)。
テッド・コッチェフ「ランボー」(’82)を久方ぶりに観る。
本作には「ベトナム帰還兵の哀しみ」と「アメリカの田舎町の狭隘」が。
「コクーン」(’85)では「優しい宇宙人」のブライアン・デネヒーの粗暴さよ。
シリーズで唯一スタローンが泣くシーンがあり。
ベトナム戦争終結から7年後の作品であることも覚えておこう。
原題「first blood」は「最初の血=最初に手を出した」という意味がある模様。
自分の腕を縫うマッチョなシーンはまともに見られず。
ジョージ・P・コストマス「ランボー 怒りの脱出」(’85)を観る。
前作での「騒動」のせいで「強制労働キャンプ」にいるランボーを
リチャード・クレンナのトラウトマン大佐が助けに来るのだが。
その条件はかつてランボーが逃げ出したベトナムの捕虜収容所に行き
戦争捕虜がいるかどうかを確認するための写真を撮ってくること。
ただしそれは議会と世論を納得させるための官僚の「工作」に過ぎず。
捕虜を見つけ出して助けた彼は土壇場で見放されることに。
ジュリア・ニクソンとの束の間の恋が描かれたりもする。
現実の彼女は「刑事スタスキー&ハッチ」のデヴィッド・ソウルと結婚。
本作では「痛みに耐えるマッチョ」は描かれず。
何より撮影がジャック・カーディフだったのに今さら気付いて驚く。
「黒水仙」(’47)「赤い靴」(’48)の色彩の美しさを思い出し。
捕虜収容所の爆破もすさまじく。
スタローンの弟フランクが主題歌を歌っている。
後の「エクスペンダブルズ」のタイトルは本作の「台詞」として登場。
シナリオライターとしてのスタローンの「息の長さ」を感じさせる。
ピーター・マクドナルド「ランボー3 怒りのアフガン」(’88)を観る。
ちなみにソ連のアフガン侵攻は79年から89年まで。
「好ましい存在」として描かれるムジャーヒディンには後にビン・ラディンも参加。
今回はトラウトマン大佐がアフガンでソ連に捕われ彼を助けに行く設定。
なぜか「痛みに耐えるシーン」が復活。
この当時はまだ「世界の警察官」であったアメリカの姿が。
とてもじゃないが現在のトランプを予想できず。
ソ連にとってのアフガンがアメリカにとってのベトナムだという台詞も。
本作の翌年に「冷戦」は終わり。
その後「ランボー 最後の戦場」(’08)「ランボー ラスト・ブラッド」(’19)も。
前者はミャンマーのカレン族、後者はメキシコの人身売買がテーマらしい。
観るかどうかは不明。
「カレン族」については同年のクリント・イ-スウトウッド「グラン・トリノ」より早い。
12年前の「アメリカの話題」だったのかどうかは不明だけれど。
「スタローンの嗅覚」は鋭いと言わざるを得ない。
先日切った庭の木の根っこを意味なく掘る。
ミミズを2匹発見。
こんなところにもいるのねといった趣き。
やはり根っこはしっかりしていて。
とてもじゃないが掘り出せない(スコップ1丁のせいもあるが)。
テッド・コッチェフ「ランボー」(’82)を久方ぶりに観る。
本作には「ベトナム帰還兵の哀しみ」と「アメリカの田舎町の狭隘」が。
「コクーン」(’85)では「優しい宇宙人」のブライアン・デネヒーの粗暴さよ。
シリーズで唯一スタローンが泣くシーンがあり。
ベトナム戦争終結から7年後の作品であることも覚えておこう。
原題「first blood」は「最初の血=最初に手を出した」という意味がある模様。
自分の腕を縫うマッチョなシーンはまともに見られず。
ジョージ・P・コストマス「ランボー 怒りの脱出」(’85)を観る。
前作での「騒動」のせいで「強制労働キャンプ」にいるランボーを
リチャード・クレンナのトラウトマン大佐が助けに来るのだが。
その条件はかつてランボーが逃げ出したベトナムの捕虜収容所に行き
戦争捕虜がいるかどうかを確認するための写真を撮ってくること。
ただしそれは議会と世論を納得させるための官僚の「工作」に過ぎず。
捕虜を見つけ出して助けた彼は土壇場で見放されることに。
ジュリア・ニクソンとの束の間の恋が描かれたりもする。
現実の彼女は「刑事スタスキー&ハッチ」のデヴィッド・ソウルと結婚。
本作では「痛みに耐えるマッチョ」は描かれず。
何より撮影がジャック・カーディフだったのに今さら気付いて驚く。
「黒水仙」(’47)「赤い靴」(’48)の色彩の美しさを思い出し。
捕虜収容所の爆破もすさまじく。
スタローンの弟フランクが主題歌を歌っている。
後の「エクスペンダブルズ」のタイトルは本作の「台詞」として登場。
シナリオライターとしてのスタローンの「息の長さ」を感じさせる。
ピーター・マクドナルド「ランボー3 怒りのアフガン」(’88)を観る。
ちなみにソ連のアフガン侵攻は79年から89年まで。
「好ましい存在」として描かれるムジャーヒディンには後にビン・ラディンも参加。
今回はトラウトマン大佐がアフガンでソ連に捕われ彼を助けに行く設定。
なぜか「痛みに耐えるシーン」が復活。
この当時はまだ「世界の警察官」であったアメリカの姿が。
とてもじゃないが現在のトランプを予想できず。
ソ連にとってのアフガンがアメリカにとってのベトナムだという台詞も。
本作の翌年に「冷戦」は終わり。
その後「ランボー 最後の戦場」(’08)「ランボー ラスト・ブラッド」(’19)も。
前者はミャンマーのカレン族、後者はメキシコの人身売買がテーマらしい。
観るかどうかは不明。
「カレン族」については同年のクリント・イ-スウトウッド「グラン・トリノ」より早い。
12年前の「アメリカの話題」だったのかどうかは不明だけれど。
「スタローンの嗅覚」は鋭いと言わざるを得ない。












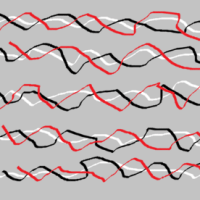


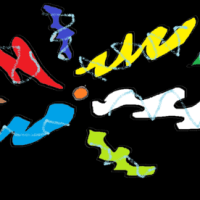
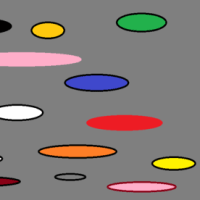
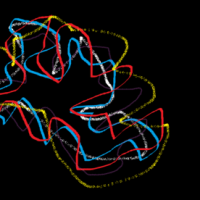
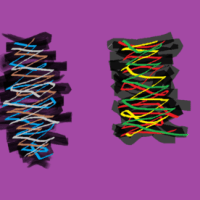







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます