前回記事の秋田県大館市「露天とガーデンの温泉 ほうおう庭」を出た私は、レンタサイクルに跨り大館駅へと戻りました。

駅の観光協会へレンタサイクルを返却後、列車が来るまで腹ごなしをすることに。
大館駅といえば駅弁「鶏めし」がとっても有名であり、私もいままで何度も食べている大好物です。近年になって駅前には綺麗な店舗が建ち、その食堂でイートインも可能なのですが、旅情を楽しむべく敢えて折詰のお弁当を購入することにしました。


大館駅の「鶏めし」って1種類かと思いきや、以前から売られている普通バージョンと、ご当地らしく比内地鶏バージョンの2種類があるんですね。初めて知りました。しかも後者の方がちょっと高い。その名の通り比内地鶏を使っているのでしょう。せっかくなので私は後者を買うことにしました。やっぱり大館の鶏めしは美味い!


さて大館駅から奥羽本線の普通列車秋田行に乗り、次なる目的地である森岳駅で下車しました。当駅は森岳温泉の最寄駅ですから、ホームには温泉旅館の名前が掲示されています。かつてはもっと多くの名前が連なっていたのでしょうけど、いまでは2つの宿と1つの公営入浴施設があるだけ。あまりに寂しい温泉地となってしまいました。


ガランとした森岳駅構内。一応特急が停まり、かつ地域の玄関口としての役割を果たしているからか、日中は駅員さんが勤務し、改札業務のほか出札も行っています。いわゆる委託駅であり、出改札業務を行っているのはおそらく役場関係の方ではないかと思われますが、近隣の駅までの乗車券のみならずJR各線の指定席券も販売しており、実際に指定席券をお願いすると、JRマルス指令に電話で問い合わせた後、手書きの補充券で発券してくれます。機械化が進んで「みどりの窓口」すら減らしている昨今にあって、昔ながらの駅の業務が残っているとても珍しい駅ですね。


駅から今回の目的地である森岳温泉へは3.5kmほど離れており、一応路線バスが運行されているのですが、本数が非常に少ないため、温泉へのアクセスとしてはあまり使えません。このためタクシーに乗るか、宿泊する場合はお宿の送迎車を利用ですることになるかと思います。
この時の私は路線バスに乗り継げず、わざわざ日帰り入浴のためにタクシーを使うのはもったいないという吝嗇な気持ちもあったため、私は温泉まで歩いて向かうことにしました。私が当地を旅したのは2018年の秋。途中には水田が広がり、頭を垂れた稲穂が黄金色に染まっていました。ちょうど稲刈りのシーズンでした。

駅から歩くこと約40分で森岳温泉に到着しました。温泉街というより田舎の集落と表現したくなるような寂しい住宅地の一角、駅から行くと温泉街の最も手前に位置しているのが、今回尋ねた「森岳温泉ホテル」です。後述しますが森岳温泉では旅館の廃業が相次いでおり、現在営業しておるのは2軒だけ。しかも掛け流しのお風呂に入れるのはこちらだけなのです。お宿の外観は瓦屋根でちょっと和風な感じがするのですが、でも基本的には平成的であり、洋風と和風が折衷した帝冠様式の平成版といったようなファサードです。


天井が高くて広いロビーの右手にあるフロントで日帰り入浴したい旨を伝え、湯銭を直接フロントに支払います。お風呂はフロントの奥にあり、脱衣室出入口前に無料のロッカーが設置されています。なおこちらのお宿では日帰り入浴を積極的に受け入れているらしく、回数券も発売されていました。
脱衣室内はエアコンが効いているので、塩辛い森岳温泉の湯でポカポカ火照った体をクールダウンするには良い環境でした。ありがたい配慮です。

お風呂は内湯のみですが、檜をふんだんに使っており、黒い石材と檜の質感がシックで大人な雰囲気を醸し出していました。また天井が高く梁も立派です。

男湯の場合、入って右側に洗い場が配置されています。本来この洗い場にはシャワー付き混合水栓が8個あるはずですが、私の訪問時は真ん中の1つが故障中なので実質7箇所でした。なおシャワーから出てくるお湯は真湯です。


浴場内にはサウナが設けられています。ごく一般的なものですが、このサウナの戸を開けると名古屋の東山動物園で飼育されているフクロテナガザルの鳴き声みたいな「ウォーーッ」という音が室内に響くのです。浴場に入った私は、中で誰かが叫んでいるのかと勘違いしてしまい、ちょっと怖かったのですが、サウナをお客さんが出入りする度にその音が響くので、ようやく合点がいきました。おそらく蝶番の油が切れているのでしょう。
なお浴場内には小さいながら水風呂も設置されています。また水風呂の隣には泡風呂と思しき浴槽も並んでいるのですが、訪問時は空っぽでした。


タイル貼りの主浴槽は結構広く、サイズは計測し忘れてしまいましたが、15人は余裕で入れそうな容量を有しています。そしてサウナが出っ張っていて妙に狭くなっている浴槽の最奥部で、上へ噴き上げるようにして熱い温泉が吐出されており、上で述べた空っぽの浴槽へオーバーフローしています。
森岳温泉の歴史はさほど古くなく、昭和27年に石油を掘削しようとした際に湧出しました。新潟から東北、そして北海道にかけて、日本海沿岸のグリーンタフが広がる一帯では、石油掘削を試みた際に温泉が出てしまったという例が多く、ここもその典型です。
石油掘削の際に湧いたグリーンタフ型温泉は、えてしてお湯に色が付いており、湯の花も多いのですが、森岳温泉はこの手のタイプには珍しく無色透明に近い状態で湯船に張られています。しかもオーバーフローが流れるタイルも着色されていません。また一般的にこの手の温泉はアブラ臭やヨード臭が伴いますが、ここはその手の匂いが比較的弱く、浴室内に籠っているようなこともありませんでした。
このためパッと見は食塩泉だと思えず、単純泉かと勘違いしてしまいそうになったのですが、実際に入浴してみてビックリ。非常に塩辛く海水みたいなのです。無色透明で匂いもあまり漂っていたいのですが、ただひたすら塩辛く、そして苦汁の味もかなり強いのです。透明で匂いが少ないという点は、石油掘削の際に湧いた東北のグリーンタフ型温泉としてはちょっと異色の存在かもしれません。
塩分の濃いお湯ですから湯船では体が浮きます。また傷がピリピリ沁みます。湯口の湯は加水のほか、噴き上げによる自然冷却や投入量を加減することで湯温を適切に維持しています。でも非常に塩辛いお湯ですから体が強烈に火照り、そのあまりに凶暴な性格ゆえ数分で体が音を上げ、ノックダウンしてしまいそうになりました。森岳温泉で長湯は禁物です。上述のサウナルームの上には瓦屋根がかかっているのですが、それがあたかも土俵の屋根に見えてしまい、このお風呂での入浴は相撲のような格闘技ではないかと思いたくなるほど。ここでは誰しもがお湯と真正面から戦うことになるでしょう。
湯中では食塩泉系のツルツル感のほか、引っかかり浴感も少々混在しているように感じられました。なお館内には2つの分析表が掲示されており、平成17年のものには消毒されている旨が記入されていますが、平成27年の分析書には消毒している旨の記載は無く、掛け流しとなっていました。実際の私の体感から申し上げても消毒らしさはあまり感じなかったので、純然たる掛け流しと言って差し支えないでしょう(無論弱いとはいえヨードや臭素臭は感じられましたが、塩素と同じ刺激臭のハロゲン系だから、塩素に気づかなかっただけかもしれません)。
湯上がりはベタつきますので、しっかり上がり湯をかけるか、水風呂でさっぱりした方が良いでしょう。
とにかく塩辛い個性的なお湯です。興味がある方は是非体験なさってみてください。


お風呂上がりに体をクールダウンさせるべく、温泉街を歩いてみました。温泉街というよりも単なる田舎の集落と表現したくなるような街並みですが、旅館よりも小さな飲み屋(スナック)がやけに目立ち、ちょっと異様な光景でもあります。田んぼと山林、そしてゴルフ場以外に何もないこの地域にとって、三業地的な役割を担ってきたのかもしれません。


温泉街の通りは奥に向かって緩やかな上り坂なのですが、その坂を登ってゆくと、左右に廃業したホテルが通りを挟んで対峙していました。いずれもなかなかの規模であり、特に左(上)画像の旅館は収容客数の大きなお宿と推測されますから、そのような宿が相次いでクローズしなければならないほど、この温泉を訪れるお客さんの数は大幅に減少しているのでしょう。

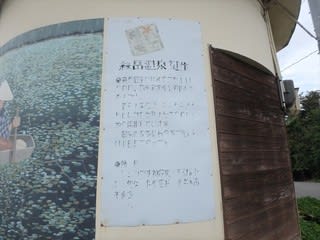
坂を登りきった丁字路の真ん中に円筒形の建物を発見。どうやら温泉の源泉ポンプ小屋のようです。小屋の外壁には上述した森岳温泉の歴史が書かれていました。その説明を読んでいると・・・

下の方からボコボコという音とともに湯気が上がってくるではありませんか。なんとオーバーフロー管よりアブラ臭を放ちながら熱々の温泉が捨てられていた。あぁ勿体ない。

温泉街をひと通り歩いた私は、再び徒歩で森岳駅へ戻り、秋田行の普通列車に乗車。
秋田から新幹線で東京へ戻りました。
これにて昨年から続けてきました2018年秋の東北湯巡りシリーズは終了。
次回からは関東近県の温泉を取り上げます。
森岳温泉1号井戸
ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩温泉 66.2℃ pH7.5 溶存物質23.02g/kg
Na+:5525mg(60.59mval%), Ca++:2974mg(37.42mval%),
Cl-:13790mg(98.28mval%), Br-:41.4mg, I-:1.8mg, S2O3--:0.3mg, SO4--:284.5mg(1.50mval%),
H2SiO3:51.2mg, HBO2:43.9mg, CO2:15.8mg,
(平成18年1月11日)
加水あり、
加温循環消毒なし
秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢115-27
0185-83-5522
ホームページ
日帰り入浴9:00~21:00
450円
ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり
私の好み:★★

駅の観光協会へレンタサイクルを返却後、列車が来るまで腹ごなしをすることに。
大館駅といえば駅弁「鶏めし」がとっても有名であり、私もいままで何度も食べている大好物です。近年になって駅前には綺麗な店舗が建ち、その食堂でイートインも可能なのですが、旅情を楽しむべく敢えて折詰のお弁当を購入することにしました。


大館駅の「鶏めし」って1種類かと思いきや、以前から売られている普通バージョンと、ご当地らしく比内地鶏バージョンの2種類があるんですね。初めて知りました。しかも後者の方がちょっと高い。その名の通り比内地鶏を使っているのでしょう。せっかくなので私は後者を買うことにしました。やっぱり大館の鶏めしは美味い!


さて大館駅から奥羽本線の普通列車秋田行に乗り、次なる目的地である森岳駅で下車しました。当駅は森岳温泉の最寄駅ですから、ホームには温泉旅館の名前が掲示されています。かつてはもっと多くの名前が連なっていたのでしょうけど、いまでは2つの宿と1つの公営入浴施設があるだけ。あまりに寂しい温泉地となってしまいました。


ガランとした森岳駅構内。一応特急が停まり、かつ地域の玄関口としての役割を果たしているからか、日中は駅員さんが勤務し、改札業務のほか出札も行っています。いわゆる委託駅であり、出改札業務を行っているのはおそらく役場関係の方ではないかと思われますが、近隣の駅までの乗車券のみならずJR各線の指定席券も販売しており、実際に指定席券をお願いすると、JRマルス指令に電話で問い合わせた後、手書きの補充券で発券してくれます。機械化が進んで「みどりの窓口」すら減らしている昨今にあって、昔ながらの駅の業務が残っているとても珍しい駅ですね。


駅から今回の目的地である森岳温泉へは3.5kmほど離れており、一応路線バスが運行されているのですが、本数が非常に少ないため、温泉へのアクセスとしてはあまり使えません。このためタクシーに乗るか、宿泊する場合はお宿の送迎車を利用ですることになるかと思います。
この時の私は路線バスに乗り継げず、わざわざ日帰り入浴のためにタクシーを使うのはもったいないという吝嗇な気持ちもあったため、私は温泉まで歩いて向かうことにしました。私が当地を旅したのは2018年の秋。途中には水田が広がり、頭を垂れた稲穂が黄金色に染まっていました。ちょうど稲刈りのシーズンでした。

駅から歩くこと約40分で森岳温泉に到着しました。温泉街というより田舎の集落と表現したくなるような寂しい住宅地の一角、駅から行くと温泉街の最も手前に位置しているのが、今回尋ねた「森岳温泉ホテル」です。後述しますが森岳温泉では旅館の廃業が相次いでおり、現在営業しておるのは2軒だけ。しかも掛け流しのお風呂に入れるのはこちらだけなのです。お宿の外観は瓦屋根でちょっと和風な感じがするのですが、でも基本的には平成的であり、洋風と和風が折衷した帝冠様式の平成版といったようなファサードです。


天井が高くて広いロビーの右手にあるフロントで日帰り入浴したい旨を伝え、湯銭を直接フロントに支払います。お風呂はフロントの奥にあり、脱衣室出入口前に無料のロッカーが設置されています。なおこちらのお宿では日帰り入浴を積極的に受け入れているらしく、回数券も発売されていました。
脱衣室内はエアコンが効いているので、塩辛い森岳温泉の湯でポカポカ火照った体をクールダウンするには良い環境でした。ありがたい配慮です。

お風呂は内湯のみですが、檜をふんだんに使っており、黒い石材と檜の質感がシックで大人な雰囲気を醸し出していました。また天井が高く梁も立派です。

男湯の場合、入って右側に洗い場が配置されています。本来この洗い場にはシャワー付き混合水栓が8個あるはずですが、私の訪問時は真ん中の1つが故障中なので実質7箇所でした。なおシャワーから出てくるお湯は真湯です。


浴場内にはサウナが設けられています。ごく一般的なものですが、このサウナの戸を開けると名古屋の東山動物園で飼育されているフクロテナガザルの鳴き声みたいな「ウォーーッ」という音が室内に響くのです。浴場に入った私は、中で誰かが叫んでいるのかと勘違いしてしまい、ちょっと怖かったのですが、サウナをお客さんが出入りする度にその音が響くので、ようやく合点がいきました。おそらく蝶番の油が切れているのでしょう。
なお浴場内には小さいながら水風呂も設置されています。また水風呂の隣には泡風呂と思しき浴槽も並んでいるのですが、訪問時は空っぽでした。


タイル貼りの主浴槽は結構広く、サイズは計測し忘れてしまいましたが、15人は余裕で入れそうな容量を有しています。そしてサウナが出っ張っていて妙に狭くなっている浴槽の最奥部で、上へ噴き上げるようにして熱い温泉が吐出されており、上で述べた空っぽの浴槽へオーバーフローしています。
森岳温泉の歴史はさほど古くなく、昭和27年に石油を掘削しようとした際に湧出しました。新潟から東北、そして北海道にかけて、日本海沿岸のグリーンタフが広がる一帯では、石油掘削を試みた際に温泉が出てしまったという例が多く、ここもその典型です。
石油掘削の際に湧いたグリーンタフ型温泉は、えてしてお湯に色が付いており、湯の花も多いのですが、森岳温泉はこの手のタイプには珍しく無色透明に近い状態で湯船に張られています。しかもオーバーフローが流れるタイルも着色されていません。また一般的にこの手の温泉はアブラ臭やヨード臭が伴いますが、ここはその手の匂いが比較的弱く、浴室内に籠っているようなこともありませんでした。
このためパッと見は食塩泉だと思えず、単純泉かと勘違いしてしまいそうになったのですが、実際に入浴してみてビックリ。非常に塩辛く海水みたいなのです。無色透明で匂いもあまり漂っていたいのですが、ただひたすら塩辛く、そして苦汁の味もかなり強いのです。透明で匂いが少ないという点は、石油掘削の際に湧いた東北のグリーンタフ型温泉としてはちょっと異色の存在かもしれません。
塩分の濃いお湯ですから湯船では体が浮きます。また傷がピリピリ沁みます。湯口の湯は加水のほか、噴き上げによる自然冷却や投入量を加減することで湯温を適切に維持しています。でも非常に塩辛いお湯ですから体が強烈に火照り、そのあまりに凶暴な性格ゆえ数分で体が音を上げ、ノックダウンしてしまいそうになりました。森岳温泉で長湯は禁物です。上述のサウナルームの上には瓦屋根がかかっているのですが、それがあたかも土俵の屋根に見えてしまい、このお風呂での入浴は相撲のような格闘技ではないかと思いたくなるほど。ここでは誰しもがお湯と真正面から戦うことになるでしょう。
湯中では食塩泉系のツルツル感のほか、引っかかり浴感も少々混在しているように感じられました。なお館内には2つの分析表が掲示されており、平成17年のものには消毒されている旨が記入されていますが、平成27年の分析書には消毒している旨の記載は無く、掛け流しとなっていました。実際の私の体感から申し上げても消毒らしさはあまり感じなかったので、純然たる掛け流しと言って差し支えないでしょう(無論弱いとはいえヨードや臭素臭は感じられましたが、塩素と同じ刺激臭のハロゲン系だから、塩素に気づかなかっただけかもしれません)。
湯上がりはベタつきますので、しっかり上がり湯をかけるか、水風呂でさっぱりした方が良いでしょう。
とにかく塩辛い個性的なお湯です。興味がある方は是非体験なさってみてください。


お風呂上がりに体をクールダウンさせるべく、温泉街を歩いてみました。温泉街というよりも単なる田舎の集落と表現したくなるような街並みですが、旅館よりも小さな飲み屋(スナック)がやけに目立ち、ちょっと異様な光景でもあります。田んぼと山林、そしてゴルフ場以外に何もないこの地域にとって、三業地的な役割を担ってきたのかもしれません。


温泉街の通りは奥に向かって緩やかな上り坂なのですが、その坂を登ってゆくと、左右に廃業したホテルが通りを挟んで対峙していました。いずれもなかなかの規模であり、特に左(上)画像の旅館は収容客数の大きなお宿と推測されますから、そのような宿が相次いでクローズしなければならないほど、この温泉を訪れるお客さんの数は大幅に減少しているのでしょう。

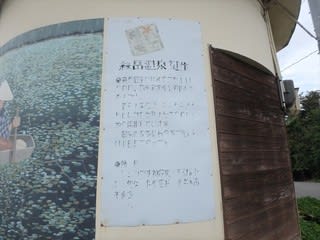
坂を登りきった丁字路の真ん中に円筒形の建物を発見。どうやら温泉の源泉ポンプ小屋のようです。小屋の外壁には上述した森岳温泉の歴史が書かれていました。その説明を読んでいると・・・

下の方からボコボコという音とともに湯気が上がってくるではありませんか。なんとオーバーフロー管よりアブラ臭を放ちながら熱々の温泉が捨てられていた。あぁ勿体ない。

温泉街をひと通り歩いた私は、再び徒歩で森岳駅へ戻り、秋田行の普通列車に乗車。
秋田から新幹線で東京へ戻りました。
これにて昨年から続けてきました2018年秋の東北湯巡りシリーズは終了。
次回からは関東近県の温泉を取り上げます。
森岳温泉1号井戸
ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩温泉 66.2℃ pH7.5 溶存物質23.02g/kg
Na+:5525mg(60.59mval%), Ca++:2974mg(37.42mval%),
Cl-:13790mg(98.28mval%), Br-:41.4mg, I-:1.8mg, S2O3--:0.3mg, SO4--:284.5mg(1.50mval%),
H2SiO3:51.2mg, HBO2:43.9mg, CO2:15.8mg,
(平成18年1月11日)
加水あり、
加温循環消毒なし
秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢115-27
0185-83-5522
ホームページ
日帰り入浴9:00~21:00
450円
ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり
私の好み:★★









































































































