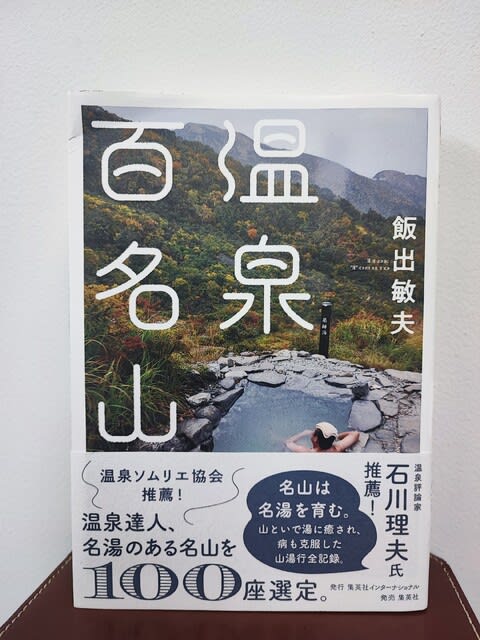久しぶりに鉄道ネタです。しかも思いっきり東京ローカルの話題です。興味のない方、ごめんなさい。
私は幼いころから長年にわたって小田急沿線で育ち、数年前から諸般の事情で京王沿線に移り住んでおります。こんな私にとって新宿はどんな街よりも馴染みがあるターミナルであり、物心ついた頃から今日に至るまで自分の目で新宿の変遷を見つめてまいりました。複雑に入り組んで分かりにく新宿駅構内に対して多くの方は「ダンジョン」や「迷宮」などと呼んでいるそうですが、通い慣れている私は迷ったことなど一度も無く、目を瞑っても構内の目的地まで歩いて行ける自信があります。そんな私にとっても大きな影響がある新宿駅の大変革が先日挙行されました。
●前置き
ニュースでも取り上げられていましたが、今年(2020年)7月19日に新宿駅構内を東西に貫く自由通路が開通しました。これまで新宿駅には東口~西口を自由に行き来できる通路が無かったため、南口の甲州街道を大きく迂回するか、丸ノ内線の駅構内地下通路を回るか、はたまた思い出横丁(いわゆるションベン横丁)の端から線路下を潜る狭くて薄暗いトンネル歩道を抜けるかのいずれかのルートで遠回りせざるを得ませんでした。いや、迂回しなくてもJRの入場券を購入して西口改札と東口改札を直線状に結ぶ構内通路を通過する、つまりお金を払うことで駅構内を通り抜けることもできたのですが、当然ながら入場券を買う必要があるため、わざわざそこまでする人は皆無に等しい状況でした。
長年にわたってこのような遠回りを強いられる構造でしたが、世界で最も利用者数の多い駅なのに、こんな不便な造りではみっともないということなのか、ようやく新宿区とJRは重い腰を上げ、難工事の末に東西自由通路が開通することになったわけです。といっても東西に新しく通路を開削したわけではなく、上述したJRの西口~東口を構内通路から改札を取っ払ってそこを自由通路とし、取っ払った代わりに新たな改札(西改札・東改札)と階段が作ったのでした。

上画像は、東西自由通路が開通する1~2日前に撮影したJR新宿駅西口および東口改札の様子。
それぞれ赤枠で囲んだ内側に写っている改札機が、7月18日の終電を以て撤去されました。

(JR東日本のプレスリリースより抜粋)
往来を阻む関所のような改札を撤去することによって、JRの西口と東口相互間が自由に行き来できるようになり、利便性が格段に向上しました。
以上のことは、いろんなメディアで既に報道されている通りですので、もうこれ以上詳しく述べる必要はないでしょう。
●本題 小田急・京王から中央東口への通り抜けが廃止
さて、ここからが本題。
今回の措置によって新宿駅を利用する多くの方の利便性や街全体の回遊性が向上されたのは間違いないのですが、「ちょっと待った、若干不便になるんじゃねぇの?」と声をかけたくなったのが、我々小田急・京王の両ユーザーなのです。
一般的に、鉄道会社の駅構内に入る際には、その会社の切符を所有していないといけませんね。でも7月18日まで、新宿駅では例外が認められてきました。もう一度、上のJR東日本のプレスリリースから抜粋した図をご覧ください。図の右側の上下(南北)に伸びている薄いブルーの通路が、今回開通した東西自由通路です。一方、左側にも上下(南北)に貫いている通路がありますね。こちらは中央通路と称し、JR構内の中央東口と中央西口を結んでいます。このうち、中央西口側(図の左上)には、小田急・京王からJRへ乗り換える連絡改札が接続しています(図にも「小田急・京王乗継口」と示されています)。連絡改札ですから、小田急・京王~JRの相互間で乗り換える乗客が通過するための改札ですが、この連絡改札では、小田急・京王それぞれの新宿までの乗車券を持っている旅客も、中央東口から出ることを条件に、通過を認められていたのです。
なぜか・・・。
それは小田急・京王ともに西口側に駅のコンコースがあり、東口側との行き来が極めて不便だったからにほかなりません。
この特例措置が、東西自由通路の開通とともに廃止されてしまいました。
話を自由通路開通前に戻らせます。7月19日にオープンした東西自由通路の供用前に、小田急・京王両線の新宿で下車する客が東口方面へ向かおうとすると、小田急も京王も西口側に駅がありますから、甲州街道か、丸ノ内線駅構内地下通路か、あるいはションベン横丁を迂回しなければなりません。これではあまりに不便すぎるということで、中央西口の連絡改札を通過した場合に限り、JR構内の中央通路を経由して、JR中央東口改札へ通り抜けることができたのです。

こちらは7月18日の京王線・中央西口連絡改札を撮ったもの。写真右手に写っているようなJRへの乗り換え専用改札機の他、JR中央東口へ通り抜ける旅客専用の改札機(黄色い自動改札機)が設置されていました。

同じ日の小田急線・中央西口連絡改札。こちらも同様に、JR乗り換え専用改札機の他、JR中央東口へ通り抜ける旅客専用の改札機(黄色い自動改札機)が設置されていました。

中央西口連絡改札を通り過ぎて中央通路を通り抜けてきた小田急・京王の旅客は、JR中央東口改札から出るのがお約束。上画像は7月17日に撮影した同改札です。画像中央に写る黄色い案内表示に「中央東口 小田急線・京王線からのお客様出口」と書かれているのがお分かりになりますでしょうか。当然JR構内では他の改札にも行けますが、新宿までの切符を持っている小田急・京王の旅客はJRの他の改札から出ることはできません。出場できるのは中央東口だけでした。ま、いまだから告白しちゃいますが、私はこの特例を使い、小田急の切符を持ちながら、JR構内の立ち食い蕎麦を食べたり、珍しい列車の入線を見学したりと、いろいろ活用させていただきました。

出場できるのならば、入場だってできました。東口側から小田急・京王の新宿駅を利用したい場合は、中央東口で各社の切符を購入し、中央東口改札を通過して、中央通路を通り、小田急・京王それぞれの中央西口連絡改札を通過して各線の乗り場へ向かうことができました。
上画像は中央東口改札のラッチ外に掲出されていた案内表示(7月17日撮影)。下の方に小さく「小田急線・京王線へのお客様入口」と書かれています。

構内へ入場するためには切符が必要。というわけで、本来JR構内である中央東口改札横には、小田急と京王の券売機も用意されていました。青い券売機が小田急専用、ピンク色の券売機が京王専用です。代々木上原など途中駅から乗客が増える小田急に対し、京王は始発の新宿からいきなり乗客が多いためか、券売機の台数も京王の方が1台多かったようです。とはいえ、中央東口は両社にとって裏口のような存在ですし、そもそも近年はSuica・PASMO利用者が圧倒的ですから、この券売機自体、使用頻度は激減していたものと思われます。

かく言う私も東京圏で切符を買う機会は久しくなかったのですが、たまには切符を手にしてみたくなったので、両社の券売機で購入してみました。ここで切符を買うのは、おそらく20年ぶりかしら・・・。
上画像は中央東口の券売機で買った切符。左側は京王、右側は小田急です。京王の券面は民鉄標準の地紋に京王標準の表記で印字されているごくごく普通の切符なのですが、小田急の方はいろんな面でイレギュラー。まず地紋がJR東日本のものであり、かつ左上に□囲みに東の字が印字されています。フォントも各語句の配置もJR仕様そのもの。つまり、中央東口で販売される小田急の切符は、JRの用紙にJRの機械でJRの仕様に従い発券されるのです。京王についてはよく覚えていませんが、小田急については私が小学生の頃(昭和)から既にこのスタイルでしたから、長年にわたってイレギュラーな切符が発券されつづけてきたのですね。
このように、新宿東口方面に用事がある小田急・京王ユーザーにとって優しい特例措置だった中央東口の通り抜けでしたが、東西自由通路の開通にともない「小田急・京王それぞれの西口改札(メインの改札)を出て、東西自由通路を利用すれば、JR構内を通り抜ける特例措置を廃止しても東口方面へ楽に行けるよね」ということで、7月18日を以てこの特例措置が廃止されてしまいました。

上の図は小田急のプレスリリースを抜粋したものです。図で左側に示されている赤い上下の矢印が、中央東口への通り抜けの動線です。廃止されたことを意味するバッテンがつけられていますね。通り抜けが廃止されるけれども、自由通路が開通するからそちらを通ってね、ということを示しているのが黄色い矢印。今後はこの黄色い矢印の動線に従って行き来することになります。なおこの図は小田急のものですが、京王も同様です。これにより、中央東口はJR専用になり、上述で紹介した案内表示の数々や券売機も使用中止・廃止されてしまいました。
新宿で東口方面に用事がある方は、旧東口から近い伊勢丹方面か歌舞伎町方面が多いので、小田急・京王ユーザーの多くも東西自由通路の開通により利便性が高まったのみならず、特例の廃止により各社の改札業務から「通り抜け」に伴う煩雑さも解消されたわけです。つまり多くの方にとっては歓迎すべき改善策なのですが、しかしながら、中央東口を利用した方が便利な場所も少なからずあるわけで、例えばルミネエストや武蔵野館などは中央東口の方がはるかに便利です。このほかビックロや丸井など、普通は東口から向かうような施設も、実は中央東口から向かった方が若干短い距離で到達できちゃいます。とはいえ、伊勢丹方面や歌舞伎町方面に比べてこれらに向かう人数は圧倒的に少ないでしょうし、そもそも小田急ユーザーならば南口から回っちゃえば良いので、大騒ぎするほどの影響はないのかもしれません。いや、西口の端っこの不便な場所に位置していて小田急やJRのコンコースに行手を遮られている京王線新宿駅ユーザーの中には、今回の特例廃止によって余計に不便になってしまう方もいらっしゃるでしょう。
でも諦めて嘆くのはまだ早い。新宿駅の改良は今回の東西自由通路の開通にとどまらないようです。現在のルミネエスト(東口側)と小田急百貨店(西口側)に高さ260mのツインタワーが建設され、JR駅構内の上を跨ぐ東西通路も設けられる計画もあるようですから、中央東口の通り抜け廃止によって不便になった方も、しばらく我慢すれば事態が好転するかもしれません。首を長くして待ちましょう。でも首を長くしすぎてろくろ首になり、「恨めしやぁ」なんて化けて出ちゃうかも・・・。
●小田急の中央地下連絡窓口(中央西口の出札窓口)も廃止に


さて今回廃止されたのは中央東口への通り抜けだけではありません。小田急中央西口地下連絡改札で続けられてきた精算や連絡切符の販売も廃止されてしまいました。
新宿に限らず、日本全国のJR(古くは国鉄)と民鉄各社の間に設けられた連絡改札では、乗り換え客のために出札窓口で切符が販売されてきました。自動券売機が主流になってからも、精算の必要性があったため、長らく出札窓口で駅員による対面発券が行われてきましたが、IC乗車券の普及により切符の必要性が激減したため、全国的に連絡改札を残しつつ出札窓口を廃止する傾向が強まっています。この新宿中央西口に関しても、京王は既に連絡切符用の出札窓口を廃止しているため、乗り換え先の会社の切符を所有していない場合は、一旦改札を出て、その会社の切符を購入することになります。もっとも先述のようにいまはIC乗車券の利用がほとんどですので、わざわざ切符を買い直す乗客は極めて少数派です(回数券利用者など)。
一方小田急は一見さんの観光客利用が多い路線であるためか、いままで出札窓口を残してきましたが、外国人旅行者ですらICを利用する時代になってきたため、中央東口の通り抜け廃止のタイミングに合わせて出札窓口も廃止することにしたようです。

廃止されてしまうということは、もう二度とここで切符が買えなくなるわけです。そこで窓口が廃止される当日に惜別購入させていただきました。
2つ並んでいるきっぷのうち、右はJRから小田急へ乗り換える手前の出札窓口で購入した、新宿から新百合ヶ丘までの乗車券です。私が子供の頃は5つほどの窓口が開いており、それぞれに長蛇の列ができていました。列に並んで自分の番がくると、出札窓口の駅員さんに新宿までの切符を差し出し、乗り継いで行きたい目的地の駅名を告げると、窓口の職員は秒速で精算金額を計算して切符を発券し、縦に積んである硬貨を指先でトントンと落として、真ん中がちょっと凹んでいる大理石の受け皿の上に、切符とお釣りを一緒にを差し出してくれました。窓口が廃止される当日は窓口が1つしか空いていなかったのですが、それでも利用する客は非常に少なく、全く待つことなく購入することができました。こんなに少なけりゃ廃止したってほとんど影響ないよね・・・。そう思わざるを得ませんでした。
一方、左の切符は小田急構内の窓口で購入した、新宿からJR経由西武新宿線新井薬師前までの切符です。この切符はちょっと変わり種。一般的にここで買える連絡切符はJRだけなのですが、例外的に初乗り区間の乗り継ぎ割引を実施している高田馬場接続西武新宿線の初乗り運賃区間までは、小田急の出札窓口で購入できたのでした。小田急の窓口で発券しているのに、小田急の駅はちっとも通らず、JRどころか西武線の駅に向けているのですから、実に不思議な券です。おそらく小田急で西武線の乗車券を発券しているのはこの窓口だけだったかと思います(定期券や企画券などは除く)。
といっても、実際に私が窓口で「西武線の新井薬師前まで」と告げたところ、窓口の職員さんはちょっと間を置いて「そういえばそんな駅も発券できたっけな」という感じでしたので、ここで西武線の乗車券を購入する客はほとんどいなかったかと思われます。このような変わり種の切符も7月18日を以て過去帳入りしてしまいました。

今回廃止された小田急の出札窓口ではこのようなメッセージが希望者に向けて配布されていました。
私もIC乗車券が普及するまではこの出札窓口に数えきれないほどお世話になりましたので、私からもお礼を申し上げたいと思います。
新宿駅のヘビーユーザーである私にとってはこの一連の措置は歴史的な出来事だったため、非温泉ネタですが記事にさせていただきました。
次回記事から温泉ネタに戻ります。