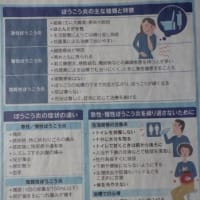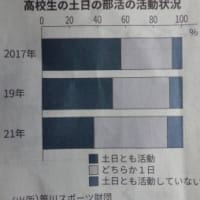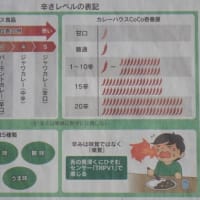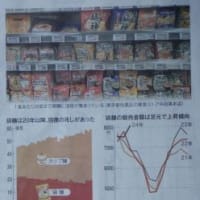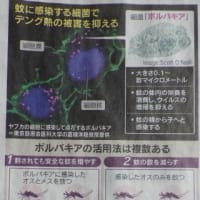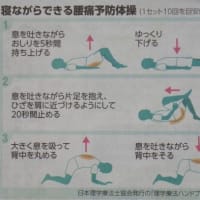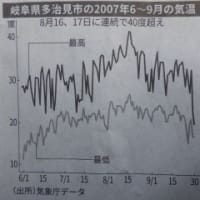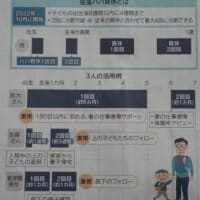動画やポッドキャストなどの人気が高まっている。 登場する人々が話す速度は通常の会話よりバラツキが
あるようで、再生速度も一定の範囲内で調整可能だ。 「聞き心地がいい速度」は変化しているのだろうか。

車やペット、勉強法など、様々なテーマを取り上げて解説する動画がYouTubeなどの動画配信プラッ
トフォームで人気を集めている。 こうした動画の中には人工音声を使って解説しているものも多い。
 人工音声は街中で聞く機会も増えた。音声合成ソフトの開発を手がけ
人工音声は街中で聞く機会も増えた。音声合成ソフトの開発を手がけ
るAHS(東京・台東)の文字読み上げソフトは、イベント会場の案内や
交通案内のアナウンスに使われている。同社の”尾形会長”は「人工音
声は人工知能(AI)などの技術の活用でより人間の話し方に近づいて
おり、使われる場面が広がってきている」と説明している。これらの
人口音声は制作側が聞く相手に合わせて読み上げる速度を調整するこ
とができるのも特徴だ。
人がきちんと理解できる「話す速さ」は一般的にどれくらいなのだろうか。 声の出し方やスピーチのコ
ンサルティングを手がける”林さん”は「1分間に250~300文字程度の速度で話すのが適切とされ
る」と話す。 これはあくまでも一般論で、実は人間が聞き取れる速さの上限はもっと速い。 国立情
報学研究所の”坊農准教授”は「聞き取るだけであれば早口でも処理できる」と指摘する。
林さんが計測したところ、俳優の“黒柳徹子さん”は1分間470文字程度と通常の人よりもかなり速く話
すが、多くの人は内容を理解できる。 AHSの尾形会長は「黒柳さんはよく響く声をしていると同時
に、発音する瞬間高い音と低い音を同時に出しているので聞きやすい。 滑舌もいいことから、早口で
も聞き取れる」と解説。
尾形会長によると、実はもともと人間の脳の処理能力は一般的な人が話すよりも速い言葉を処理できると
いう。 一般的な人が話す速度の1.5倍程度までであれば十分理解できるようだ。 話す内容をあらか
じめ知っていることも上限を高める効果がある。 例えば対談などで事前の打ち合わせで内容を共有し
ていれば、少々早口でも内容を理解できる。 一方、事前情報なしで対談を聞く第三者の脳は、早口で
流れてくる情報を片っ端から処理するのに追われる。
人同士の会話以外では高速化がかなり進んでいる。 人工音声ならば速度を自由に変えられるためで、東
京農工大学大学院の"北原教授"は「視覚障害者向けの読み上げソフトでは、標準の速度は1分間410
文字だが、670文字と速度を上げて聞いている人が多い」と解説する。 同じ時間で多くに内容を聞
ける方がいいという「タイパ志向」にの人が増えているようだ。
なぜ高速再生が普及しているのか。 音は波形で表現され、声の高低を決めるのは波形の幅だ。 幅が狭
いほど時間は短くなるが、同時に音が高くなる。 かつては話す速度を上げようとこの波形の幅を半分
にすると、声が高くなったり、雑音が入ったりしていた。
技術革新が進み、現在は波の幅を狭める以外の方法で高速再生できるようになった。 母音は同じ波形パ
ターンが繰り返されているため、波をいくつか外す余地がある。 この方法だと話す速度は2倍になっ
ても声は高くならない。 このほか、無音区域を削除したり、子音のうち有声音を縮めたりすることで
声が甲高くならずに再生速度を上げることができるようになった。
聞く「高速化」は発信側の意識も変えつつある。 コンサルタントの林さんは「長い目で見ると、ニュー
スなどを読み上げる速度が少しずつ速くなってきた」としてきする。 林さんの調査によると、199
0年ごろのNHKのアナウンサーは1分間に340文字程度の速度でニュースを読み上げていた。 現
在は1分間に380文字程度になっているという。
YouTubeなどのプラットフォームでも多くの情報を短時間で発信できる人が活躍している。 「忙
しい現代の人は、ゆっくり話したり何も話さなかったりするような演出に芸術性を感じなくなったりつ
つある。 筋書だけを知りたい人は演出は不要と考え始めているのではないか」(国立情報学研究所の坊農氏)
もちろん年を取ることで脳の処理速度が落ちれば、早口の情報発信を処理するのは難しくなる。 NHK
は話速変換技術を研究し、主に高齢者向けにゆっくりとした速度でニュースを聞けるサービスを提供し
ている。 速さに慣れると人とゆっくりを選ぶ人。 音声コンテンツは、より個々人が心地よい速度で
楽しむのが主流になっていくのかもしれません。
あるようで、再生速度も一定の範囲内で調整可能だ。 「聞き心地がいい速度」は変化しているのだろうか。

車やペット、勉強法など、様々なテーマを取り上げて解説する動画がYouTubeなどの動画配信プラッ
トフォームで人気を集めている。 こうした動画の中には人工音声を使って解説しているものも多い。
 人工音声は街中で聞く機会も増えた。音声合成ソフトの開発を手がけ
人工音声は街中で聞く機会も増えた。音声合成ソフトの開発を手がけるAHS(東京・台東)の文字読み上げソフトは、イベント会場の案内や
交通案内のアナウンスに使われている。同社の”尾形会長”は「人工音
声は人工知能(AI)などの技術の活用でより人間の話し方に近づいて
おり、使われる場面が広がってきている」と説明している。これらの
人口音声は制作側が聞く相手に合わせて読み上げる速度を調整するこ
とができるのも特徴だ。
人がきちんと理解できる「話す速さ」は一般的にどれくらいなのだろうか。 声の出し方やスピーチのコ
ンサルティングを手がける”林さん”は「1分間に250~300文字程度の速度で話すのが適切とされ
る」と話す。 これはあくまでも一般論で、実は人間が聞き取れる速さの上限はもっと速い。 国立情
報学研究所の”坊農准教授”は「聞き取るだけであれば早口でも処理できる」と指摘する。
林さんが計測したところ、俳優の“黒柳徹子さん”は1分間470文字程度と通常の人よりもかなり速く話
すが、多くの人は内容を理解できる。 AHSの尾形会長は「黒柳さんはよく響く声をしていると同時
に、発音する瞬間高い音と低い音を同時に出しているので聞きやすい。 滑舌もいいことから、早口で
も聞き取れる」と解説。
尾形会長によると、実はもともと人間の脳の処理能力は一般的な人が話すよりも速い言葉を処理できると
いう。 一般的な人が話す速度の1.5倍程度までであれば十分理解できるようだ。 話す内容をあらか
じめ知っていることも上限を高める効果がある。 例えば対談などで事前の打ち合わせで内容を共有し
ていれば、少々早口でも内容を理解できる。 一方、事前情報なしで対談を聞く第三者の脳は、早口で
流れてくる情報を片っ端から処理するのに追われる。
人同士の会話以外では高速化がかなり進んでいる。 人工音声ならば速度を自由に変えられるためで、東
京農工大学大学院の"北原教授"は「視覚障害者向けの読み上げソフトでは、標準の速度は1分間410
文字だが、670文字と速度を上げて聞いている人が多い」と解説する。 同じ時間で多くに内容を聞
ける方がいいという「タイパ志向」にの人が増えているようだ。
なぜ高速再生が普及しているのか。 音は波形で表現され、声の高低を決めるのは波形の幅だ。 幅が狭
いほど時間は短くなるが、同時に音が高くなる。 かつては話す速度を上げようとこの波形の幅を半分
にすると、声が高くなったり、雑音が入ったりしていた。
技術革新が進み、現在は波の幅を狭める以外の方法で高速再生できるようになった。 母音は同じ波形パ
ターンが繰り返されているため、波をいくつか外す余地がある。 この方法だと話す速度は2倍になっ
ても声は高くならない。 このほか、無音区域を削除したり、子音のうち有声音を縮めたりすることで
声が甲高くならずに再生速度を上げることができるようになった。
聞く「高速化」は発信側の意識も変えつつある。 コンサルタントの林さんは「長い目で見ると、ニュー
スなどを読み上げる速度が少しずつ速くなってきた」としてきする。 林さんの調査によると、199
0年ごろのNHKのアナウンサーは1分間に340文字程度の速度でニュースを読み上げていた。 現
在は1分間に380文字程度になっているという。
YouTubeなどのプラットフォームでも多くの情報を短時間で発信できる人が活躍している。 「忙
しい現代の人は、ゆっくり話したり何も話さなかったりするような演出に芸術性を感じなくなったりつ
つある。 筋書だけを知りたい人は演出は不要と考え始めているのではないか」(国立情報学研究所の坊農氏)
もちろん年を取ることで脳の処理速度が落ちれば、早口の情報発信を処理するのは難しくなる。 NHK
は話速変換技術を研究し、主に高齢者向けにゆっくりとした速度でニュースを聞けるサービスを提供し
ている。 速さに慣れると人とゆっくりを選ぶ人。 音声コンテンツは、より個々人が心地よい速度で
楽しむのが主流になっていくのかもしれません。