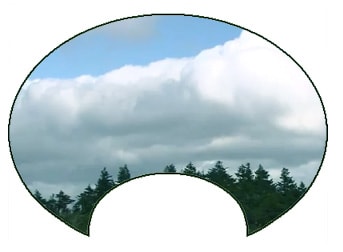「おや? 何だろう」
小さなお社の境内に人集りが出来ている。境内に走り込む人の群れは皆血相を変えている。賢吉は、その叫び声のなかに「仇討ち」という言葉を聞いた。仇討ちなど、生れてこの方見たことがない。恐いもの見たさに、賢吉も野次馬の一人になっていた。
賢吉は、目明しの父親長次に言い付けられて、朝から叔父の家まで使いに行った帰り道である。
「賢吉、この大根を持って帰れ」
百姓の叔父が育てた立派な大根を、五つばかり束ねて差し出した。
「重いから嫌だ」
「この罰当たりめ、重いから嫌だとは何事だ」
「だって、この後回るところがあるのに、大根背負って行けねぇや」
「良家のお坊ちゃんじゃあるめえし、何を軟弱(やわ)なことを言いやがる」
それでも、賢吉は無理やり持たされて、捨てることも出来ずに大根を背負ってお社のところまで帰って来たのだ。
お社の境内は、黒山の人だかりで、賢吉が潜り込もうとしても、弾き出されてしまった。
「こら、子供が見るものじゃない、けぇれ」
賢吉は未練気に人々の背中をみていたが、最初から見ていたらしく、微に入り細に入り説明をしている男が居た。賢吉が聞き耳を立てると、仇討ち側はまだ年端もいかない少年とその姉だそうである。
彼らは、花巻藩士倉掛半平太の倅・倉掛藤太郎と姉・美代と名乗ったそうである。敵は、元花巻藩士、笹川仁左衛門 訳は分からないが、姉弟の父を殺害し、江戸へ逃れてきたらしい。
賢吉は、仇討側がまだ子供だと聞いて心配になり、どうしても見たくなった。辺りを見回すと、少し離れた位置に松の木が植わっている。その木まで駆けていくと、大根を根元に下ろし登っていった。
弟は賢吉より二つ三つ年上だろうか、姉は十七、八のお年頃といったところであった。姉弟揃って純白の装束に白襷と鉢巻きで、手にはキラリと光る刃といった芝居で観る仇討姿そのままである。賢吉の目には、それが不自然に映った。
姉弟は江戸に出てきて敵(かたき)を探し回り、やっとここで出会ったのだと言っていたそうであるが、その割には装束に汚れはなく綺麗過ぎる。
江戸の地で仇討ちをするには、国元の藩で「仇討ち赦免状」を藩主から賜り、それを提示して奉行所で仇討ちの許可をとる。道で出会ったからと言って、無許可で仇討ちをしてもよいというものではないことを、賢吉は、与力の長坂清心に聞いたことがある。
賢吉は暫く見ていたが、一向に勝負が付かなかった。それはそれで良いことなのだが、仇敵は屈強な大男であり、仇討ち側はまだ幼さが残る弟と、きゃしゃな姉である。勝負などたちどころに付きそうなものである。
動きがない訳ではない。弟が斬られそうになると姉が庇い、姉が斬られそうになると弟が庇う。だが、どう見ても仇敵の男に姉弟を斬る意思が全くない様子だ。
「この仇討ち、芝居かも」
そう思って冷静な目で見ると、賢吉にはどうしても本気の仇討ちとは思えない。しかし、賢吉以外の野次馬は違う。視線は仇討ちに釘付けで、手に汗を握って姉弟を見守っている。江戸庶民の判官贔屓というところであろうか。
野次馬の動きを見ていて、賢吉は違和感を覚えた。仇討ちに夢中になっているなか、仇討ちそっちのけで矢鱈に場所を変更している人が何人か居るのだ。
「もしや、掏摸集団?」
その時、野次馬の一人が大声を出した。
「役人が来たぞ!」
一番に仇敵の男が反応した。姉弟を無視して、逃げだしたのだ。
「おのれ、逃がしはしないぞ!」
姉弟は、抜き身の刃先を下げて仇敵を追った。ふと我に返った野次馬の一人が、懐に手を突っ込んで気付いた。
「財布がない、掏摸だ!」
それにつられて、あっちでこっちでも「掏摸だ!」と喚きだした。賢吉は、木から降りると無意識で大根を背負い、姉弟の後を追った。
仇敵(きゅうてき) 笹川仁左衛門の姿は見えないが、賢吉は、倉掛藤太郎と姉美代の姿を捉えた。恐らく、笹川も倉掛姉弟の名も偽名であろう。この三者が行き着くところは同じに違いないと、賢吉は確信した。
姉弟にかなり接近してしまった賢吉は、とうとう気付かれてしまった。
「お姉さん、大根は要りませんか、一本十二文です」
不審がられる前に、賢吉が声を掛けたのだ。
「要りませぬ」
つっけんどんな物言いが、武士の娘であることを明かしている。
「美味しいですよ」
「要らないと言ったら、要らないのです」
「お屋敷まで、お持ちしますから一本如何です」
「諄い、怒りますよ」
「すみません」
断られ乍らも、尚も付いてくる賢吉に、弟が刀を抜いて脅してきた。
「戻れ、我らに付いてくるな」
「俺も、こちらに戻りますので…」
「それなら、もっと離れて歩け」
賢吉は、仕方なく傍らの石積みに腰を掛けて休息する振りをした。先ほどから、賢吉は大根の葉を毟っては道の端に捨てているが、満更断られた腹いせでもなさそうである。
やがて姉弟が、森の木に覆われた荒れ寺に入って行くのを賢吉は見届けた。こっそり忍び込んで様子を窺うと、やはり仇敵笹川と倉掛姉弟は仲間であり、親子のようであった。円く囲んだ人々の真ん中には、巾着や財布が置かれている。
「やはり、掏摸の集団だったか」
賢吉が小さく呟いたとき、何者かに肩を掴まれた。
「おい小僧、何をしておる」
賢吉は驚いて飛び退いたが遅かった。腕を取られて後ろ手に捩じ上げられた。
昼過ぎになって、長次の詰める番屋に、賢吉の弟と妹がやってきた。
「おめえら、どうした?」
「腹が減った、兄ちゃんが帰ってこない」
長次は首を傾げた。
「兄貴のところへ使いにやったが、昼前には帰ってくる筈だ」
「兄ちゃん、何処かへ寄っているのかなぁ」
「兄弟思いの賢吉のことだ、寄り道しているとは思えねえ」
とにかく、子供たちに昼飯を食べさせて賢吉の帰りを待ったが、未の刻(午後一時)頃になっても帰ってこなかった。
「長次親分、俺が探してこようか」
右吉が名乗り出た。
「そうか、では幹太と一緒に兄貴のところまで見に行って貰おうか」
長次の兄の家は、下っ引きの幹太が知っている。二人は出かけて行ったが、しっかり者の賢吉のことだ、叔父に使いを頼まれでもしたのだろうと、さほど心配していなかった。
日の高いうちに賢吉の叔父の家に着いたが、賢吉は大根を担いでとうに帰ったと知らされた。
「帰り道、何か事件に出会わせたのだろうか」
薄暮れ刻、お社の境内でなにやら文句を言いながら掃除をしている神主が居た。右吉は目明しであることを告げて憤っている神主に訳を尋ねた。
「昼間、ここで仇討ち騒動があってのう」
断りもなく境内を荒らされたうえに、返り討ちにでも遭ったのか詫びにも来ないのだという。
「その騒動のとき、大根を担いだ子供を見かけませんでしたか?」
神主は、即答した。
「居ましたわい、人垣が多くて見えないので、罰当たりめ境内の木に登って見物しておった」
賢吉に相違ない。
「結局、ここでは勝負が付かずに、敵の男は逃げだし、討つ側の姉弟が敵を追いかけた」
「その後、子供はどうしました?」
「そのうち、あっちでもこっちでも掏摸だと叫ぶ者が居て、その子は何を思ったか大根を担ぐと後を追って行った」
「逃げたのは、どの方向でしたか?」
神主は、黙って箒の柄で行った先を指した。右吉と幹太は、神主の手を止めた詫びを言って駆けて行った。
「賢吉は、この仇討ちを掏摸集団が企んだものだと勘付いて、後を追ったようだ」
「深入りしていなければよいのに」
幹太は、心配になってきた。
二人走って行くと、道端に千切れた大根の葉が落ちているのに気付いた。
「賢吉だ、賢吉が我らに教える為に大根の葉を落として行ったのだ」
だが、やがて日がとっぷりと落ちてしまった。今宵は月も出ぬようである。
「どこかで、提灯を借りよう」
更に進むと、森の木々の間から灯りが見えた。右吉と幹太が、灯りを目指して森に入ろうとした時、幹太が何かに躓いて転びそうになった。
「右吉親分、足元に大根が…」
「そうか、あの荒ら家に賢吉が掴まっているらしい」
近付いて荒ら家の中を覗いてみると、大勢で酒盛りをしている。賢吉はと見ると、隅の柱に縛り付けられて居眠りをしている。
「泣いているかと思えば、賢吉のヤツ船を漕いでいやがる」
「さすが長次親分の息子だ、肝が据わっていますね」
さて、踏み込もうにも多勢に無勢である。しかも、刀を持った武士も居る。右吉は、刀を持っていない。右吉は何を思ったか、懐の十手を幹太に渡した。
「幹太は、その辺に隠れて待っていてくれ」と、単身で荒ら家の中へ入っていった。
「旅の途中で日が暮れてしまいました」
酒に酔った浪人風の男が、腰に刀をぶっ込んで出てきた。
「提灯をお借りしたいと思いまして…」
聞き慣れた声に、賢吉が目を覚ました。
「嘘をつけ、旅支度はしておらんじゃないか、お前目明しだろう」
男は、いきなり右吉の懐に手を突っ込んだ。十手を隠し持っているのではないかと疑っているようだ」
「いえ、武家の下働きでございます」
男は、右吉の懐から巾着を掴み出して紐を解いた。
「チッ、しけてやがる、たったこれだけかい」
男が巾着の中を覗いたとき、右吉は素早く男の刀を抜き取った。刀が手に入れば酔った男の十人や二十人など右吉の敵ではない。縛られた賢吉のところに走り寄ると、縄を切った。
「賢吉、表で幹太が待っている、呼んで来い」
右吉は叫ぶと、刀の峰を返して構えた。
「刀を隠し持っているところをみると、貴様たちはただの掏摸集団ではなかろう、拙者が退治してやる」
右吉は、刀を手にすると武士に戻る。そのとき、右吉の後ろで男の声がした。
「刀を捨てろ! 捨てぬと、このガキの命はないぞ!」
幹太を呼びに行った筈の賢吉が、男に羽交い絞めされて首に匕首を押し当てられている。賢吉が、少し暴れでもしたら、刃が喉笛を引き裂く。右吉はあっさりと降参して、黙って刀を自分の足元へ投げ捨てた。男は、賢吉を羽交い絞めにしたまま右吉の傍まで摺り足で近寄り、右吉が捨てた刀を蹴り離した。
蹴った瞬間、男の持った匕首が賢吉の首から少し離れたのを右吉は見逃さなかった。男の匕首を持つ手首を、掌底でしたたかに打ち据えた。
「あっ!」
男は、思わず匕首を落とした。賢吉は、そのまま逃げるかと思えば、男の方に向き直って、男の下腹を力任せに蹴り上げた。その間に右吉は刀を拾うと、男が蹲るのを確かめ、賢吉に「行け!」と目で合図をした。
賢吉は幹太を呼びに走ろうとしたが、幹太は騒ぎを聞きつけて荒ら家に入ってきたところだった。
「賢吉、大丈夫か、首に血が滲んでいるぞ」
「大丈夫です、親分が助けてくれました」
右吉に対していた男が、また一人ドタンと倒された。
「幹太、倒れているヤツ等を縛れ! その隅に荒縄がたくさん有る」
「よしきた」
幹太に手伝って、賢吉も倒れている男たちの手足を縛った。
最後に三人残った。右吉はこの集団の頭目と思しき浪人に向かって刀を中段に構えている。賢吉と幹太が見ていて、右吉が苦戦をしいられているのが分かる。浪人が相当の腕を持った手練れなのだ。
右吉は、対している浪人に打ち込む隙がなく、手古摺っている。賢吉は、右吉に助勢する術もなく、焦りが出てきたとき、浪人に隙が出来た。
「娘に、手をだすな!」
浪人の視線の先を見れば、幹太が娘を縛ろうとしている。その浪人の声を聞いて、弟らしい少年が幹太の背中に刀を振り下ろそうとしている。
「危ない!」
賢吉は、咄嗟に懐の巾着を取り出すと、少年の顔をめがけて投げつけた。
賢吉が投げた巾着が、刀を振り下ろそうとした少年の目に当たった。
「あっ!」
少年の驚きの声に幹太が気付き、振り返った。少年が気を取り戻して再び振り下ろそうとした刀を、幹太の十手が受け止めた。その隙に、娘は幹太の手から逃れて、少年を促して闇に消えた。
右吉に対していた集団の頭目らしい浪人が、奇声を発しながら打ち込んできた。右吉は辛うじて峰で受け止め、力任せに押し返した。
右吉は再び中段に構えたが、ここでゆっくりと峰に返していた刀を戻した。刀の峰では互角に戦えぬと判断したのだ。
このとき、闇の中に隠れていた少年が、浪人に加勢するために走り出た。
「父上!」
それが、却って浪人に隙を与えてしまった。隙を衝いて右吉の刀が浪人の脇腹に入った。心配顔で父親を見る少年に、右吉が言い放った。
「安心致せ、峰打ちだ」
右吉の僅かな余裕が、瞬時に刃を返していたのだ。幹太が息子を捉えて縛り上げる間に、右吉は呻いている父親を縛り上げた。
「今夜は寝ずの番だ」
右吉が、つぶやいた。姉が逃げている。隙を突いて縄を切りにくるに違いない。うっかり寝ようものなら、寝首さえ掻かれ兼ねない。
「俺が寝ずの番をする、幹太と賢吉は寝なさい」
「右吉親分こそ寝てください、あっしが番をします」幹太が名乗り出た。
「俺も起きています」
賢吉は、そう言いながら一番先に寝てしまった。続いて右吉がうとうとし始めた。
「賢吉も右吉親分も、若けぇから無理もねぇや」
幹太は、やはり自分が起きていなければならないと、頬を叩いて頑張った。ところが、昼間に賢吉の足取りを追って歩きづくめだった為に疲れが出て、ついうとうととしてしまった。
幹太は、真夜中に気が付いて周りを見たところ、縛っておいた掏摸集団の男たちが姿を消していた。もしや、右吉と賢吉は寝込みを襲われて殺されたのではないかと心配になって駆け寄ったが、「スヤスヤ」と寝息を立てていた。
「右吉親分、起きてくだせぇ、皆逃げられました」
右吉は驚いて飛び起きたが、あとのまつりだった。
「面目ねぇ、あっしの所為です」
「いや、俺が寝てしまった所為だ」
右吉と幹太が庇い合っていたが、賢吉は「ヤツ等は、何故自分たちを殺さなかったのだろう」と、しきりに考えていた。
「それは、ヤツ等がただの掏摸集団だったのだろう」
この前の占い集団のように、何やら大きな目的を持った集団であれば、きっと口封じをして去ったであろう。
「それにしても、俺はどうして気付かなかったのだろう」
右吉も、首を傾げる。気の所為か荒ら家の中に、甘い香りが立ち込めているようであった。
「この匂いは…」 (次回に続く)
「賢吉捕物帖」第九回 作成中
「賢吉捕物帖」第一回 大川端殺人事件へ戻る
小さなお社の境内に人集りが出来ている。境内に走り込む人の群れは皆血相を変えている。賢吉は、その叫び声のなかに「仇討ち」という言葉を聞いた。仇討ちなど、生れてこの方見たことがない。恐いもの見たさに、賢吉も野次馬の一人になっていた。
賢吉は、目明しの父親長次に言い付けられて、朝から叔父の家まで使いに行った帰り道である。
「賢吉、この大根を持って帰れ」
百姓の叔父が育てた立派な大根を、五つばかり束ねて差し出した。
「重いから嫌だ」
「この罰当たりめ、重いから嫌だとは何事だ」
「だって、この後回るところがあるのに、大根背負って行けねぇや」
「良家のお坊ちゃんじゃあるめえし、何を軟弱(やわ)なことを言いやがる」
それでも、賢吉は無理やり持たされて、捨てることも出来ずに大根を背負ってお社のところまで帰って来たのだ。
お社の境内は、黒山の人だかりで、賢吉が潜り込もうとしても、弾き出されてしまった。
「こら、子供が見るものじゃない、けぇれ」
賢吉は未練気に人々の背中をみていたが、最初から見ていたらしく、微に入り細に入り説明をしている男が居た。賢吉が聞き耳を立てると、仇討ち側はまだ年端もいかない少年とその姉だそうである。
彼らは、花巻藩士倉掛半平太の倅・倉掛藤太郎と姉・美代と名乗ったそうである。敵は、元花巻藩士、笹川仁左衛門 訳は分からないが、姉弟の父を殺害し、江戸へ逃れてきたらしい。
賢吉は、仇討側がまだ子供だと聞いて心配になり、どうしても見たくなった。辺りを見回すと、少し離れた位置に松の木が植わっている。その木まで駆けていくと、大根を根元に下ろし登っていった。
弟は賢吉より二つ三つ年上だろうか、姉は十七、八のお年頃といったところであった。姉弟揃って純白の装束に白襷と鉢巻きで、手にはキラリと光る刃といった芝居で観る仇討姿そのままである。賢吉の目には、それが不自然に映った。
姉弟は江戸に出てきて敵(かたき)を探し回り、やっとここで出会ったのだと言っていたそうであるが、その割には装束に汚れはなく綺麗過ぎる。
江戸の地で仇討ちをするには、国元の藩で「仇討ち赦免状」を藩主から賜り、それを提示して奉行所で仇討ちの許可をとる。道で出会ったからと言って、無許可で仇討ちをしてもよいというものではないことを、賢吉は、与力の長坂清心に聞いたことがある。
賢吉は暫く見ていたが、一向に勝負が付かなかった。それはそれで良いことなのだが、仇敵は屈強な大男であり、仇討ち側はまだ幼さが残る弟と、きゃしゃな姉である。勝負などたちどころに付きそうなものである。
動きがない訳ではない。弟が斬られそうになると姉が庇い、姉が斬られそうになると弟が庇う。だが、どう見ても仇敵の男に姉弟を斬る意思が全くない様子だ。
「この仇討ち、芝居かも」
そう思って冷静な目で見ると、賢吉にはどうしても本気の仇討ちとは思えない。しかし、賢吉以外の野次馬は違う。視線は仇討ちに釘付けで、手に汗を握って姉弟を見守っている。江戸庶民の判官贔屓というところであろうか。
野次馬の動きを見ていて、賢吉は違和感を覚えた。仇討ちに夢中になっているなか、仇討ちそっちのけで矢鱈に場所を変更している人が何人か居るのだ。
「もしや、掏摸集団?」
その時、野次馬の一人が大声を出した。
「役人が来たぞ!」
一番に仇敵の男が反応した。姉弟を無視して、逃げだしたのだ。
「おのれ、逃がしはしないぞ!」
姉弟は、抜き身の刃先を下げて仇敵を追った。ふと我に返った野次馬の一人が、懐に手を突っ込んで気付いた。
「財布がない、掏摸だ!」
それにつられて、あっちでこっちでも「掏摸だ!」と喚きだした。賢吉は、木から降りると無意識で大根を背負い、姉弟の後を追った。
仇敵(きゅうてき) 笹川仁左衛門の姿は見えないが、賢吉は、倉掛藤太郎と姉美代の姿を捉えた。恐らく、笹川も倉掛姉弟の名も偽名であろう。この三者が行き着くところは同じに違いないと、賢吉は確信した。
姉弟にかなり接近してしまった賢吉は、とうとう気付かれてしまった。
「お姉さん、大根は要りませんか、一本十二文です」
不審がられる前に、賢吉が声を掛けたのだ。
「要りませぬ」
つっけんどんな物言いが、武士の娘であることを明かしている。
「美味しいですよ」
「要らないと言ったら、要らないのです」
「お屋敷まで、お持ちしますから一本如何です」
「諄い、怒りますよ」
「すみません」
断られ乍らも、尚も付いてくる賢吉に、弟が刀を抜いて脅してきた。
「戻れ、我らに付いてくるな」
「俺も、こちらに戻りますので…」
「それなら、もっと離れて歩け」
賢吉は、仕方なく傍らの石積みに腰を掛けて休息する振りをした。先ほどから、賢吉は大根の葉を毟っては道の端に捨てているが、満更断られた腹いせでもなさそうである。
やがて姉弟が、森の木に覆われた荒れ寺に入って行くのを賢吉は見届けた。こっそり忍び込んで様子を窺うと、やはり仇敵笹川と倉掛姉弟は仲間であり、親子のようであった。円く囲んだ人々の真ん中には、巾着や財布が置かれている。
「やはり、掏摸の集団だったか」
賢吉が小さく呟いたとき、何者かに肩を掴まれた。
「おい小僧、何をしておる」
賢吉は驚いて飛び退いたが遅かった。腕を取られて後ろ手に捩じ上げられた。
昼過ぎになって、長次の詰める番屋に、賢吉の弟と妹がやってきた。
「おめえら、どうした?」
「腹が減った、兄ちゃんが帰ってこない」
長次は首を傾げた。
「兄貴のところへ使いにやったが、昼前には帰ってくる筈だ」
「兄ちゃん、何処かへ寄っているのかなぁ」
「兄弟思いの賢吉のことだ、寄り道しているとは思えねえ」
とにかく、子供たちに昼飯を食べさせて賢吉の帰りを待ったが、未の刻(午後一時)頃になっても帰ってこなかった。
「長次親分、俺が探してこようか」
右吉が名乗り出た。
「そうか、では幹太と一緒に兄貴のところまで見に行って貰おうか」
長次の兄の家は、下っ引きの幹太が知っている。二人は出かけて行ったが、しっかり者の賢吉のことだ、叔父に使いを頼まれでもしたのだろうと、さほど心配していなかった。
日の高いうちに賢吉の叔父の家に着いたが、賢吉は大根を担いでとうに帰ったと知らされた。
「帰り道、何か事件に出会わせたのだろうか」
薄暮れ刻、お社の境内でなにやら文句を言いながら掃除をしている神主が居た。右吉は目明しであることを告げて憤っている神主に訳を尋ねた。
「昼間、ここで仇討ち騒動があってのう」
断りもなく境内を荒らされたうえに、返り討ちにでも遭ったのか詫びにも来ないのだという。
「その騒動のとき、大根を担いだ子供を見かけませんでしたか?」
神主は、即答した。
「居ましたわい、人垣が多くて見えないので、罰当たりめ境内の木に登って見物しておった」
賢吉に相違ない。
「結局、ここでは勝負が付かずに、敵の男は逃げだし、討つ側の姉弟が敵を追いかけた」
「その後、子供はどうしました?」
「そのうち、あっちでもこっちでも掏摸だと叫ぶ者が居て、その子は何を思ったか大根を担ぐと後を追って行った」
「逃げたのは、どの方向でしたか?」
神主は、黙って箒の柄で行った先を指した。右吉と幹太は、神主の手を止めた詫びを言って駆けて行った。
「賢吉は、この仇討ちを掏摸集団が企んだものだと勘付いて、後を追ったようだ」
「深入りしていなければよいのに」
幹太は、心配になってきた。
二人走って行くと、道端に千切れた大根の葉が落ちているのに気付いた。
「賢吉だ、賢吉が我らに教える為に大根の葉を落として行ったのだ」
だが、やがて日がとっぷりと落ちてしまった。今宵は月も出ぬようである。
「どこかで、提灯を借りよう」
更に進むと、森の木々の間から灯りが見えた。右吉と幹太が、灯りを目指して森に入ろうとした時、幹太が何かに躓いて転びそうになった。
「右吉親分、足元に大根が…」
「そうか、あの荒ら家に賢吉が掴まっているらしい」
近付いて荒ら家の中を覗いてみると、大勢で酒盛りをしている。賢吉はと見ると、隅の柱に縛り付けられて居眠りをしている。
「泣いているかと思えば、賢吉のヤツ船を漕いでいやがる」
「さすが長次親分の息子だ、肝が据わっていますね」
さて、踏み込もうにも多勢に無勢である。しかも、刀を持った武士も居る。右吉は、刀を持っていない。右吉は何を思ったか、懐の十手を幹太に渡した。
「幹太は、その辺に隠れて待っていてくれ」と、単身で荒ら家の中へ入っていった。
「旅の途中で日が暮れてしまいました」
酒に酔った浪人風の男が、腰に刀をぶっ込んで出てきた。
「提灯をお借りしたいと思いまして…」
聞き慣れた声に、賢吉が目を覚ました。
「嘘をつけ、旅支度はしておらんじゃないか、お前目明しだろう」
男は、いきなり右吉の懐に手を突っ込んだ。十手を隠し持っているのではないかと疑っているようだ」
「いえ、武家の下働きでございます」
男は、右吉の懐から巾着を掴み出して紐を解いた。
「チッ、しけてやがる、たったこれだけかい」
男が巾着の中を覗いたとき、右吉は素早く男の刀を抜き取った。刀が手に入れば酔った男の十人や二十人など右吉の敵ではない。縛られた賢吉のところに走り寄ると、縄を切った。
「賢吉、表で幹太が待っている、呼んで来い」
右吉は叫ぶと、刀の峰を返して構えた。
「刀を隠し持っているところをみると、貴様たちはただの掏摸集団ではなかろう、拙者が退治してやる」
右吉は、刀を手にすると武士に戻る。そのとき、右吉の後ろで男の声がした。
「刀を捨てろ! 捨てぬと、このガキの命はないぞ!」
幹太を呼びに行った筈の賢吉が、男に羽交い絞めされて首に匕首を押し当てられている。賢吉が、少し暴れでもしたら、刃が喉笛を引き裂く。右吉はあっさりと降参して、黙って刀を自分の足元へ投げ捨てた。男は、賢吉を羽交い絞めにしたまま右吉の傍まで摺り足で近寄り、右吉が捨てた刀を蹴り離した。
蹴った瞬間、男の持った匕首が賢吉の首から少し離れたのを右吉は見逃さなかった。男の匕首を持つ手首を、掌底でしたたかに打ち据えた。
「あっ!」
男は、思わず匕首を落とした。賢吉は、そのまま逃げるかと思えば、男の方に向き直って、男の下腹を力任せに蹴り上げた。その間に右吉は刀を拾うと、男が蹲るのを確かめ、賢吉に「行け!」と目で合図をした。
賢吉は幹太を呼びに走ろうとしたが、幹太は騒ぎを聞きつけて荒ら家に入ってきたところだった。
「賢吉、大丈夫か、首に血が滲んでいるぞ」
「大丈夫です、親分が助けてくれました」
右吉に対していた男が、また一人ドタンと倒された。
「幹太、倒れているヤツ等を縛れ! その隅に荒縄がたくさん有る」
「よしきた」
幹太に手伝って、賢吉も倒れている男たちの手足を縛った。
最後に三人残った。右吉はこの集団の頭目と思しき浪人に向かって刀を中段に構えている。賢吉と幹太が見ていて、右吉が苦戦をしいられているのが分かる。浪人が相当の腕を持った手練れなのだ。
右吉は、対している浪人に打ち込む隙がなく、手古摺っている。賢吉は、右吉に助勢する術もなく、焦りが出てきたとき、浪人に隙が出来た。
「娘に、手をだすな!」
浪人の視線の先を見れば、幹太が娘を縛ろうとしている。その浪人の声を聞いて、弟らしい少年が幹太の背中に刀を振り下ろそうとしている。
「危ない!」
賢吉は、咄嗟に懐の巾着を取り出すと、少年の顔をめがけて投げつけた。
賢吉が投げた巾着が、刀を振り下ろそうとした少年の目に当たった。
「あっ!」
少年の驚きの声に幹太が気付き、振り返った。少年が気を取り戻して再び振り下ろそうとした刀を、幹太の十手が受け止めた。その隙に、娘は幹太の手から逃れて、少年を促して闇に消えた。
右吉に対していた集団の頭目らしい浪人が、奇声を発しながら打ち込んできた。右吉は辛うじて峰で受け止め、力任せに押し返した。
右吉は再び中段に構えたが、ここでゆっくりと峰に返していた刀を戻した。刀の峰では互角に戦えぬと判断したのだ。
このとき、闇の中に隠れていた少年が、浪人に加勢するために走り出た。
「父上!」
それが、却って浪人に隙を与えてしまった。隙を衝いて右吉の刀が浪人の脇腹に入った。心配顔で父親を見る少年に、右吉が言い放った。
「安心致せ、峰打ちだ」
右吉の僅かな余裕が、瞬時に刃を返していたのだ。幹太が息子を捉えて縛り上げる間に、右吉は呻いている父親を縛り上げた。
「今夜は寝ずの番だ」
右吉が、つぶやいた。姉が逃げている。隙を突いて縄を切りにくるに違いない。うっかり寝ようものなら、寝首さえ掻かれ兼ねない。
「俺が寝ずの番をする、幹太と賢吉は寝なさい」
「右吉親分こそ寝てください、あっしが番をします」幹太が名乗り出た。
「俺も起きています」
賢吉は、そう言いながら一番先に寝てしまった。続いて右吉がうとうとし始めた。
「賢吉も右吉親分も、若けぇから無理もねぇや」
幹太は、やはり自分が起きていなければならないと、頬を叩いて頑張った。ところが、昼間に賢吉の足取りを追って歩きづくめだった為に疲れが出て、ついうとうととしてしまった。
幹太は、真夜中に気が付いて周りを見たところ、縛っておいた掏摸集団の男たちが姿を消していた。もしや、右吉と賢吉は寝込みを襲われて殺されたのではないかと心配になって駆け寄ったが、「スヤスヤ」と寝息を立てていた。
「右吉親分、起きてくだせぇ、皆逃げられました」
右吉は驚いて飛び起きたが、あとのまつりだった。
「面目ねぇ、あっしの所為です」
「いや、俺が寝てしまった所為だ」
右吉と幹太が庇い合っていたが、賢吉は「ヤツ等は、何故自分たちを殺さなかったのだろう」と、しきりに考えていた。
「それは、ヤツ等がただの掏摸集団だったのだろう」
この前の占い集団のように、何やら大きな目的を持った集団であれば、きっと口封じをして去ったであろう。
「それにしても、俺はどうして気付かなかったのだろう」
右吉も、首を傾げる。気の所為か荒ら家の中に、甘い香りが立ち込めているようであった。
「この匂いは…」 (次回に続く)
「賢吉捕物帖」第九回 作成中
「賢吉捕物帖」第一回 大川端殺人事件へ戻る