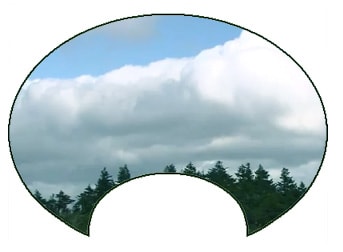一晩かけて三十石船は淀川を下り、大坂は淀屋橋に着いた。よく寝ていないのか、辰吉は眠い目をこすりながら下船した。
「三太兄ぃ、元気にしているかなぁ」
『二・三日前に別れたばかりじゃねぇか』辰吉の守護霊、新三郎である。
「うん、まあな」
町並みを少し外れた道を歩いていて、廃屋寸前のような荒屋に、板切れに「鷹塾」と書かれた看板を辰吉が見つけた。
「新さん、あれ鷹塾と書かれている、三太兄ぃが通っていた塾だろ」
『場所は違うが、同じ名だな』
しばらくこの場に留まって様子を窺っていると、四・五歳の子供が五人集まってきた。
「先生、おはようございます」
子供たちはそれぞれ元気な声で挨拶をすると、荒屋の中へ入っていった。
「お早う、みんな揃っているか?」
「はい、五人揃っています」
「そうか、ほんなら長座卓を並べて待っていてや、先生食事の後片付けをするから」
「はーい」
辰吉は鷹塾を知らないが、鷹之助には一度会っている。
「新さん、あの先生、鷹之助先生と違うか?」
『違う、違う、鷹之助さんは上方言葉を使わない』
その声は二十四・五歳というところか、三太よりも少し上のようである。子供たちはガヤガヤとお喋りをしながら長座卓を並べ、算盤を置いているのが窓から見える。
「先生、誰か窓から覗いとる」
先生と呼ばれた男が、血相を変えて表に飛び出してきた。
「子供たちには関係おまへん、どうか子供たちを巻き添えにしないでください」
そう叫んだ後、辰吉を見て人間違いと気付いたらしく、「すんまへん」と、頭を下げた。
「いえいえ、こちらこそ覗いたりして、子供たちを怖がらせてしまいました、勘弁してください」
「何かご用でしたか?」
「あ、いやいや、ちょっと鷹塾という名に心当たりがありましたもので、つい覗いてしまいました」
「鷹塾に心当たりといいますと、もしや佐貫鷹之助先生のお知り合いでおますか?」
「やはり鷹之助先生と関わりがありましたか、じつはそうなのです、それに鷹塾の塾生でした三太さんや源太さんにも関わった者です」
「えっ、源太ですか? 源太は私の弟です、三太さんは私と机を並べて勉強した塾生同士です」
「ついこの間、源太さんにお会いしましたが、お元気でしたよ」
「そうですか、そうですか、心配しておりましたので、何よりのお便りでございます」
「それと、三太さんが大坂へ戻っているのはご存知でしたか?」
「三太が大坂に戻っているのですか、知りませんでした」
「立派になって帰っていますので、是非会ってやってください」
「それはもう、今直ぐにでも飛んで行きとうございます」
三吉は、佐貫鷹之助の弟子源太の兄である。鷹之助が信濃へ戻ったあと、小さい子供たちを集めて鷹塾を継いだが、鷹塾があった古屋は取り壊されて廃塾になった。三吉は鷹之助の意志を継ぐべく古屋を探しては何度も鷹塾を開いたが、古屋はすぐに追い出され、地廻りに僅かな収入の殆どを取り上げられ、三吉一人食っていけるのがやっとであった。
「それで俺を地回りと間違えたのですね」
「そうです、子供たちを怖がらせてはならないという一心で、慌ててしまいました」
「三吉さん、俺と三太兄ぃが鷹塾の後押しをしましょう、もう決して地回りに勝手なことをさせませんから安心なさい」
「ほんとうですか、有難う御座います」
塾は午前中で終わると言うので、辰吉は子供たちの後ろで待つことにした。子供たちは辰吉が気になるのか、勉強途中にチラチラ後ろを見ていた。この後、子供たちを送って行くと、辰吉のおごりで外食をし、三太の奉公する相模屋長兵衛のお店(たな)へ会いに行った。
「番頭さん、お客さんだす」
三太さんに会いたいと言うと、小僧が取り継いでくれた。三太はこのお店の番頭らしい。
「おや、辰吉坊ちゃん、帰ってきはりましたか」
「はい、江戸の辰吉、ただ今戻りました」
「何が江戸の辰吉や、もう旅鴉やあらへん、福島屋辰吉と名乗りなはれ」
「福島屋辰吉、恥ずかしながらただ今帰って参りました」
「余計なことは言わんでもよろしい、何が恥ずかしながらやねん」
「へい」
「それで、亥之吉旦那に会ってきはりましたのやろな」
「いえ、まだ」
「何をしていますのや、真っ先にお父っぁんに顔を見せなはらんか」
「それが…敷居が高くて」
「旦那さんも、お絹女将さんも、心配して待っていなはるのに、何が敷居や」
ようやく、三太は辰吉に連れが居ることに気が付いた。
「そのお方は?」
ちょっと三吉を見た三太は、直ぐに気が付いたようであった。
「三吉先生やおまへんか、やっぱり三吉さんや」
三吉は頷き、三太は懐かしそうに三吉の手を取った。
「すっかり大人になりはったが、面影は残っています、やっぱり兄弟ですねぇ、源太さんにそっくりですわ」
三太は、大坂に帰ってきたとき、真っ先に鷹塾の有った場所に行ってみたそうである。建物は壊されて、土地は草が生え茂り、鷹塾は跡形もなく消えていた。鷹之助の奥方、お鶴の実家に行って塾生であった子供たちのその後の消息を尋ねたが、分からないということであった。
鷹之助の元で学ぶ源太の元気な消息を伝えようと源太の実家を訪ねてみたが、荒れ果てて人の住む様子はなかった。
「三吉さん、今ご両親はどこにお住まいですか?」
「両親は亡くなりました、源太の他にもう一人弟が居ますが、大工の棟梁の元で修業しております」
「そうでしたか、源太さんに会いましたが、ご両親が亡くなったとは一言も言っておりませんでした…」
「親父の遺言で、源太には知らせるなと固く止められていましたので…」
「修業の邪魔になるからでしょうか」
「そうだと思います」
「三吉さん、あなたはどうしてここに?」
三吉は、当時鷹之助の助手をしていたが、鷹之助が信濃へ帰ったあと、意志を受け継いで、鷹塾を再開したこと、借りていた古屋を次々と追われたこと、地廻りに金を巻き上げられていることなどを三吉に代わり辰吉が代弁した。
「知っていれば、わいがなんとかしたものを…」
三太は悔しがった。
「三吉先生、わいが知ったからには、悪いようにはしまへん、鷹之助先生の鷹塾よりも、もっと立派な鷹塾にして、三吉先生に活躍してもらいます」
そして、源太の帰りを待って、立派な鷹塾に先生として迎えましょうと、再び三吉の手を握りしめた。
「三太兄ぃ、一人で何を意気がっているのです、辰吉も居るのですぜ」
「あかん、辰吉坊ちゃんは、鷹之助先生の塾生ではおまへん、余所者や」
「何だいそれは、俺にはもと鷹之助先生の守護霊だった新さんが憑いているのですよ」
「あ、ほんまや、余所者と違うわ」
三吉は泣いていた。余程悔しいことや、辛いことがあったのだろう。あのチビ三太が、こんなにも逞しくなって、ふと知り合った辰吉と共に自分の肩を押してやろうと言う。弟の元気な消息を知ると共に、急に目の前が開けたような感動が涙になって溢れたのであった。
その夜、地回りが脅しに来るというので、辰吉が鷹塾に泊まることになった。親父の亥之吉に会うのは後回しになった訳だ。
三吉と共に夕餉を平らげ、話をしながら地回りが来るのを待った。
「三吉さん、今度暇が出来たら、俺と一緒に旅に出ないか?」
「もしや、源太に会いにいくのですか?」
「うん、源太もいい大人だ、何時までもご両親のことを伝えないのはよくないよ」
「そうでしょうか」
「兄貴の元気な顔を見せてやろうじゃないか」
「そう出来ればうれしおますのやが」
「塾生が気がかりかい?」
「はい」
「ちゃんと訳を話せば分かってくれると思うよ」
「辰吉さんは、何時でも旅に出られるのですか?」
「三太の兄ぃが、親父との間を取り持ってくれるだろう」
日も暮れかかった頃、三人の男が鷹塾に入ってきて、土足で上がり込んだ。
「三吉、今日はショバ代を払って貰うで」
「何や、ショバ代って」辰吉が問うた。
「うちの縄張り内で商売したら、ショバ代を払うのが当たり前やろ、ところであんさん何者や、三吉の何や」
「三吉さんの友達や」
「そのお友達はんが、えらそうな口を叩くやないか」
「商売言うたかて、十文、二十文という僅かな月並銭で勉強を教えているのや、何がショバ代や、奉行所に訴えて、取り締まって貰いましょか」
「あほ抜かせ、わいらの後ろには同心が付いているのや」
「同心が何や、わいにはお奉行が付いているのやで」
「ハッタリもええかげんにさらせ」
「その同心の名前を聞こうやないか」
「そんなもん、言えるかい」
「名前も言えん同心に、何ができるのや」
「こいつ、ガキの癖に生意気な口を叩きよって、わい等の恐さを思い知らせてやる」
懐から匕首を取り出して脅して見せた。
「そんなもので脅されて黙るわいやないで」
怒ると上方弁が出る辰吉、六尺棒を振り上げた。
「さあ、束になってかかってきやがれ、束言うたかて、たった三本の一束やなぁ」
辰吉は勇ましいセリフを吐いた割には、敵に背中を見せて外へ飛び出して行った。男たちは、すぐさま辰吉を追って飛び出してきた。
「口が利けないようにしてやる」
地回りの一人が、匕首の鞘を拔きはらって一歩辰吉に接近した。辰吉が一歩下がると、ここぞとばかり匕首を左右に振りながら、さらに接近してきた。
辰吉は更に下がったが、さがりざまに棒を振り下ろした。「がっ」と乾いた音がして、男は右腕を抱えて悲鳴をあげた。
「こいつ、やりやがったな」
二人目が突っ込んで来たのを、体を交わすと男はつんのめった。その背中を「ぼこん」と棒で打つと、そのまま頭から倒れた。
三人目は、辰吉に背を向けて逃げた。その背中に、辰吉が投げた棒の先が命中して、男は足がもつれ、二・三歩泳いで上体から前に倒れた。
「おい、お前、腕の骨にヒビが入ったと思うぜ、早く医者に駆け込め」
最初に飛び込んできた男に言った。その男は慌てて逃げ去ったが、他の二人は遠巻きに辰吉を睨み、「憶えとけよ」と捨てゼリフを残して立ち去った。その夜は鷹塾に泊まり、仕返しに来るかと待ったが、来なかった。
翌日、塾は開かれ、無事に終えた。午後、辰吉は三吉と共に、昨夜有ったことを報告する為に三太に会いに行った。
「坊っちゃん、あんさんはやくざと違いまっせ、何てことをしましたのや」
三太は笑っていたが、これから堅気の商人になる若旦那が、地廻りと喧嘩して相手を傷つけるとは、なんたる軽はずみなことをしたのだと、辰吉を咎めていた。
「さあ、わいが付いて行きますさかい、旦那様のところへ行きましょ」
辰吉の父親、亥之吉は福島屋本店に留まっていた。取り敢えず空き店舗を見つけて、商売を始めようと東奔西走している最中であった。
「辰吉、お帰り」
亥之吉は、何事も無かったように辰吉を迎えてくれた。辰吉が地回りと喧嘩をして、相手を傷つけたと三太が話したが、亥之吉は意に反して辰吉を叱ることもなく、ただ笑っていた。
「そうか、あんな屑野郎たちと喧嘩したのか、心配せんでもええ、わいがちゃんと話を付けてやる」
「三吉も何も恐れることはないのやで、安心して塾が開けるようにしてやるさかいにな」
辰吉は、この親父をとてつもなく大きく感じた。三太もまた、「このスケベ親父、頼もしいな」と、我師匠を誇らしく思った。
「第十九回 鷹塾の三吉先生」 -続く- (原稿用紙16枚)
「第二十回 師弟揃い踏み 」へ
「三太兄ぃ、元気にしているかなぁ」
『二・三日前に別れたばかりじゃねぇか』辰吉の守護霊、新三郎である。
「うん、まあな」
町並みを少し外れた道を歩いていて、廃屋寸前のような荒屋に、板切れに「鷹塾」と書かれた看板を辰吉が見つけた。
「新さん、あれ鷹塾と書かれている、三太兄ぃが通っていた塾だろ」
『場所は違うが、同じ名だな』
しばらくこの場に留まって様子を窺っていると、四・五歳の子供が五人集まってきた。
「先生、おはようございます」
子供たちはそれぞれ元気な声で挨拶をすると、荒屋の中へ入っていった。
「お早う、みんな揃っているか?」
「はい、五人揃っています」
「そうか、ほんなら長座卓を並べて待っていてや、先生食事の後片付けをするから」
「はーい」
辰吉は鷹塾を知らないが、鷹之助には一度会っている。
「新さん、あの先生、鷹之助先生と違うか?」
『違う、違う、鷹之助さんは上方言葉を使わない』
その声は二十四・五歳というところか、三太よりも少し上のようである。子供たちはガヤガヤとお喋りをしながら長座卓を並べ、算盤を置いているのが窓から見える。
「先生、誰か窓から覗いとる」
先生と呼ばれた男が、血相を変えて表に飛び出してきた。
「子供たちには関係おまへん、どうか子供たちを巻き添えにしないでください」
そう叫んだ後、辰吉を見て人間違いと気付いたらしく、「すんまへん」と、頭を下げた。
「いえいえ、こちらこそ覗いたりして、子供たちを怖がらせてしまいました、勘弁してください」
「何かご用でしたか?」
「あ、いやいや、ちょっと鷹塾という名に心当たりがありましたもので、つい覗いてしまいました」
「鷹塾に心当たりといいますと、もしや佐貫鷹之助先生のお知り合いでおますか?」
「やはり鷹之助先生と関わりがありましたか、じつはそうなのです、それに鷹塾の塾生でした三太さんや源太さんにも関わった者です」
「えっ、源太ですか? 源太は私の弟です、三太さんは私と机を並べて勉強した塾生同士です」
「ついこの間、源太さんにお会いしましたが、お元気でしたよ」
「そうですか、そうですか、心配しておりましたので、何よりのお便りでございます」
「それと、三太さんが大坂へ戻っているのはご存知でしたか?」
「三太が大坂に戻っているのですか、知りませんでした」
「立派になって帰っていますので、是非会ってやってください」
「それはもう、今直ぐにでも飛んで行きとうございます」
三吉は、佐貫鷹之助の弟子源太の兄である。鷹之助が信濃へ戻ったあと、小さい子供たちを集めて鷹塾を継いだが、鷹塾があった古屋は取り壊されて廃塾になった。三吉は鷹之助の意志を継ぐべく古屋を探しては何度も鷹塾を開いたが、古屋はすぐに追い出され、地廻りに僅かな収入の殆どを取り上げられ、三吉一人食っていけるのがやっとであった。
「それで俺を地回りと間違えたのですね」
「そうです、子供たちを怖がらせてはならないという一心で、慌ててしまいました」
「三吉さん、俺と三太兄ぃが鷹塾の後押しをしましょう、もう決して地回りに勝手なことをさせませんから安心なさい」
「ほんとうですか、有難う御座います」
塾は午前中で終わると言うので、辰吉は子供たちの後ろで待つことにした。子供たちは辰吉が気になるのか、勉強途中にチラチラ後ろを見ていた。この後、子供たちを送って行くと、辰吉のおごりで外食をし、三太の奉公する相模屋長兵衛のお店(たな)へ会いに行った。
「番頭さん、お客さんだす」
三太さんに会いたいと言うと、小僧が取り継いでくれた。三太はこのお店の番頭らしい。
「おや、辰吉坊ちゃん、帰ってきはりましたか」
「はい、江戸の辰吉、ただ今戻りました」
「何が江戸の辰吉や、もう旅鴉やあらへん、福島屋辰吉と名乗りなはれ」
「福島屋辰吉、恥ずかしながらただ今帰って参りました」
「余計なことは言わんでもよろしい、何が恥ずかしながらやねん」
「へい」
「それで、亥之吉旦那に会ってきはりましたのやろな」
「いえ、まだ」
「何をしていますのや、真っ先にお父っぁんに顔を見せなはらんか」
「それが…敷居が高くて」
「旦那さんも、お絹女将さんも、心配して待っていなはるのに、何が敷居や」
ようやく、三太は辰吉に連れが居ることに気が付いた。
「そのお方は?」
ちょっと三吉を見た三太は、直ぐに気が付いたようであった。
「三吉先生やおまへんか、やっぱり三吉さんや」
三吉は頷き、三太は懐かしそうに三吉の手を取った。
「すっかり大人になりはったが、面影は残っています、やっぱり兄弟ですねぇ、源太さんにそっくりですわ」
三太は、大坂に帰ってきたとき、真っ先に鷹塾の有った場所に行ってみたそうである。建物は壊されて、土地は草が生え茂り、鷹塾は跡形もなく消えていた。鷹之助の奥方、お鶴の実家に行って塾生であった子供たちのその後の消息を尋ねたが、分からないということであった。
鷹之助の元で学ぶ源太の元気な消息を伝えようと源太の実家を訪ねてみたが、荒れ果てて人の住む様子はなかった。
「三吉さん、今ご両親はどこにお住まいですか?」
「両親は亡くなりました、源太の他にもう一人弟が居ますが、大工の棟梁の元で修業しております」
「そうでしたか、源太さんに会いましたが、ご両親が亡くなったとは一言も言っておりませんでした…」
「親父の遺言で、源太には知らせるなと固く止められていましたので…」
「修業の邪魔になるからでしょうか」
「そうだと思います」
「三吉さん、あなたはどうしてここに?」
三吉は、当時鷹之助の助手をしていたが、鷹之助が信濃へ帰ったあと、意志を受け継いで、鷹塾を再開したこと、借りていた古屋を次々と追われたこと、地廻りに金を巻き上げられていることなどを三吉に代わり辰吉が代弁した。
「知っていれば、わいがなんとかしたものを…」
三太は悔しがった。
「三吉先生、わいが知ったからには、悪いようにはしまへん、鷹之助先生の鷹塾よりも、もっと立派な鷹塾にして、三吉先生に活躍してもらいます」
そして、源太の帰りを待って、立派な鷹塾に先生として迎えましょうと、再び三吉の手を握りしめた。
「三太兄ぃ、一人で何を意気がっているのです、辰吉も居るのですぜ」
「あかん、辰吉坊ちゃんは、鷹之助先生の塾生ではおまへん、余所者や」
「何だいそれは、俺にはもと鷹之助先生の守護霊だった新さんが憑いているのですよ」
「あ、ほんまや、余所者と違うわ」
三吉は泣いていた。余程悔しいことや、辛いことがあったのだろう。あのチビ三太が、こんなにも逞しくなって、ふと知り合った辰吉と共に自分の肩を押してやろうと言う。弟の元気な消息を知ると共に、急に目の前が開けたような感動が涙になって溢れたのであった。
その夜、地回りが脅しに来るというので、辰吉が鷹塾に泊まることになった。親父の亥之吉に会うのは後回しになった訳だ。
三吉と共に夕餉を平らげ、話をしながら地回りが来るのを待った。
「三吉さん、今度暇が出来たら、俺と一緒に旅に出ないか?」
「もしや、源太に会いにいくのですか?」
「うん、源太もいい大人だ、何時までもご両親のことを伝えないのはよくないよ」
「そうでしょうか」
「兄貴の元気な顔を見せてやろうじゃないか」
「そう出来ればうれしおますのやが」
「塾生が気がかりかい?」
「はい」
「ちゃんと訳を話せば分かってくれると思うよ」
「辰吉さんは、何時でも旅に出られるのですか?」
「三太の兄ぃが、親父との間を取り持ってくれるだろう」
日も暮れかかった頃、三人の男が鷹塾に入ってきて、土足で上がり込んだ。
「三吉、今日はショバ代を払って貰うで」
「何や、ショバ代って」辰吉が問うた。
「うちの縄張り内で商売したら、ショバ代を払うのが当たり前やろ、ところであんさん何者や、三吉の何や」
「三吉さんの友達や」
「そのお友達はんが、えらそうな口を叩くやないか」
「商売言うたかて、十文、二十文という僅かな月並銭で勉強を教えているのや、何がショバ代や、奉行所に訴えて、取り締まって貰いましょか」
「あほ抜かせ、わいらの後ろには同心が付いているのや」
「同心が何や、わいにはお奉行が付いているのやで」
「ハッタリもええかげんにさらせ」
「その同心の名前を聞こうやないか」
「そんなもん、言えるかい」
「名前も言えん同心に、何ができるのや」
「こいつ、ガキの癖に生意気な口を叩きよって、わい等の恐さを思い知らせてやる」
懐から匕首を取り出して脅して見せた。
「そんなもので脅されて黙るわいやないで」
怒ると上方弁が出る辰吉、六尺棒を振り上げた。
「さあ、束になってかかってきやがれ、束言うたかて、たった三本の一束やなぁ」
辰吉は勇ましいセリフを吐いた割には、敵に背中を見せて外へ飛び出して行った。男たちは、すぐさま辰吉を追って飛び出してきた。
「口が利けないようにしてやる」
地回りの一人が、匕首の鞘を拔きはらって一歩辰吉に接近した。辰吉が一歩下がると、ここぞとばかり匕首を左右に振りながら、さらに接近してきた。
辰吉は更に下がったが、さがりざまに棒を振り下ろした。「がっ」と乾いた音がして、男は右腕を抱えて悲鳴をあげた。
「こいつ、やりやがったな」
二人目が突っ込んで来たのを、体を交わすと男はつんのめった。その背中を「ぼこん」と棒で打つと、そのまま頭から倒れた。
三人目は、辰吉に背を向けて逃げた。その背中に、辰吉が投げた棒の先が命中して、男は足がもつれ、二・三歩泳いで上体から前に倒れた。
「おい、お前、腕の骨にヒビが入ったと思うぜ、早く医者に駆け込め」
最初に飛び込んできた男に言った。その男は慌てて逃げ去ったが、他の二人は遠巻きに辰吉を睨み、「憶えとけよ」と捨てゼリフを残して立ち去った。その夜は鷹塾に泊まり、仕返しに来るかと待ったが、来なかった。
翌日、塾は開かれ、無事に終えた。午後、辰吉は三吉と共に、昨夜有ったことを報告する為に三太に会いに行った。
「坊っちゃん、あんさんはやくざと違いまっせ、何てことをしましたのや」
三太は笑っていたが、これから堅気の商人になる若旦那が、地廻りと喧嘩して相手を傷つけるとは、なんたる軽はずみなことをしたのだと、辰吉を咎めていた。
「さあ、わいが付いて行きますさかい、旦那様のところへ行きましょ」
辰吉の父親、亥之吉は福島屋本店に留まっていた。取り敢えず空き店舗を見つけて、商売を始めようと東奔西走している最中であった。
「辰吉、お帰り」
亥之吉は、何事も無かったように辰吉を迎えてくれた。辰吉が地回りと喧嘩をして、相手を傷つけたと三太が話したが、亥之吉は意に反して辰吉を叱ることもなく、ただ笑っていた。
「そうか、あんな屑野郎たちと喧嘩したのか、心配せんでもええ、わいがちゃんと話を付けてやる」
「三吉も何も恐れることはないのやで、安心して塾が開けるようにしてやるさかいにな」
辰吉は、この親父をとてつもなく大きく感じた。三太もまた、「このスケベ親父、頼もしいな」と、我師匠を誇らしく思った。
「第十九回 鷹塾の三吉先生」 -続く- (原稿用紙16枚)
「第二十回 師弟揃い踏み 」へ