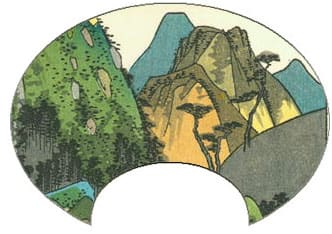敵の注目を亥之吉に向けさせておいて、新平を雨宿り小屋へ走らせた筈だったが、刺客を倒して新平を呼び寄せようとすると、そこに新平の姿はなかった。どうやら、小屋の中にも刺客の仲間が居て、新平を連れ去ったようであった。
「何の目的で連れ去ったのですやろ」
亥之吉は自分の迂闊を後悔していた。
「旦那様、それは捕まった仲間の命と交換する為やと思います」
三太は、新平の安否が心配で、半ベソをかいている。
「新さんの勘で、なんとか居場所を突き止めてください」
三太の頼みの綱は、新さんの推理であった。
「何も手懸りを残していないので、ただ四方八方を探すだけです」
遠くまでは行っていないとは思うが、大名の若様の一行は一言の礼もなく江戸を向けて既に発ってしまったので、亥之吉と三太と幽霊の新三郎だけで探さねばならない。
「手を拱いていても仕方がおまへん、敵は若様の後を追ったか、捕まった仲間たちのあとを追ったか、どちらかやと思うが、わいは若様を追う、三太は城へ戻る捕り方の後を追とくなはれ」
「わかりました」
その時、三太の懐でコン太が暴れだした。
「わっ、こんな時に腹を空かしたのかいな」
仕方なくコン太を下ろして、軍鶏の卵を食べさせようとしたが、それには見向きもせずにコン太は走りだした。
「コン太、何処へ行くのや?」
コン太は、仔狐の癖に素早い。
「こらっ、戻って来い! 今は忙しいのや、コン太と遊んでいる暇は無い」
それでも、コン太は走っては止まり、振り返って三太の姿を確認してはまた走る。こんなに走れるのに、三太の懐に入りたがる。「この横着もんが」三太はコン太の後を追うのをやめた。
「コン太、放っといて船に乗るで」
コン太には、何かが憑いたかのように走り続ける。
「もう、しゃあないなあ、何がしたいのや」
三太の脳裏に、ふと、あることが浮かんだ。コン太は、新平の臭いはよく覚えている。それを犬のように辿っているのではないだろうか。
「旦那様、ちょっと待っとくなはれ、コン太の様子が唯事では無いようだす、新平の臭いを追っかけているようなのです」
亥之吉の頭の中では、「仔狐に犬の真似ができるかいな」と、否定的である。
「大好きな卵には目もくれずに走りだしましたんや、これは何かおます」
「さよか、ただのウンチをる場所探しかも知れまへんで」
「お願いします、コン太に付き合ってください」
「わかった、後を追いましょ」
コン太は、「ハァハァ」と、息を荒げながら、それでも十町(約1Km)を走り通した。ようやくコン太が止まった畑の中に、農家の農具などを入れておく掘建小屋があった。三太が新平の名を呼ぼうとしたとき、慌てて亥之吉が遮った。
「し-っ、まだ刺客がいるようだす、ここはわいに任せておきなはれ」
亥之吉が小屋にそっと忍び寄ると、小屋の中に人の気配がする。
「小屋から柄杓だして、畑に肥を撒くさかいに、お芳、先に菜畑へ行っといてや」
と、芝居をしておいて、亥之吉が天秤棒を手に持って小屋の戸をあけると、案の定、男が一人、剣を鞘から抜いて、仁王立ちになっていた。
「うわぁ、吃驚した、おまはんは何方でおます」
問答無用、見られたからには殺すしかないと思ったのか、男はいきなり亥之吉に向かってきた。
「何をしはりますねん、わたいが何をしたといいますのや」
「気の毒だか、命は貰い受ける」
男は小屋から飛び出すと、亥之吉目掛けて刀を左から右に振った。亥之吉は後ろに飛び退くと、天秤棒を振り上げ男の肩先に振り下ろした。男は「うっ」と漏らしたうめき声と共に片膝がガクンと崩れながら、傍に縛られて転がっていた新平に躙り寄り、切っ先を新平の喉に突きつけた。
「近寄るな! 拙者に近寄ると、このガキの喉を突く」
「わかった、あんさん止めなはれ、子供が恐がっていますやないか」
「煩い、近寄るなと言うに」
その時、コン太が小屋に跳び込んできた。驚いて怯んだ男の刀の下に天秤棒を差し込んで、そのまま上に跳ね上げた。それでも觀念せずに男は新平を掴もうとしたが、亥之吉の天秤棒が男の脳天を直撃した。男は頭を抱えて気を失った。
「新平、恐かったやろ、いま縄を解いてやるからな」
新平の縄を解く亥之吉の傍で、コン太が疲れ果てたのか、コテンと横に倒れた。
「コン太、大丈夫か」
縄を解いて貰った新平が、自分のことは忘れてコン太を気にかけている。
「新平、無事か、よかったなあ」
三太が小屋の中を覗きこんだ。
「あっ、親分、コン太が…」
三太が小屋に入り、コン太を抱き上げた。
「大丈夫や、ようけ走ったから、疲れているだけや」
三太は、手ぬぐいでコン太の汚れを拭ってやると、自分の懐へ押し込んだ。
「コン太、お手柄やったなあ、寝てもええで」
男は、子供を拐かしたとして、番所に突き出した。どこの藩かもわからないので、若様暗殺計画の刺客だとも言えず、あとは代官所で自白させてもらわねば仕方がない。多分、男は自白しないであろう。
「わい等の知らない侍の世界の話や」
三太と新平は、目の上のたんこぶ、亥之吉を伴って江戸への旅を続けた。
三太は、新平と亥之吉に聞こえないようにコソコソ話している。
「なあ新平、わい等旅を楽しんでいたのに、若様なんか助けたばっかりに、とんだ災難やったなあ」
「恐い目に遭った、あのまま断って二人で旅を続けとったら、もっと楽しい旅でしたのにね」
「もう、お店に奉公しとるのと同じや、何も自由にはできしまへん」
先を歩いていた亥之吉が振り返った。
「じゆうが、どうしたんや?」
「いえ、後三年しないとじゆう歳にならへんと…」
「奉公が、どないしたんや?」
「歩いている方向はこれでええのやろかと…」
「東海道を東へ歩いているのや、アホでも方向を間違えたりするかいな」
「それで安心しました」
「嘘をつきなはれ、わいと一緒に旅をしたら奉公しているのと同じで自由がないと言ったのですやろ」
「何や、聞こえていたのやないか」
「わいは老耄(おいぼれ)やあらしまへん、耳はちゃんと聞こえとります」
三太は亥之吉に提案した。
「吉原宿で、一泊しましょうな」
「あきまへん、お天道さまはまだあんなに高いのや、あと四里や五里は歩けます」
「わっ、地獄や、今から五里も歩くのやて」
「そうだす、宿は三島宿で取ります」
「あっ、三島やて、旦那様さま、何か企んでいまへんか?」
「企むて、何を?」
「大人の男が考えることだす」
「三島の宿で、女郎買いでもする積りやと言いますのか?」
「子どもたちに向かって、えらいハッキリ言いますのやな」
「女郎の居る宿場で、大人の男が考えること言うたら、それぐらいですやろ」
「わい、子供やから、ようわかりません」
「そうか、わからへんやろな、じょろ言うたら、植木に水をやるもんや、それを買うことがじょろ買いだす」
「そんなもん買うて楽しいのですか?」
「そら、男の第一の楽しみだす」
「嘘ですやろ、女を買うて抱くことですやろ」
「それみろ、分かっていて言うとるのやないか」
上方の人間が二人寄れば、掛け合い漫才になると言われている。それにしても師匠と弟子の会話にすれば、あまりにもあけすけで無遠慮である。
「ほんなら、三島で泊まっても、何処へも行かへんのですか?」
「そら、行くけど… わいの女房に言い付けたらあきまへんで」
「言い付けたりしまへん、女郎買いで、息抜きをしたやなんて…」
「嫌な小僧やなあ、先が思いやられるわい」
喋りながら歩いていると、後ろから忍者走りで三人の男がつけてきた。亥之吉がキッと構えたが、男たちは亥之吉たちを追い越してしまった。
「あんさん達、ちょっと待ちなはれ、若様の命を狙う刺客でっしゃろ」
男たちは「ギクッ」として立ち止まった。
「誰だ、お前たちは?」
「へえ、富士川で刺客を捕らえる手伝いをした者でおます」
「お前たちか、仲間七人を縄目にしたやつは」
「いいえ、八人だす」
「仲間の仇だ、序にお前達の命は貰って行く」
「鎌をかけてやったら、あっさりと白状しましたな」
「洒落臭せえ、殺ってしまえ!」
一斉に剣を抜いて亥之吉に向けた。新三郎が加勢しようとしたが、亥之吉の気迫に押されてしまった。
「三太、真剣勝負だす、よく見ておきなはれ、天秤棒はこうして使うのです」
亥之吉は天秤棒を両手で持って、右上から左下に斜めに構えだ。
「コヤツ、出来るぞ、気をつけてかかれ!」一人の男が叫んだ。
亥之吉は咄嗟に読んだ。三人同時に斬りかかって来れば、味方を傷付ける恐れがある。まず一人が突っ込んでくる。亥之吉が一人に感けていると隙が出来てしまう。そこを後の二人が斬り込んでくるだろうと。
亥之吉は虚を突いて、切り込んできた男を飛び退いて避けると、後に控えていた男の一人の肩を責めた。肩を打たれた男は「どっ」と倒れた、もう一人の控えていた男は驚いて隙をみせた。
一人目の男を倒した天秤棒が、その反動で上段に跳ね上がったかと思うと、二人目の男の脳天に振り下ろした。
「三太、天秤棒は武器ではなくて武具です、一対一では決して自分から攻めることはおまへんのやが、相手が三人なら先手も仕方がないことです」
二人を自分から攻めた弁解とも見られたが、これも我が身を防御する手段なのだろうと三太は感じた。
亥之吉は残る一人と向き合った。天秤棒を斜に構えて亥之吉はピタリと動きを止めた。対する相手は腕に自信があると見えて、怯む気配はない。先程は逃げられたので、逃すまいとにじり寄ってくる。亥之吉の天秤棒が相手に届くところ近寄ってきたが、それでも亥之吉は動かない。
さらに、相手の剣の切っ先が亥之吉に届くところまで来ると、上段に構えた相手の男の手首がピクリと動いた。
「来るのやな」
亥之吉の天秤棒の上先が、少し後ろへ引いた。それを合図のように相手が踏み込んできて、剣を振り下ろした。その瞬間、亥之吉の天秤棒が風を切った。
「ブーン」と風を切る音が聞こえて亥之吉が後ろへ飛んだ。三太には何が起きたのかわからなかっが、相手の男が「どすん」と倒れた。
「三太、よろしいか、相手を焦れさせるのも戦術だす」
三太は、旦那様の強さを自分の目で確かめて、何があってもこの人について行こうと決心した。
倒した三人は怪我をしていて、若君の後を追えないだろうと、このまま捨て置くことにした。
第三十七回 亥之吉の棒術(終) -次回に続く- (原稿用紙15枚)
「チビ三太、ふざけ旅」リンク
「第一回 縞の合羽に三度笠」へ
「第二回 夢の通い路」へ
「第三回 追い剥ぎオネエ」へ
「第四回 三太、母恋し」へ
「第五回 ピンカラ三太」へ
「第六回 人買い三太」へ
「第七回 髑髏占い」へ
「第八回 切腹」へ
「第九回 ろくろ首のお花」へ
「第十回 若様誘拐事件」へ
「第十一回 幽霊の名誉」へ
「第十二回 自害を決意した鳶」へ
「第十三回 強姦未遂」へ
「第十四回 舟の上の奇遇」へ
「第十五回 七里の渡し」へ
「第十六回 熱田で逢ったお庭番」へ
「第十七回 三太と新平の受牢」へ
「第十八回 一件落着?」へ
「第十九回 神と仏とスケベ 三太」へ
「第二十回 雲助と宿場人足」へ
「第二十一回 弱い者苛め」へ
「第二十二回 三太の初恋」へ
「第二十三回 二川宿の女」へ
「第二十四回 遠州灘の海盗」へ
「第二十五回 小諸の素浪人」へ
「第二十六回 袋井のコン吉」へ
「第二十七回 ここ掘れコンコン」へ
「第二十八回 怪談・夜泣き石」へ
「第二十九回 神社立て籠もり事件」へ
「第三十回 お嬢さんは狐憑き」へ
「第三十一回 吉良の仁吉」へ
「第三十二回 佐貫三太郎」へ
「第三十三回 お玉の怪猫」へ
「第三十四回 又五郎の死」へ
「第三十五回 青い顔をした男」へ
「第三十六回 新平、行方不明」へ
「第三十七回 亥之吉の棒術」へ
「第三十八回 貸し三太、四十文」へ
「第三十九回 荒れ寺の幽霊」へ
「第四十回 箱根馬子唄」へ
「第四十一回 寺小姓桔梗之助」へ
「第四十二回 卯之吉、お出迎え」へ
「最終回 花のお江戸」へ
次シリーズ「第一回 小僧と太刀持ち」へ