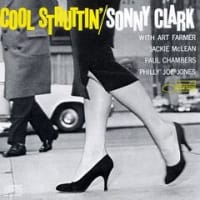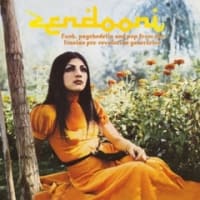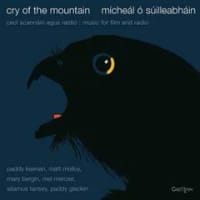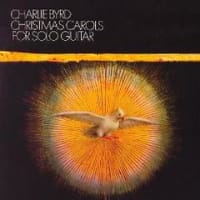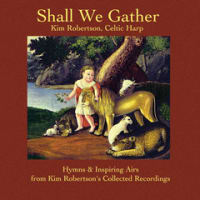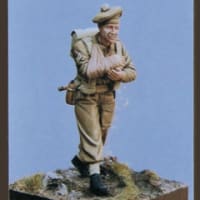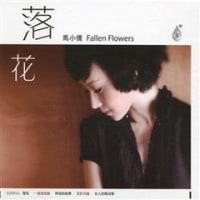”Hingus”by Sven Grunberg
バルト三国はエストニアのシンセサイザー奏者、1981年度作品。もはや古典的名作でしょうか。まあ、いずれにせよ、マニアしか聴いちゃいない盤なんだが。
なぜか分からないが、ひどい雨に降り込められた夜など、決まってシンセサイザー音楽を聴きたくなる。それも一人宅録でじっとり作り上げられたようなオタク臭の漂う奴が良い。
さんざんへんてこりんな動きをした挙句、台風は本土上陸をすると決めたようで、今は関西方面に照準を定めている。紀伊半島あたりの大変な被害予測など訊くにつけても、中上健次の紀行文集、”紀州”など、もう一度読みたくなったりしている。いや、新宮とか那智勝浦とかの地名を聞くたびに中上の顔が浮かび、「俺って、そんなに中上のファンだったっけ?」と不思議になるが、何のことはない、私は中上とその作品を通じてしか紀州について知らないのだった。
というわけで、夕刻から降り始めた極太の雨音と混ざり合うように、Sven Grunberg のシンセサイザーが鳴り続けている。
シンセの機材に関する知識など、私にはないに等しいのだが、30年も前の作品となると演奏センスとともに、やや古めかしい部分も出て来ているのではないか。アタックを効かせて衝撃音を響かせる、あるいはミステリアスにメロディをうねらせる。そんな折々に、なにやら昔のSF映画を見ている時のような時代のずれを感ずる。それは辺地を行く蒸気機関車を見て「かっこいい」と感ずる感性があるように、この作品の、むしろ魅力となってはいるのだが。
SF映画を連想してしまうのは、この印象的な星雲の天文写真をジャケに使っているからもあるのだが、ともかく硬質で透明感のある美学を芯に置いて描く音世界は遠方の星々に寄せる思いに良く似合う。このあたりは北国のミュージシャン独特の詩情かとも思うのだが。ともかく深々と鳴り渡る電子音が、果て知れぬ宇宙の暗黒を渡って行く冷え冷えとした美しさはたまらない。
Sven Grunbergは東洋の文化に惹かれていたらしく、インド音楽や東洋思想にかかわる作品を書いたりしていたが、あまり露骨にその趣味が正面に出てこないのが趣味のよろしいところだろう。それでも、この作品にもやはり、アジアの民謡で使われる音階に近いものが所々に顔を出し、不思議なエキゾティック感をかもし出す。それが生み出す、ある種チャーミングな効果を、作者はどこまで自覚していたか。
などと言っているうちに雨は上がっていたが、もちろん台風はこれからが本番なのである。さらに宇宙の旅を続けることとしよう。