重信房子
~ビートたけしの作品に思う~
☆初めに☆
重信房子が出所した時、彼女や連合赤軍のことについて書かないのかという問い合わせを何件かいただきました。私が重信房子について知ることは何もない。ただ、連合赤軍や「新左翼」へ勝手放題言ってる連中に、反論することは山ほどあります。そしてなぜ、ビートたけしなのか。諸作品を貫く心情が、余りにも近くに思えるからです。
1 離陸には成功した
少し前の話だ。思いがけない場所(東京)で、50年前のことが議論になった。相手は日大出身、それもバリバリの体育会系だった。まさかオマエは全共闘かと迫って来たこいつに、私は、当ったり前だ!と肩を入れた。ここで会ったが百年目、いや50年目だった。とりあえず、当時の応援団・体育会系のやったことが話題になった。日大当局からの体育会系に対する手厚い保証・保護については、2019年の悪質タックル事件を思い起こしてもらえばいい。私は、体育会系の連中が、学生(どっちも学生だが)に対していかにひどいことをしたかを責めた。しかし、この男は、それをやったのは全共闘だ、お陰で主将の指はちぎれたんだ、と反論した。何より、この男は現場にいた。私は日大という場所にいない所からの反論だった。押し問答の様相となった。
仲裁が入って半端な終わり方になったが、このあと私は反省した。日大闘争の大変な局面はともかく、きっかけとなったのは、東京国税局が暴いた34億円の使途不明金である。また、発覚直後、大学の会計担当主任が自殺したことだ。そのことからどうして話さなかったのか。こいつが裏口入学のあっせんをしていたかどうかは知らない。しかし当時、ひとりあっせんすれば10万円というリベートが、学生には極上のバイトとなっていたのは、この手口を知る連中には公然の秘密だった。日大闘争が起こると、今まで日大卒を「恥じ」としていた埴谷雄高や宇野重吉(寺尾聡のお父さん)たちが、連帯の声明を送る。
日大闘争が最も端的な「全共闘」だった。私たちは極めて当たり前な疑問を解明しようとした。すると思いがけないほど大きな問題が立ち現れた。これが全国に共通する全共闘の展開だったはずだ。立ち現れたひとつに、私たちが大学の「顔」と思っていた教授たちの、「そんなことは知らない」「生意気を言うな」等という、居丈高で無知な姿勢があった。これが戦後「民主化」されたはずの場所で起きているという事実に、おそらく私たちは驚き呆れたのだ。ベトナム戦争が身近だった当時、私たちが「反戦」を言えば、この連中は「何を甘ったれた」「簡単に戦争反対などど言うな」と言った。今も思うが、終戦、あるいは敗戦を受け止めず、ちゃっかり「戦後/未来」に向き合う男たちは、私たちにむかって「戦争の厳しさも知らないで」と、白い眼をむいた。その姿には、日本の今があるのは誰のお陰だと思ってるかと言いたげな、恥知らずの誇らしさがあった。そうではない、戦争への忌避感に満ちていた女たちのそばに、私たちはいたはずである。
こうして私たちは、地上から羽ばたいた。しかし、着地点を見出すのは困難だった。私たちは繰り返し「これは違う」「ここではない」と言い続けた気がする。
2 ノンセクト(無党派)≠ノンポリ(我関せず族)
ここでも日大が分かりやすい。1968年9月30日の大衆団交の席上で、責任を取って「辞める」とした古田会頭の辞任表明が、翌日の首相(佐藤栄作)介入で撤回された。親分とは言っても、たかだか大学の親分の問題に、国の親分が介入した。しかし、日大は「まだいい」。多くの大学での告発は「無視」された。その時どうするのか、私たちの道は分かれた。
当ブログ114号で書いたことで再検証してみたい。教師たち、あるいは教師を目指した者たちが、その時どうしたか。ひとつに、国から自由ではない学校・教育は要らない、と街頭に「散った」ものたちがいた。逮捕されれば、当然のごとく解雇された。「不当解雇撤回」運動が起きるが、運動の「正当性」を証明するのは革命だけだ。これは「子どもを置き去りにした」運動だったと思える。反戦闘争という視点で言えば「日本では何も出来ない」という「日本を置き去りにする」過激なあり方が、それにあたる。
**たとえば1972年、イスラエルのロッド空港で銃を乱射し、丸腰の民間人を殺した岡本公三たち日本赤軍がそうだった。重信房子が謝罪したのは、それ等の事実に対してである。
大学闘争・教育闘争・反戦闘争、すべてが揺れ動き、分岐を余儀なくされていた。こういう流れに対し、連合赤軍の「あさま山荘事件」やリンチ殺人事件で「失望した」人たちが、急速に運動から遠ざかった、などのエラそうな評論があとを絶たない。何をかいわんや、みそ汁で顔洗って来い、一昨日来い、である。どうせこいつらの大学時代は、闘争に知らぬ顔を決め込んで、「僕たちノンセクトは」などと自らの「ノンポリ性」を人知れず恥じつつ、素顔に頬かむりして来たクソどもに間違いない。弱者がいくら声を張り上げても、それが小さくなる辛さ悲しさを、こいつらは過去においても今も知ることはない。
私たち、いや私は、言われるところの「絶望の学校」で、子どもたちがどう生きているのか知りたいと思った。そして、子どもたちと共に生きていけるとしたら、それは面白いはずだと思った。いい教育(先生)・悪い教育(先生)が、子どもの将来を決定しているというのは違う、と思った。実際、学校現場に行ってみると、そこには「学校も教師も大嫌い」ではあっても、魅力あふれる生徒・子どもがたくさんいた(もちろん「学校大好き」もたくさんいた。念のため)。「教室では何も出来ない・守れない」と考える以前に、学校現場での現象は複雑な現れ方をした。不愉快なものも多かったが、極めてストレートで気持ちいいものもあった。やっと「場所」を見つけたと、私は思った。
3 「バカヤロウ」という場所
ビートたけしの作品で、私は『キッズリターン』が一番好きだ。自身のバイクで自爆し、瀕死の重傷を負った後の作品だ。

特に図抜けたワルでもない、学校にして見れば十分厄介だが、他愛のないいたずらで明け暮れる二人の高校生の物語だ。その度に呼び出される職員室では、長々とした説教ー「人として」「社会というものは」ーという、当たり前で分かり切ったフレーズが充満する。「仲間の一杯いる職員室」という空間での、退屈でウソに満ちた在り方こそ二人のいたずらの動機となっていることを、多くの大人(「社会」と言ってもいい)は決して理解することが出来ない。いたずらに対し、ある時はたしなめ、ある時は笑い転げる同級生は、二人を「見守っている」のではない、私たちの「シンパ」と呼んでいたところの「共感」なのだ。
やがて二人は、ヤクザとボクサーというそれぞれの「道/場所」を見出し、歩み始める。しかし、「退屈とウソ」から決別したはずの二人は、やがて「違う」「ここではない」と思い始める。挫折して戻ったのは、前の学校の校庭だった。寒い校庭を、自転車で二人乗りする姿が切ない。それを窓から見下ろす教師が、「あいつら、まだあんなことやってる」と呆れたように、ざまを見ろとでも言うようにつぶやくのだ。
☆後記☆
とんでもなく暑い6月が終わり、7月になりました。第27回「うさぎとカメ」、二週間後ですよ~ 天候さえ許せば、なんと公園デビューです!

そして、これは2回目となりますが、「吉野家」さんからのご厚意で、値上がり真っ最中の牛丼の提供となりま~す
これはチラシ裏側。前回のレポートとなります。読んで下さい。近くで(遠くでも)これを読んでる方、いらしてください!

☆☆
オオタニさ~ん、やっぱりやりました! 昨日はボールの判定に、少しメンタル乱したかな? そして、あとひとりを投げたかったという気持ち、滲み出てましたね~。でもやっぱりスゴイ! 月間МVP間違いないんだとか。今日は休み。痛めた腰を、ゆっくり直してね!










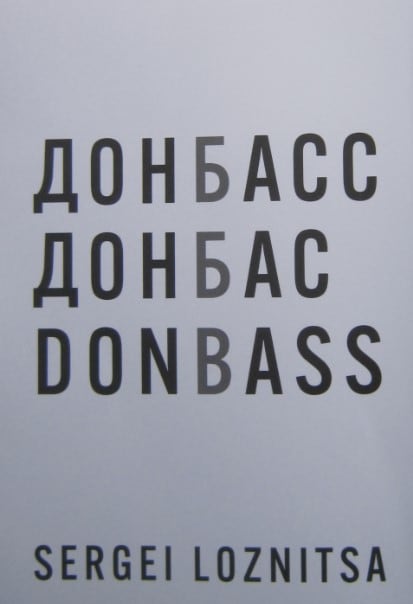























 ゆっくり、ゆったりと行こうネ
ゆっくり、ゆったりと行こうネ
