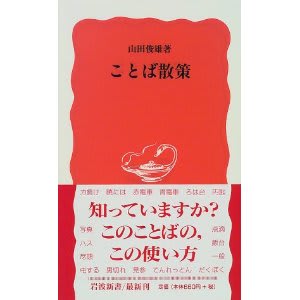
本書のねらいは、著者が幼少の頃、父母によって育まれた言葉を回顧し、また家庭の外で得た言語体験を懐旧の念で記憶のなかから取り出し、それらの作業から現代の日本語の激しい変容をいかに観察しうるか、文献のなかにそれをもとめて記録する作業である。それは、言葉が変化していく現象をとらえて記録し、語誌に役立てることでもあるという。「あとがき」で述べられている詞の世界の、著者の散策法である。
構成は次のようになっている。「追憶の中のことば」「漢語の素養」「近い過去・遠いことば」「誤用・俗用・正用」「語誌探求」。著者の研ぎ澄まされた言語感覚が随所に示されている。父母によって育まれた言葉としては、「おんぼりと(何の気兼ねもなくの意)」「はがやしい(もどかしい、じれったいの意)」「はだこ(肌に直につける下着)」「飯台(食卓のこと)」などの言葉があげられている。
巷間に、「住みづらい」「生きづらい」という言い方がよくされるが、そのような言い方はかつてはほとんどなかった、「住みにくい」「生きにくい」である。「寝台」は、いまはみな「しんだい」と読むが、むかしは「ねだい」だった。最終電車を昔は「赤電車」といい、そのひとつ前の電車を「青電車」と言った。公園などにある長いベンチは、「ろは台」と言われていた。漢字・漢文の常識の退廃にも、言及している。
他にも、興味深い話がたくさん。言葉の変容が大正、昭和、平成の国語辞典の項目や記述に、また古典的小説のなかに証言をほりおこされている。
本書はエッセイ風に編まれ、それゆえに指摘が断片的だ。著者のこの分野での業績をもっと体系的に知りたいものだ。
最新の画像[もっと見る]




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます