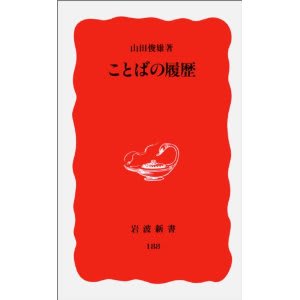
過去から現在にいたる日本語の「ゆらぎ」を考察。日本語の奥行きの深さは、いろいろな側面から語ることができるが、言葉をひとつひとつとりあげて、その変遷をたどるという視点はわたしにとっては得難いもので、勉強になった。
たとえば、「電覧」という言葉があり、この言葉自体がいまはもう使われないもので、その意味は「人がもの見ることに対する敬語」であるにもかかわらず、「ひととおりざっと目を通す」という意味で使っている人がいる。
ときおり目につく「店がはねる」「芝居がひける」などの誤った言い方にも苦言を呈している。もともと「ツルノハシ(鶴嘴)」だったのにいまは省略形で「ツルハシ」になってしまっている。平清盛は「たいらのきよもり」で「の」が入るが、足利尊氏は「あしかがたかうじ」で「の」は省略されている。このような省略を、著者は「無用の合理主義」と呼んでいる。
他にもたくさんの指摘がある。このようなことができる能力をもった人はそうはいないので貴重だ。著者は、敏感な触角で、文献、小説などにあらわれる言葉の蒐集を行っては、辞典(『言海』『大言海』『広辞苑』『広辞林』、さかのぼっては『日葡辞書』『ヘボンの辞典』『節用集』)にそれがあるのかないのか、どのように整理されているのかを検証している。
それでは、「闇から牛」「三十一字」は、本当は何と読むか。「言語同断」は間違いだろうか。(「やみからうし」「みそひともじ」ではない)。トランプの「ジャック」は日本語ではどう表現したらよいのか(「キング」は「王」、「クイーン」は「王妃」)。正解は本書で。
最新の画像[もっと見る]




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます