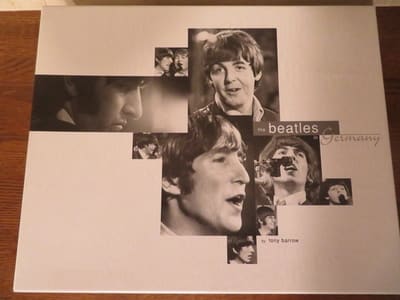盛り上がってよかったけど、幹事で疲れた。

本書は、書店で見つけた。
古代史講義の第二篇。
戦乱にフォーカスした。
前回の九州旅行で行った磐井の乱から、前九年の役と後三年の役まで。
古代で、戦乱と呼ばれるものはほぼカバーされている。
15編からなっており、古代の戦乱と呼ばれているものについては、ほぼカバー。
よく取り上げられているものもあるし、あまり注目されていないものもあるが、本書を読んで言えるのは、各々の戦乱の解釈が大きく、時代によって変化していること。
例えば、平将門の乱と、藤原純友の乱が呼応していたという説が一般的であったが、よく見るとそれはありえないとか。
従来の説によった教育を受けてきた我々にとっては、こんなに解釈が変わっているのかと驚かされるところも多い。
それだけ、新たな発見があったということなのだが、従来の説に盲従していた部分もある。
本書は、気鋭の学者が各々の章を担当しており、長くはないが、読み応えがあるし、説得力もある。
古代史を知りたい人には打って付けの本ではないか。
戦乱史だから、ダイナミックで読み易い。
続編に期待するが、次は、何を軸にするのか?