昨日はJMAのセミナーでした(参加者の皆さん、お疲れ様でした)。そこで取り上げた小話をご紹介します。「ほとんどの処理委託契約書に、排出事業場が書かれていますが、これは不要である」という話です。
施行令第6条の2では、
****************
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
****************
が法定の記載事項として挙げられています。しかし、「排出の場所の所在地」を記載しなさい、という規定はありません。
ということで、排出事業場を記載する必要はありません。それどころか契約はサイト、工場ごとに結ばなくてはならないと勘違いされていることがあります。契約は法人と法人で結ぶものなので、工場長印であったとしても、会社としての契約になります。
つまり、A工場の工場長が印鑑を押した場合、同じ契約書にのっとってB工場の廃棄物の処理委託もできるということです。他の工場で良い業者さんと付き合いがあるらしいので、ウチの工場でも取引することにしました、なんていうケースがこれです。
そんなとき、排出事業場名が記載されていたら、覚書を追加しなくてはならないと思われるかもしれません。しかし、これは法定記載事項ではないので、別に記載内容が不十分でもかまいません=追加しなくてもよいのです。
であれば、排出事業場なんて書かずに、本社が主体となって契約したほうがよい、という考え方もあります。もちろん、管理しやすいようにあえてサイトごとに運用することもできます。皆さんの状況に応じて判断してください。
※収集運搬の契約書では、積み込み地(排出事業場の管轄自治体)の許可証の添付が必要です。間違いのないように運用できるようにしてください。
施行令第6条の2では、
****************
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
****************
が法定の記載事項として挙げられています。しかし、「排出の場所の所在地」を記載しなさい、という規定はありません。
ということで、排出事業場を記載する必要はありません。それどころか契約はサイト、工場ごとに結ばなくてはならないと勘違いされていることがあります。契約は法人と法人で結ぶものなので、工場長印であったとしても、会社としての契約になります。
つまり、A工場の工場長が印鑑を押した場合、同じ契約書にのっとってB工場の廃棄物の処理委託もできるということです。他の工場で良い業者さんと付き合いがあるらしいので、ウチの工場でも取引することにしました、なんていうケースがこれです。
そんなとき、排出事業場名が記載されていたら、覚書を追加しなくてはならないと思われるかもしれません。しかし、これは法定記載事項ではないので、別に記載内容が不十分でもかまいません=追加しなくてもよいのです。
であれば、排出事業場なんて書かずに、本社が主体となって契約したほうがよい、という考え方もあります。もちろん、管理しやすいようにあえてサイトごとに運用することもできます。皆さんの状況に応じて判断してください。
※収集運搬の契約書では、積み込み地(排出事業場の管轄自治体)の許可証の添付が必要です。間違いのないように運用できるようにしてください。










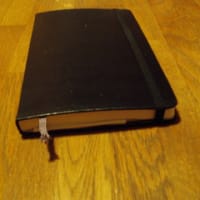

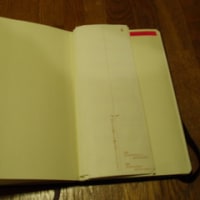

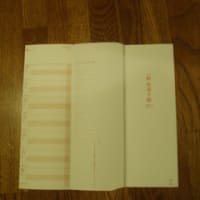






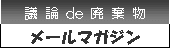





たとえば、排出事業者がガラ陶を排出したことにともない、収運業者A、破砕業者Bと各々契約を締結をし、その後、破砕したガラ陶に関しても収運業者C、最終処分業者Dと契約を各々締結する(排出事業者はガラ陶の処理に関してABCDと契約を締結)ことは法律上可能であると解してよろしいでしょうか??
(BがC、Dと契約するのが通常ですが・・・)
排出事業者がABCDと契約することは問題ないと思います。廃棄物処理法上の義務はA、Bまでですが、C、Dと契約することを妨げるものではありません。
ただ、それとは別に、BはC、Dと契約しなければならないのではないでしょうか。法第12条第3項の主語は、中間処理事業者含む「事業者」ですから。
ホリロー先生、いかがですか?
事業者(中間処理業者を含む)、産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む)という「含む」という意味は、包含関係(数学的にはベン図)を示しており、中間処理業者は中間処理産業廃棄物しか委託できないが、事業者は産業廃棄物および中間処理産業廃棄物の両方を委託可能であるという「含む」の意味と考えるからです。
あくまでも自分の理解ですので、間違っているかもしれませんが・・・
コメントありがとうございます。しばらく書き込みがないので、寂しく思っていたところです。
私は、どちらが正しいのか断言するのは難しいように思います。ただ、BがCDと契約しない場合、マニフェストの交付者はAになると思います。Aがそこまで管理をしたいというのであれば、Bに委託した業務は処分というより破砕という加工であると考えて良いと思います。
破砕という加工後のものをAに返却し、再度Aの責任で処理委託するという形です。そう考えれば、BがCDとの契約をする必要はないように思います。
しかし、Aさんはなぜそんなことをしたいのでしょうか。。。
ということは、中間処理業者Bは、中間処理産業廃棄物をCやDに委託していないということですね。中間処理産業廃棄物の排出事業者は、もともとの排出事業者ということですから。それであれば、中間処理業者BからC、Dに引渡される場合のマニフェストも、当然、排出事業者名で交付されるというのがわかります。
でも、これって、ある中間処理産業廃棄物の中に含まれる排出事業者の廃棄物の割合が100%のときに限りますよね。
最近、企業も環境問題に非常に熱心に取り組んでおり、
たとえば大手企業は廃蛍光管を破砕処分して最終処分まで一括して管理(ABCDと処理委託契約書締結)したいと考えております。
というのも、中間処理業者であるBが不法投棄した場合、排出事業者責任で措置命令対象になるリスクを減らすためです。
ほとんどの自治体では行政処分をした場合、HPで業者名を公表することから、企業ブランドが著しく傷ついてしまいます。
このことから考えて、このようなケースは今後ますます増えていくのではないかと考えています。
大手企業への立ち入り、お疲れ様です。ちなみに、アスパラ様はどちらの自治体の方ですか?差し支えなければお聞きしたいものです。
さて、チビローの言うとおり、その運用は中間処理産業廃棄物が100%A社のもので構成される場合が前提だと思います。
廃蛍光管は、おそらくそうではないでしょう。C、Dと契約したところで、形だけは責任ある契約に見えますが、マニフェストの運用も含め、実態としてはこれまでと何も変わらないと思います。そうであれば、不法投棄されるリスクは減らないでしょう。
そこにエネルギーを使うくらいなら、措置命令要件に当てはまらないようにしっかり管理したほうが良いと思います。
いろいろと議論をくりひろげられてよかったです。
所属している自治体のことですが、
このブログを多数の方がみているということもあり
差し控えさせてください(すみません・・・)
ただ、不法投棄が多く、悪徳産廃業者が多い県であるということだけ申し上げておきます。。。