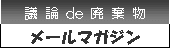http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/acdd376c0c59dfc779a3430cae194efcの記事に掲載した通知は、現在の環境省の見解とは異なるのかなと感じています。
先般、環境省を訪問して再委託に関する質問をぶつけに行きました。
そうしたら、ある行政官が「処理の委託はあくまでも排出事業者が行うもの。中間処理業者から最終処分業者へは、委託基準とマニフェストの運用は適用されるが、処理委託とはならない」という趣旨を説明されたからです。
これは、平成17年9月30日付けの環境省通知【環廃対発第050930004号、環廃産発第0509300005号】を受けての発言かと思うのですが、やたら「処理委託ではない」ということを強調していました。
この指摘が現在の環境省の解釈であれば、前の通知とは解釈が違うということになりそうです。前の通知は平成6年、今回の通知は平成12年改正の趣旨をふまえてのものですから、平成12年以降に解釈の変更があったのかもしれません。
先般、環境省を訪問して再委託に関する質問をぶつけに行きました。
そうしたら、ある行政官が「処理の委託はあくまでも排出事業者が行うもの。中間処理業者から最終処分業者へは、委託基準とマニフェストの運用は適用されるが、処理委託とはならない」という趣旨を説明されたからです。
これは、平成17年9月30日付けの環境省通知【環廃対発第050930004号、環廃産発第0509300005号】を受けての発言かと思うのですが、やたら「処理委託ではない」ということを強調していました。
この指摘が現在の環境省の解釈であれば、前の通知とは解釈が違うということになりそうです。前の通知は平成6年、今回の通知は平成12年改正の趣旨をふまえてのものですから、平成12年以降に解釈の変更があったのかもしれません。










 問10
問10