昨日に引き続き、排出事業者が誰になるのかというテーマです。
参考となる考え方として、建設工事の例を挙げたいと思います。建設工事で排出される廃棄物については、基本的には元請業者が排出事業者になるということは比較的よく知られています。関連する通知として以下の3つが挙げられます。
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)
平成13年6月1日
環廃産276号
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について
平成11年3月23日
衛産20号
建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について
平成6年8月31日
衛産82号 [改定]
平成10年11月13日 衛産51号
通知によると、原則は元請が排出事業者ですが、下請けに業務のほとんどの部分を委託している場合(通知では分離発注などといわれています)は、下請けが排出事業者になりうるとも書かれています。元請と下請けの両方が排出事業者と考えることもできるようです。(どの通知にも、同じようなことが書かれています。)
その廃棄物を最も適切に管理できる立場にあるのは誰か、そしておそらくは誰が占有者であるかが重要な判断基準になっていると思います。適正な処理を確保するためには、そのような基準を重視するのは妥当と考えられます。またこの通知は、判例を反映していると思われます。
この通知で書かれているのは、建設工事に際しての判断基準の例ですが、それ以外のシチュエーションでも「適正処理の確保」という観点から、排出事業者が誰であるかを考えることになると思います。その場合、必ずしも「所有権」は重要ではないと思います。そもそも、廃棄物に所有権を主張する人はいないのですから。。。
参考となる考え方として、建設工事の例を挙げたいと思います。建設工事で排出される廃棄物については、基本的には元請業者が排出事業者になるということは比較的よく知られています。関連する通知として以下の3つが挙げられます。
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)
平成13年6月1日
環廃産276号
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について
平成11年3月23日
衛産20号
建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について
平成6年8月31日
衛産82号 [改定]
平成10年11月13日 衛産51号
通知によると、原則は元請が排出事業者ですが、下請けに業務のほとんどの部分を委託している場合(通知では分離発注などといわれています)は、下請けが排出事業者になりうるとも書かれています。元請と下請けの両方が排出事業者と考えることもできるようです。(どの通知にも、同じようなことが書かれています。)
その廃棄物を最も適切に管理できる立場にあるのは誰か、そしておそらくは誰が占有者であるかが重要な判断基準になっていると思います。適正な処理を確保するためには、そのような基準を重視するのは妥当と考えられます。またこの通知は、判例を反映していると思われます。
この通知で書かれているのは、建設工事に際しての判断基準の例ですが、それ以外のシチュエーションでも「適正処理の確保」という観点から、排出事業者が誰であるかを考えることになると思います。その場合、必ずしも「所有権」は重要ではないと思います。そもそも、廃棄物に所有権を主張する人はいないのですから。。。










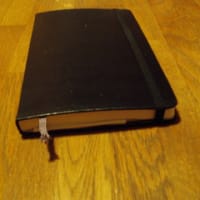

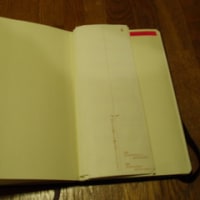

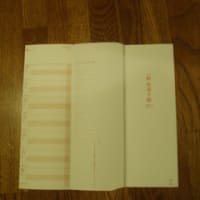






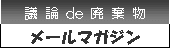





さて、排出事業者が誰になるのかと言うことに関して、悩んでいることがございます。
工場のプラントで使用している触媒等が不要となり廃棄する場合で、抜き取り作業を外部の業者(廃棄物処理許可業者ではない者)に発注する際に、抜き取り後の触媒等の廃棄処理も合わせてその業者に発注して、その業者に排出事業者になってもらうということは、法的に問題無いでしょうか。
また、プラントの解体工事と合わせて不要触媒等の廃棄処理を発注する場合ではどうでしょうか(建設工事の場合は原則として元請業者が排出事業者になるとのことですが、こういった物についても建設廃棄物と考えてよいのでしょうか)。
以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
排出事業者の問題については、明確な区分ができないところがどうしても残ります。
そこで、皆さんがよくされている考え方を引用しながら考えたいと思います。
・抜き取り作業の外注ということであれば、その業者さんは単なる作業を受託したに過ぎません。つまり、作業の主体はあくまで貴社で、業者さんは貴社の手足に過ぎないということになります。これは、建設工事における元請と下請けの関係に似ていると思います。従って、排出事業者は貴社と考えることができます。
・もし仮に、触媒の納入業者さんが、入れ替え作業も含めて業務を請け負っているのであれば、納入業者さんの廃棄物と考えることができるかもしれません。入れ替え作業の責任を主に負っているのが納入業者さんだからです。これは下取りの考えに近くなります。
・プラントの解体で出てくる触媒は、微妙です。建物の解体工事に先立っては、その建物内の不要物は基本的に事前に処理されることが期待されています。家電製品などがよい例です。この触媒がそれに該当するかどうかは判断の分かれるところだと思います。
ただ、やはりプラントそのものと、消耗品?の触媒は別物と考えることが出来ます。リスク管理の観点からは、適正処理先の確保をするためにも、事前に貴社が処理をされたほうが望ましいと思います。
<注意>
判例も基本的にはこの通知以上のことがありませんので、上記いずれについても解釈としてどれが正しいかは、議論はできても結論付けることができません。リスクの低い方法は何かということも視野に入れて運用することが重要と思います。
よろしくお願いいたします。
さて、上記掲載文では「排出業者は元請業者」となっていると思いますが、発注者が別途産廃処理業者と契約を結んでいる場合で、工事で発生する産廃の量が少ない場合等において、発注者が廃棄物を引き取り、別途処分するのは駄目なんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
元請業者が排出事業者となる、という根拠はいくつか考えられると思います。例えば、
①工事は、元請業者の事業活動と考えられる
②工事発生の廃棄物は、元請業者が責任を持って管理するのが、最も無理なく、適正処理を確保しやすいため
③逆に、発注者は工事をしたことがなく、その排出者責任を負わせるのは、酷である
等が考えられます。どれも似たような理由ですが。判例も通知もこのような考えに基づいて、元請を排出事業者としているのだと思います。
しかしそもそも、事業者間の契約が先にあって、その契約に基づく事業活動から廃棄物が出てくるのです。つまり、契約内容を踏まえて、それが誰の事業活動であるかを考えることになるのです。
したがって、「発注者が工事発生廃棄物を管理するだけの知識、能力がある」といえる場合が条件とは思いますが、「純粋に工事だけを発注している=結果として出てきた廃棄物は発注者が管理する」という契約であれば、発注者の廃棄物と考えることは可能だと思います。同様の見解を他の方からも聞いたことがあります。
私が責任を取れるのであれば、こんな解釈で運用するかもしれません。しかし、つまるところ解釈論ですので、みなさんに保証できません。
ご心配であれば、地元自治体にご相談されるとよいでしょう。多分「排出事業者は元請です」といわれるでしょうけど。
私の事業所で最近このような議論が出ており、色々悩んでおりました。
当社には「産業廃棄物処理マニュアル」なるものがあり、そこに「元々の所有者である発注者が廃棄物処理をするのが原則であるが、建物解体等の大量の廃棄物が発生する場合はそれが困難であるため、元請業者に処理を委託する」みたいな記述がありました。
元は厚生省の通達か何かの記述のようでした。
もう少し社内で色々議論し、法律の範囲内で運用しやすいやり方を検討していきます。
有難うございました。